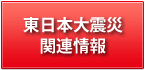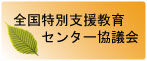特別支援教育法令等データベース 総則 / 報告・答申等 - 特殊教育の改善・充実について(第二次報告) -
平成9年9月19日
特殊教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議
特殊教育の改善・充実について(第二次報告)
I 盲・聾・養護学校等の教育課程の改善
II 教職員の資質の向上
III 今後の課題
児童生徒数等の推移
参 考 資 料
特殊教育の改善・充実について(第二次報告)
平成9年9月19日
特殊教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議
はじめに
我が国における障害者施策は,完全参加と平等をテーマとした「国際障害者年」(昭和56年)と,これに続く「国連・障害者の十年」(昭和58年~平成4年)において,障害者対策に関する長期計画の策定や各種施策の推進により,教育,医療,福祉,労働等の各分野において着実な進展がみられた。その後も「アジア太平洋障害者の十年」(平成5年~14年)という国際的な動向の中で, 「障害者基本法」(平成5年)が制定されるとともに, 「障害者対策に関する新長期計画」(平成5年度~14年度)やその重点実施計画である「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~」(平成8年度~14年度)が策定され,政府全体として,総合的・計画的な取組が進められている。
また,平成8年7月の中央教育審議会第一次答申においては,子供にゆとりの中で[生きる力]をはぐくむことを基本とし,特殊教育を含む教育全般についての見直しが提言された。これを受けて,現在,教育課程審議会においては,完全学校週5日制の下で,各学校がゆとりのある教育活動を展開し,一人一人の幼児児童生徒に[生きる力]を育成することを目指した教育内容の在り方について,幼稚園,小学校,中学校,高等学校,盲学校,聾学校及び養護学校を通じた検討が行われている。
さらに,教育職員養成審議会からは,平成9年7月に「新たな時代に向けた教員養成の改善方策について」第一次答申が出され,これからの時代に教員に求められる資質能力とそのための教員養成課程のカリキュラムの改善や免許制度の弾力化等について提言がなされた。
本協力者会議では,平成8年9月に設置されて以来,これらの動向を踏まえつつ,特殊教育の改善・充実について検討を行い,平成9年1月の第一次報告では,早急な対応が求められていた盲学校,聾学校及び養護学校(以下「盲・聾・養護学校」という。)の高等部の拡充整備と訪問教育の実施,交流教育の充実及び早期からの教育相談の充実について取りまとめた。
本協力者会議は,その後,教育課程審議会及び教育職員養成審議会の審議の状況を踏まえながら,盲・聾・養護学校等の教育課程の改善及び教職員の資質向上の在り方についての検討を重ねてきたが,今回,その検討の結果を第二次報告として取りまとめたので,ここに報告する。
I 盲・聾・養護学校等の教育課程の改善
1 教育課程の基準の改善と状況の変化
(1)前回の学習指導要領等の改訂
平成元年の盲・聾・養護学校の学習指導要領の改訂においては,(1)幼稚園,小学校,中学校及び高等学校(以下「小・中学校等」という。)の教育課程の基準の改善に準じた改善を行うこと,(2)幼稚部から高等部まで調和と統一のある教育を進めるとともに早期教育の充実を図るため,新たに「盲・聾・養護学校幼稚部教育要領」を制定すること,(3)昭和54年の養護学校教育の義務制実施後10年を経て障害の重度・重複化,多様化が進んでいる状況に対応し,児童生徒の障害の種類や程度に応じた教育の一層の充実を図ること,(4)障害のある生徒の社会参加・自立の推進を図る観点から,高等部における職業教育の充実を図ることを基本方針として改訂が行われた。
現在,各学校においては,障害の状態等に応じた多様な教育課程の編成,個別指導や小グループによる指導などの学習集団の工夫,教材・教具の開発と活用など,幼児児童生徒の実態に即した教育が行われているところであるが,時代の進展とともに特殊教育を取り巻く諸状況も大きく変化しており,今日,これらの変化に対応した教育課程の改善が更に求められているところである。
(2)特殊教育をめぐる諸状況の変化
(1) 障害の重度・重複化,多様化
盲・聾・養護学校においては,移動,食事,排泄,衣服の着脱等に際して全面的に介助が必要となるなど,障害の重い者の割合が増加しているほか,二つ以上の障害を併せ有する者の割合が増加している。盲・聾・養護学校の小学部及び中学部における重複障害学級在籍者の割合は,平成元年度の38.0%から,平成8年度には44.1%にまで増加しており,特に,肢体不自由養護学校では,59.7%から71.2%と急増している。また,重複している障害の状態についても,視覚障害,知的障害及び肢体不自由など,三つ以上の様々な障害を併せ有する者がみられるようになってきている。
さらに,平成5年度からの通級による指導の実施,近年における養護学校の拡充整備,平成9年度からの高等部の試行的な訪問教育の実施などにより,特殊教育の対象者の障害の状態は,多様化してきている。
こうしたことから,特殊教育の対象となる幼児児童生徒の障害の重度・重複化,多様化の傾向は,今後,更に拡大するものと予測される。
(2) 高等部への進学率の増加
中学部から高等部へ進学する者の割合は,盲学校及び聾学校では従来から90%以上となっている。養護学校については,平成2年3月卒業者の64.6%から,平成8年3月卒業者では78.0%まで増加している。
また,中学校特殊学級から高等部へ進学する者についても,平成2年3月卒業者の39.7%から,平成8年3月卒業者では53.2%まで増加している。
今後,中学部や中学校特殊学級から高等部へ進学する者の割合は,高等部の整備の進展等に伴い,更に増加していくものと予測される。
(3) 早期からの教育的対応
本協力者会議第一次報告でも述べたとおり,近年においては医学の進歩等により,特殊教育の対象となる乳幼児の障害の早期発見が可能となってきていることから,できる限り早期から教育的な手だてを講じていくことは,その後の障害の改善を図る上で大きな成果を期待できるものとなっており,0歳からの教育相談や幼稚部教育に対する二ーズが高まってきている。
(4) 卒業後の進路の変化
高等部(本科)卒業後の進路については,学校種別によって異なっているが,近年の特徴として,養護学校高等部卒業者のうち社会福祉施設・医療機関へ入所する者の割合が増加する一方,全般的な雇用環境が厳しくなる中で企業等へ就職する者の割合が低下する傾向にある。特に,盲・聾・養護学校全体の就職者の割合は,平成2年3月の卒業者では35.7%であったが,平成8年3月の卒業者では29.9%にまで低下している。
また,障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され,知的障害者を算定基礎に加えた法定雇用率が設定されるなど,雇用関係施策も進められてきている。
(5) 交流教育の重視
盲・聾・養護学校等の幼児児童生徒と小・中学校等の幼児児童生徒や地域社会の人々との交流については,学校行事を中心とした活動が進められてきている。このような交流教育については,本協力者会議第一次報告で述べたとおり,障害のある幼児児童生徒のみならず,すべての幼児児童生徒や教員,地域社会の人々にとって非常に有意義な活動であり,地域や学校の実態に応じて,多様で継続的な交流の一層の推進が求められている。
このように,特殊教育をめぐっては様々な変化がみられ,幼児児童生徒の保護者をはじめとした関係者からは,これまで以上に一人一人の実態を考慮したきめ細かな教育の充実が求められている。
2 教育課程の改善の基本的な考え方
近年,障害のある者が障害のない者と同等に生活し,活動する社会を目指すノーマライゼーションの理念が広く認識され,障害者が社会参加できるような社会づくりは,今後一層進展するものと予測される。このような中で,障害のある幼児児童生徒の能力や可能性を最大限に伸ばし,社会参加・自立の基盤となる[生きる力]を培うことがますます重要となっている。
このため,盲・聾・養護学校,小学校及び中学校の特殊学級又は通級による指導においては,一人一人の障害の種類や程度等に応じて,様々な工夫と配慮のもとに,手厚く,きめ細かな教育を行う努力が重ねられてきているが,今後,こうした特殊教育の果たす役割はますます重要になるものと考える。
また,盲・聾・養護学校等における個に応じた指導の実践などの種々の取組は,他の学校の教育を充実する上で十分に生かされるものである。
今回の盲・聾・養護学校等の教育課程の改善に当たっては,前述の特殊教育の重要性を十分踏まえ,国際化,情報化等の進展,社会の価値観の多様化,障害者を取り巻く環境の変化等に対応し,より一層幼児児童生徒一人一人の実態に即した教育を推進する観点から,教育課程の改善・充実を図ることが必要である。具体的な改善の視点としては,次のようなことが考えられる。
(1) 幼稚園,小学校,中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善に準じた改善
盲・聾・養護学校の教育課程の基準の改善に当たっては,幼稚園,小学校,中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善の趣旨を踏まえ,基本的には,これらの改善に準じた改善を図る必要がある。その際,今後の完全学校週5日制の下で,各学校がゆとりある教育活動を展開し,一人一人の幼児児童生徒に[生きる力]を育成することができるように配慮することが特に重要である。
(2) 障害の重度・重複化,多様化への対応
幼児児童生徒の障害の重度・重複化,多様化に適切に対応するため,養護・訓練,知的障害養護学校の各教科,重複障害者等に関する特例等についての改善・充実を図るとともに,個別の指導計画を作成するなど,個に応じた指導の一層の充実を図る必要がある。さらに,生徒の卒業後の社会生活を充実する観点から,体験的な活動を一層重視する必要がある。
(3) 早期からの適切な教育的対応
本協力者会議の第一次報告でも述べたとおり,障害のある子供に対しては,早期からの適切な教育的対応を図ることが有効であり,0歳からの教育相談及び幼稚部の教育内容・方法等の改善・充実を図る必要がある。
(4) 職業的な自立の推進
高等部卒業後の企業等への就職率が低くなってきている状況を踏まえ,職業観や勤労観を育成し職業的な自立を一層推進する観点から,学科の編成,教育内容・方法等の改善・充実を図る必要がある。
(5) 軽度の障害のある児童生徒への対応
特殊学級や通級による指導の対象となる児童生徒に対し,その実態に応じた適切な教育を進めるため,指導内容・方法等の改善・充実を図る必要がある。
3 盲・聾・養護学校の教育の改善
(1)教育課程の編成と授業時数
盲・聾・養護学校には,幼稚部,小学部,中学部及び高等部が設置されており,それぞれ,幼稚園,小学校,中学校及び高等学校に準ずる教育を行うとともに,障害に基づく種々の困難を克服するために必要な知識,技能,態度及び習慣を養うことを目標とした教育が行われている。
このため,これらの学校の教育課程は,幼稚園に準じた領域(健康,人間関係,環境,言葉,表現),小学校,中学校及び高等学校に準じた各教科,道徳,特別活動に加えて,障害の状態の改善・克服をねらいとした特別の領域である「養護・訓練」で編成されている。また,知的障害養護学校の各教科については,対象とする児童生徒の精神発達の遅れから,小学校,中学校及び高等学校の各教科の目標・内容の学習が困難であるため,その障害の学習上の特性も考慮した独自の目標・内容が示されている。
(1) 教育課程の枠組み
盲・聾・養護学校の教育課程の基準の改善に当たっては,従来と同様,基本的には,小・中学校等の教育課程の基準の改善に準じた改善を行うことが適当であると考える。
ただし,前述のとおり,盲・聾・養護学校では小・中学校等に準じた教育と障害の状態の改善・克服を図るための教育とを,限られた授業時数の中で,個々の実態に応じて適切かつ効果的に展開していかなければならない。
このため,例えば,中学部における選択教科や総合的な学習の時間(仮称)については,生徒の障害の状態等によっては,養護・訓練に充てることができるようにするなど,児童生徒及び地域や学校の実態に応じた弾力的な取扱いができるようにする必要がある。
また,中学部及び高等部におけるクラブ活動の取扱いについては,生徒の実態や通学の状況等から,部活動の実施が困難な場合も見受けられることから,現在実施されているクラブ活動の意義や教育効果等を十分踏まえて検討する必要がある。
(2) 授業時数等
小学校及び中学校では,各学年ごとに年間総授業時数並びに各教科等に充てる年間授業時数が定められている。盲・聾・養護学校の小学部及び中学部においては,各学年ごとの年間総授業時数は小学校及び中学校に準じることとし,その中で各教科等に充てる授業時数を適切に定めることとされている。また,幼稚部の教育時間や年間教育週数,高等部の週当たり授業時数(知的障害養護学校においては,各学年の総授業時数)や年間授業週数は,それぞれ幼稚園及び高等学校と同様であるほか,小学部,中学部及び高等部の1単位時間についても,それぞれ小学校(45分),中学校(50分)及び高等学校(50分)と同様である。
このような,各教科等の授業時数や年間授業週数,1単位時間の運用については,幼児児童生徒の障害の状態,興味・関心,将来の進路希望などを十分考慮し,より効果的な教育を行うことができるよう,その弾力的な取扱いを一層推進する必要がある。
また,現行,小学部及び中学部においては,重複障害又は療養中の児童生徒の教育を行う場合若しくは訪問教育を行う場合について,特に必要がある場合には,その実情に応じた授業時数を適切に定めることができることとされている。高等部においても,生徒の障害が重度・重複化の傾向にあることから,訪問教育の試行的実施の状況を踏まえつつ,単位制との関連を考慮しながら授業時数の弾力化を図ることについて検討する必要がある。
(2)教科・科目等の編成と内容
(1) 幼稚部の教育
ア 教育相談の位置づけ
本協力者会議第一次報告では,障害のある子供に対し,できる限り早い時期から教育的な手だてを講じていくことにより,その後の障害の状態の改善・克服に大きな効果がみられることから,幼稚部の整備や教育相談の一層の充実,盲・聾・養護学校が地域での教育相談センター的な役割を果たすことなどについて提言したところである。これを受け,平成9年度から,教育,医療,福祉関係機関が一体となった教育相談体制についての研究を行う「早期教育相談等の在り方に関する実践研究」が進められている。
今後,盲・聾・養護学校における教育相談をはじめとした早期からの教育的対応を一層充実させるためには,0歳からの教育相談に関する事項を幼稚部教育要領に明記し,教育相談及び幼稚部教育を充実する必要がある。また,教育相談に関し,小学部,中学部及び高等部の学習指導要領にも明記するなど,その充実を図ることについて検討する必要がある。
イ 教育課程の改善
(ア) 盲学校,聾学校,肢体不自由養護学校及び病弱養護学校においては,幼稚園に準じた領域である健康,人間関係,環境,言葉,表現のねらいや内容等については,幼稚園教育要領の改善に準じて改善を図ることが適当であると考える。
また,知的障害養護学校においては,小学部,中学部及び高等部では児童生徒の障害の状態等に応じた独自の各教科の目標・内容が定められていることや,幼稚部に在学する幼児の発達段階等を踏まえ,健康,人間関係,環境,言葉,表現の各領域の内容等について検討する必要がある。
(イ) 現行の幼稚部における養護・訓練のねらいや内容等については,幼稚部の他の領域の示し方に合わせて,小学部,中学部及び高等部とは異つた示し方となつているが,小学部,中学部及び高等部との一貫性や他の領域との関連を踏まえてその示し方を検討する必要がある。
(ウ) 幼児の障害の種類や程度,発達段階等に応じた指導を一層進める観点から,幼稚部教育要領に,重複障害の幼児への配慮事項を明記することや,現行,学校種別ごとにそれぞれ1項目ずつ示されている指導計画作成上の留意事項を更にきめ細かく示すことなどについて検討する必要がある。
(2) 小学部,中学部及び高等部の各教科等
ア 盲学校,聾学校,肢体不自由養護学校及び病弱養護学校
現行の盲学校,聾学校,肢体不自由養護学校及び病弱養護学校の各教科の構成及び目標・内容等については,小・中学校等に準ずるほか,高等部においては障害の特性に応じた職業に関する教科・科目が設けられており,また,各教科の指導上の配慮事項が示されている。各教科の目標・内容等の改善に当たっては,小・中学校等における改善に準じた改善を行うほか,次の点について検討する必要がある。
(ア) 小学部及び中学部
児童生徒の障害の状態の多様化などに応じたよりきめ細かな指導を進めることができるよう,現行,学校種別に3から6項目が示されている各教科の指導上の配慮事項を更にきめ細かく示すことについて検討する必要がある。
(イ) 高等部
a 高等部においても,小学部及び中学部と同様に,各教科の指導上の配慮事項を更にきめ細かく示すことについて検討する必要がある。
b 高等部においては,職業的な自立を目指し,その障害の特性等に応じた様々な職業教育が行われているが,近年の社会の変化や雇用環境の変化,生徒の障害の重度・重複化,多様化などにより,高等部卒業後,企業等へ就職する者の割合が低くなってきている。このような状況に対し,社会や企業等においては,障害者への理解を深め,障害者の雇用の促進に努めることが求められる。また,障害のある生徒についても,積極的に社会参加・自立を目指すとともに,望ましい職業観や勤労観を身に付けることができるようにすることが重要である。これらの点を踏まえて,職業的な自立を一層推進する観点から,進路指導との関連を考慮しつつ学科の構成や教科・科目等の改善を図る必要がある。
(a) 職業的な自立を図る上で極めて有効な国家資格等を取得するため,盲学校においては保健理療科(あん摩マッサージ指圧師の養成),理療科(あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師の養成),理学療法科(理学療法士の養成)が設けられ,また,聾学校においては理容科・美容科(理容師・美容師の養成),歯科技工科(歯科技工士の養成)が設けられている。
これらの資格取得に当たっては,関係法令により当該学科において修得すべき科目及びその授業時数等が定められているが,今後の完全学校週5日制の実施に伴い全体の授業時数が縮減された場合,資格取得に必要となる授業時数の確保についての問題が生じてくる。また,生徒の能力・適性,興味・関心等の多様化に対応するためには,選択科目を拡大するなど,各学校において特色ある教育課程を編成することができるようにすることが重要である。このため,文部省においては,関係省庁とも協議し,職業資格の取得要件となっている科目の内容や授業時数等について検討する必要がある。
(b) 盲学校,聾学校,肢体不自由養護学校及び病弱養護学校においては,社会の国際化,情報化,科学技術の進歩や,高等部に在学する生徒の障害の状態や進路希望の多様化等に対応するため,情報に関する教科・科目の導入や既存の教科・科目の見直しを行う必要がある。また,新たな学科の設置や既存の学科の改編についても併せて検討を行う必要がある。
さらに,普通科に在学する生徒について,早い時期から,職業観や勤労観を育成していくことは,将来の社会参加・自立を進める上で重要であることから,生徒の実態等に応じ,職業に関する教科・科目の開設やコース制の導入などについて検討する必要がある。
(c) 企業等における現場実習は,生徒の職業意識を高め,学校生活から社会生活への円滑な移行を進める上で重要な役割を果たしている。このため,職業に関する各教科の指導においては,生徒及び地域や学校の実態に応じて現場実習の実施に十分配慮するよう学習指導要領に明記するなど,現場実習の一層の充実を図る必要がある。
イ 知的障害養護学校
知的障害養護学校の各教科の構成及び目標・内容等については,精神発達に遅れのある児童生徒の実態に応じた独自の目標・内容等が示されている。各教科の目標・内容等の改善に当たっては,次の点について検討する必要がある。
(ア) 児童生徒を取り巻く生活環境が変化してきていることや,知的障害養護学校高等部における生徒の障害の程度が軽度から重度まで幅広くなってきていること,さらには,盲学校等において知的障害を併せ有する者が増加し,知的障害養護学校の各教科を中心とした教育課程が編成されるようになってきていることなどを踏まえ,小学部,中学部及び高等部の各教科の内容等について検討する必要がある。
(イ) 国際化の進展に伴い,外国人と触れ合う機会や日常生活の様々な場面で英語が用いられることが多くなっており,一部の知的障害養護学校では,高等部において英語の指導が行われるようなってきている。今後,国際化は一層進展するものと予測され,生徒の日常生活を豊かにし,また,卒業後の社会生活への適応を円滑に進めるためには,知的障害養護学校高等部の選択教科として新たに「外国語(英語)」を設けることについて検討する必要がある。
(ウ) 職業に関する教科については,近年の産業構造や雇用環境の変化,高等部への進学率の増加等に対応し,盲学校等と同様に,職業的な自立を一層推進する観点から,次のような改善を図ることについて検討する必要がある。
a 産業構造の変化等により,高等部卒業後サービス産業に進む者が増加していることから,サービス産業に関する基礎的・基本的な知識や技術,事務機器等の操作,実習などを内容とした新たな教科の設置について検討する必要がある。
b 前回の学習指導要領の改訂において,職業教育を主とする学科のうち標準的な学科として「家政科」,「農業科」及び「工業科」が示された。現在,高等部のみを置く養護学校を中心として職業教育を主とする学科が設けられてきているが,標準的な学科のほか,多様な職業に関する基礎的・基本的な教育を行う学科として「産業科」が,平成8年度には26校に設置されている。このような実態を踏まえ,学習指導要領に定める標準的な学科として,上記のサービス産業に関する教科を主とした学科「商業科」(仮称)や「産業科」を新たに示すことについて検討する必要がある。
c 高等部における上記の教科や学科の設置に関連し,必修教科となっている「職業」及び「家庭」の内容について見直すとともに,中学部における「職業・家庭」について,高等部への進学率が増加してきていることを踏まえ,高等部における職業に関する教科との関連を考慮した見直しを図る必要がある。
d 現場実習については,盲学校等と同様,生徒及び地域や学校の実態に応じて現場実習の実施に十分配慮するよう学習指導要領に明記するなど,現場実習の一層の充実を図る必要がある。
(エ) 学習指導要領においては,各教科,道徳,特別活動,養護・訓練の別に目標・内容等が示されているが,精神発達に遅れのある児童生徒の場合,領域別,教科別に指導するよりも,生活に即した内容を取り上げ,実際的な活動を中心とした総合的な学習が適合しやすいことから,各教科や領域の全部又は一部を合わせた指導を中心とした教育が行われている。このため,各教科等の示し方と実際の指導との関連を明確にするなど,学習指導要領における示し方について検討する必要がある。
(3) 養護・訓練
盲・聾・養護学校においては,従前は,肢体不自由養護学校の「体育・機能訓練」や,病弱養護学校の「養護・体育」など,独自の教科が設けられており,これらの教科の中で,障害の状態を改善・克服するための指導が行われていた。こうした指導は,一人一人の児童生徒の障害の種類や程度,発達の状態等に応じて,学校の教育活動全体を通して配慮する必要があり,また,それぞれに必要とする内容は,個別的,計画的かつ継続的に指導すべきものであることから,盲・聾・養護学校に共通の特別の指導領域として,昭和46年に初めて「養護・訓練」が設けられた。
また,平成元年の学習指導要領の改訂においては,幼児児童生徒の障害の多様化等に対応する観点から,内容の再構成等が行われたところであるが,近年の盲・聾・養護学校に在学する幼児児童生徒の障害の重度・重複化,多様化が一層進む中で,いかに養護・訓練の指導を充実させるかが重要な課題となっている。本協力者会議としては,次の点について見直しを行う必要があると考える。
ア 目標,名称
養護・訓練は,幼児児童生徒が自らの障害の状態の改善・克服を目指す主体的な活動であるが,養護・訓練という名称から他動的な指導とみられ,実際の指導と異なる印象があるとの指摘がある。また,目標については,養護・訓練の創設以来同様の示し方となっているが,この間,障害者を取り巻く社会環境や,幼児児童生徒の実態が大きく変化してきている。こうした点を踏まえ,一人一人の幼児児童生徒の実態に対応した活動であることや,自立を目指した主体的な活動であることを一層明確にする観点から,目標及び名称について検討する必要がある。
イ 内容の構成と示し方
現行の小学部,中学部及び高等部における養護・訓練の内容は,「身体の健康」,「心理的適応」,「環境の認知」,「運動・動作」及び「意思の伝達」の五つの視点から18項目が示されており,個々の児童生徒の実態に応じて,これらの内容の中から必要な事項を選定し,相互に関連づけて指導することとされている。
近年,児童生徒の障害の状態は多様化してきており,今後,こうした多様化の傾向は一層顕著になるものと予測されることなどから,このような児童生徒の実態に応じた適切かつ効果的な指導を進めるため,具体的な指導をよりイメージしやすくなるよう,内容の構成や示し方について検討する必要がある。
ウ 授業時数
盲学校,聾学校,肢体不自由養護学校及び病弱養護学校における養護訓練の授業時数は,現行,年間105単位時間を標準とするが,児童生徒の実態に即した授業時数を配当することとしている。今回の教育課程の基準の改善においても,養護・訓練の授業時数については,これまでと同様の取扱いとすることが適当と考えられるが,児童生徒の障害の種類や程度,発達段階等に応じた弾力的な取扱いを一層推進する必要がある。
エ 知的障害教育における養護・訓練
知的障害養護学校においては,その障害の特性に応じた各教科の目標内容が示されており,精神発達の遅れそのものへの対応は各教科等で行うこととなる。しかし,知的障害養護学校に在学する幼児児童生徒には,精神発達の遅れに伴って,言語,感覚・知覚,運動,情緒・行動等の発達上の偏りが多く見られ,このような発達の偏りへの対応として養護・訓練が位置づけられている。
また,知的障害養護学校の養護・訓練の指導は,領域・教科を合わせた指導の形態により行われる場合が多く,個々の児童生徒について,養護・訓練の目標・内容等が明確にされていない例も見受けられることや,知的障害養護学校の各教科と養護・訓練との関連が分かりにくいとの指摘もある。
このため,知的障害養護学校における各教科と養護・訓練の関連を明確にし,知的障害養護学校における指導はもとより,他の学校における知的障害を併せ有する者に対するより適切な指導が行われるよう検討する必要がある。
オ 個別の指導計画
幼児児童生徒の障害の種類や程度等は,一人一人異なっていることから,養護・訓練の指導は,個々の実態に応じた個別の指導計画に沿って行われることが大切である。このため,養護・訓練における個別の指導計画の作成の必要性を,学習指導要領上,より明確に示すことについて検討する必要がある。
なお,学校によっては,養護・訓練のほか各教科等の指導に関しても,個別の指導計画を作成したきめ細かな指導が進められており,こうした状況をも踏まえつつ,個別の指導計画の在り方について検討する必要がある。
(3)重複障害者等の教育課程
盲・聾・養護学校の学習指導要領では,児童生徒の障害の状態等に応じた適切な教育を行うことができるよう,例えば,次のような教育課程編成の特例が定められている。
(1) 知的障害を併せ有する児童生徒については,各教科の目標・内容の全部又は一部を,知的障害養護学校の各教科の目標・内容の全部又は一部に替えること
(2) 重複障害の児童生徒のうち,学習が著しく困難な者については,各教科,道徳,特別活動の目標・内容の一部又は各教科に替えて養護・訓練を主とした指導を行うこと
(3) 障害の状態により教科の学習が困難な児童生徒については,各教科の目標・内容の一部を欠くことができること。また,各教科の目標・内容の全部又は一部を当該学年の前各学年の目標・内容の全部又は一部に替えることができること
各学校においては,多様な児童生徒の実態に応じて,これらの規定等を適用した教育課程による指導が行われてきているが,近年,盲・聾・養護学校に在学する児童生徒の障害の重度・重複化が一層進んでおり,それぞれの児童生徒の実態に応じたより効果的な指導を行うことができるよう,教育課程編成の在り方,指導内容・方法等について検討する必要がある。
ア 教育課程編成の一層の弾力化
(ア) 高等部の教科・科目の学習が困難な場合には,現行,中学部の教科の目標・内容に代替して教育を行うことができるようになっているが,障害の状態が極めて重度であって,中学部の教科の目標・内容に代替しても学習が困難な場合には,小学部の教科の目標・内容と代替できるよう,代替の範囲を拡大することについて検討する必要がある。
(イ) 小学部又は中学部において,教科の学習が困難な場合には,幼稚部教育要領に示す内容の中から,必要な事項を取り入れた指導を行うことができるようにすることについて検討する必要がある。
(ウ) 現行,肢体不自由養護学校又は病弱養護学校の高等部在学者で,療養中のため通学して教育を受けることが困難な場合には,各教科・科目の一部を通信により教育を行うことが認められているが,これら以外であっても,障害の進行などにより通学が困難となった場合には,通信により教育を行うことができるようにすることについて検討する必要がある。
イ 教育課程編成の明確化
重複障害者等に対する教育課程の編成については,個々の実態に応じた適切な教育を行うことができるよう学校教育法施行規則及び盲・聾・養護学校の学習指導要領で種々の特例が定められている。
しかし,現行の特例に関する仕組みが分かりにくいとの指摘があることや,今後一層の障害の重度・重複化に対応していくためには,重複障害者等の教育課程編成に関する規定を整理し,適切な教育が展開されるようにする必要がある。
ウ 指導内容・方法の工夫
各学校種別を通じて重複障害の児童生徒が増加してきており,併せ有する障害の種類や程度は実に様々な状況で,三つ以上の障害を併せ有する者もみられるようになってきている。重複障害者等については,その実態を的確に把握し,種々の特例を活用した適切な教育課程を編成するとともに,体験的な活動を通して効果的な指導を行うことが重要であり,個別の指導計画の作成を明確にするなど,一人一人の実態に応じた指導内容・方法等について,更なる工夫と改善を図る必要がある。
(4)訪問教育に係る教育課程
本協力者会議は,第一次報告において,障害のある生徒に対し,義務教育段階に引き続き高等部で教育を行うことは,社会参加・自立のための資質の育成に大きな意義があることから,高等部の拡充整備及び高等部における訪問教育を実施する旨提言した。これを受け,文部省では,平成9年度より現行制度の枠内で高等部における訪問教育を試行的に実施できる旨を各都道府県教育委員会に通知し,平成9年4月から,32都道府県・92校で164人を対象として高等部の訪問教育が試行的に実施されている。
また,小学部及び中学部において実施されている訪問教育については,小学部・中学部学習指導要領に訪問教育に関する特例が示されており,その運用については昭和53年に示された「訪問教育の概要(試案)」により行われている。
今回の教育課程の基準の改善においては,現在の高等部における試行的実施の状況や小学部及び中学部でのこれまでの実施の状況等を踏まえ,高等部における訪問教育について高等部学習指導要領に明確に位置づけるとともに,小学部,中学部及び高等部の関連を図った訪問教育の実施方法等について,検討する必要がある。
(5)情報化の進展への対応
近年の情報化の急速な進展に伴い,各学校においてもコンピュータ等の情報機器の整備が進められ,平成8年3月現在,盲学校及び聾学校ではすべての学校に,養護学校では約98%の学校にコンピュータが設置されている。また,学習用ソフトウェアについても,市販のものや各学校が創意工夫して開発したものが整備されてきており,盲・聾・養護学校における1学校当たりのソフトウェアの平均保有本数も,約27種類・50本となっている。
盲・聾・養護学校における情報機器の活用は,例えば,盲学校における点字と普通の文字との相互変換やネットワークを活用した点字情報の拡大,聾学校における発音の状態を画面に表示しての発音・発語の指導,知的障害養護学校におけるコンピュータ・グラフィックスによるアニメーションを取り入れた学習指導,肢体不自由養護学校におけるコンピュータを活用したコミュニケーションの指導,病弱養護学校におけるコンピュータ・シミュレーションを活用した体験学習等多岐にわたっている。
特殊教育の分野において,情報機器の効果的な活用は,幼児児童生徒の興味・関心や学習意欲を高めるとともに,障害に基づく種々の困難の克服,各教科等の学習の補完,情報活用能力の育成等に極めて有効であり,今後一層の積極的な活用について工夫していく必要がある。
4 特殊学級及び通級による指導の充実
特殊学級は,障害の程度が比較的軽度な児童生徒に対し,障害の状態等に応じたきめ細かな教育を行うため,小学校及び中学校において特別に編制された小人数の学級で,弱視,難聴,知的障害,肢体不自由,病弱・身体虚弱,言語障害及び情緒障害を対象とした学級がある。特殊学級は,全国の小学校及び中学校の約半数に設置されており,学級数は年々増加し,平成8年度では,約2万3千学級に6万6千人の児童生徒が在籍している。
また,通級による指導は,小学校及び中学校の通常の学級に在籍している軽度の障害のある児童生徒のうち,障害の状態等に応じた特別な指導を一部必要とする者のための教育形態として,平成5年度に新たに制度化された。通級による指導を受ける児童生徒は急増しており,平成5年度の約1万2千人から平成8年度には2万人を超える状況となっている。
平成8年度現在,盲・聾・養護学校の小学部及び中学部も含めた義務教育段階における特殊教育の対象者は,約13万5千人であり,特殊学級及び通級による指導の対象者は,このうちの約64%を占めている。
(1)特殊学級の充実
特殊学級の教育課程は,基本的には,小学校及び中学校の学習指導要領によることとなるが,障害の状態等に応じた教育を行うため,特に必要がある場合には,盲学校,聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領を参考とした特別の教育課程を編成することができることとされている。
現行の小学校及び中学校の学習指導要領においては,障害のある児童生徒などについては,児童生徒の実態に即した適切な指導を行う旨の規定がなされているが,特殊学級に関する記述がないことから,特殊学級の指導についての全校的な理解が得られにくい状況にある。このため,小学校及び中学校の学習指導要領に,特殊学級に関する事項を明記し,児童生徒の障害の状態等に応じた指導の一層の充実を図る必要がある。
(2)通級による指導の充実
通級による指導の対象となる児童生徒は,各教科等の指導の大半を通常の学級で受けながら,障害の状態に応じた特別の指導を受けることとなるため,平成5年度の制度化に伴い示された文部省告示(平成5年1月28日文部省告示第7号)により,通常の学級の教育課程に加え,又はその一部に替えた特別の教育課程を編成することができることとされている。また,同告示により,特別の指導に係る授業時数は,週当たり1~3単位時間を標準とし,当該指導に加えて各教科の補充指導を行う場合には,おおむね週当たり8単位時間以内とされている。
通級による指導については,個々の実態に応じた指導内容・指導形態が工夫されてきているところであるが,対象となる児童生徒の急増やこれに伴う障害の状態等の多様化に適切に対応していくためには,小学校及び中学校の学習指導要領に,通級による指導に関する事項を明記し,児童生徒の障害の状態等に応じた指導の一層の充実を図る必要がある。
5 交流教育の充実
盲・聾・養護学校等の幼児児童生徒と,小・中学校等の幼児児童生徒や地域社会の人々が,様々な機会を通じて共に活動し,互いに触れ合う交流教育は,すべての幼児児童生徒の豊かな人間性や社会性を育成する上で大きな意義があるとともに,地域社会の人々が,障害のある幼児児童生徒とその教育に対する正しい理解を深める上でも重要な活動となっている。
このような交流教育の意義やその一層の推進については,平成8年7月の中央教育審議会第一次答申においても提言されているが,本協力者会議も第一次報告において,交流教育の意義を踏まえ,多様で継続的な交流教育の一層の推進や,教育課程上に位置づけることの必要性などについて提言したところである。これを受け,平成9年度から,すべての都道府県において「交流教育地域推進事業」が実施され,多様な交流が展開されている。
(1)小・中学校等の学習指導要領等における位置づけ
交流教育の一層の充実を図るためには,小・中学校等における積極的な取組が重要である。現行の幼稚園教育要領並びに小学校,中学校及び高等学校の学習指導要領においては,盲・聾・養護学校の幼児児童生徒との交流については明確になっていないことから,これを明確に位置づけ,特別活動や総合的な学習の時間(仮称)をはじめとした様々な教育活動の中で,盲・聾・養護学校の幼児児童生徒との交流を推進する必要がある。
また,小学校及び中学校の通常の学級と特殊学級との交流については,学校や児童生徒の実態等を十分考慮し,可能な限り,各教科等における交流のほか,日常の学校生活における様々な場面で交流が図られるよう配慮する必要がある。
(2)盲・聾・養護学校の学習指導要領等における位置づけ
盲・聾・養護学校における交流教育の一層の充実を図るため,学習指導要領の総則における交流教育の位置づけについて,現行の「指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項」としての示し方から,教育課程の編成に関して特に配慮すべき事項として「一般方針」に示すなどの見直しを行う必要がある。
また,盲・聾・養護学校卒業後の社会生活を考慮し,現場実習などを通じた企業等との交流,社会に貢献する活動を通じた交流など,地域における社会生活と結び付いた活動への取組について配慮する必要がある。特に,完全学校週5日制の実施に向けて,学校・家庭・地域社会が一体となった活動を充実・発展させていく観点からも,それぞれの地域において交流を深めるための更なる取組が強く望まれるところである。
なお,こうした交流教育が幅広くかつ無理なく継続的に実施することができるよう,例えば,総合体育大会や文化祭を通じた交流,学校新聞の交換やパソコン通信を活用した交流など,その実施方法について工夫する必要がある。
II 教職員の資質の向上
教育職員養成審議会は,平成9年7月28日に「新たな時代に向けた教員養成の改善方策について(第一次答申)」(以下「教養審第一次答申」という。)を取りまとめ,これからの時代の教員に求められる資質能力とそのための教員養成カリキュラムの改善や免許制度の弾力化を提言した。今後の教員養成課程は,時代の変化の中で大きく変わろうとしている。
その中にあって,幼児児童生徒の多様な障害の状態に対応して,個に応じた適切な教育を行う必要がある特殊教育担当教員については,特にその専門性の確保が重要な課題となっている。本協力者会議では,去る6月20日に,教養審第一次答申の取りまとめに際して,同審議会に対し特殊教育を担当する教員等の養成関係に関して提言を行ったが,今回第二次報告を取りまとめるに当たり,特殊教育をめぐる状況の変化の中で特殊教育担当教員等の資質向上のために取り組むべき全般的な方策について,以下に提言することとしたい。
1 現状と課題
(1)特殊教育担当教員の養成・任用等の現状と課題
ア 盲・聾・養護学校の教員については,幼児児童生徒の障害の状態に即した教育を行うため,小・中学校等に比べて,特別な専門性が要求されることから,小・中学校等の教員のいわゆる基礎免許状に加えて,盲・聾・養護学校の学校種ごとの特殊教育教諭免許状の所有が求められている(教育職員免許法第3条)。 (なお,当分の間はこの特殊教育教諭免許状がなくても盲・聾・養護学校の教諭となることができる特例(同法附則)が設けられている。)
しかしながら,現状では盲・聾・養護学校の教員の特殊教育教諭免許状の保有率は必ずしも高いとはいえない状況にある。
その背景として,同一都道府県内における盲・聾・養護学校の数が少なく,養成・採用の規模が小さいことや,その中で組織の活性化を図るために異校種間の人事交流を行っていること,学校によっては,教科指導の水準を確保するため,広く基礎免許状のみを有する者の中からも優れた人材を求める必要があること等の事情が考えられる。
また,人事交流によって様々な得意分野をもった人材が盲・聾・養護学校に配置されたり,また,小・中学校等に特殊教育の経験のある者が配置されることは,教育全体の水準の向上や活性化につながる側面もある。
イ 特殊教育担当教員の資質は,幼児児童生徒に対する教育的愛情,人間の成長・発達や障害についての理解,特殊教育に対する意欲等が基本であり,免許状の所有のみをもって,その適性を一律に論ずることができないことはもとよりである。
しかしながら,小・中学校に比べて,特別の専門性を必要とする盲・聾・養護学校の教育においては,基本的には,配置された教員に対し,その基礎的な専門性の裏付けとなる特殊教育教諭免許状を有することを求めるべきと考える。
このことは,盲・聾・養護学校の組織全体としての専門的力量を高めていく上でも大切なことであり,このような考え方に立って,今後,盲・聾・養護学校における特殊教育教諭免許状保有率の向上を図っていく必要がある。
また,特殊学級担当教員については,法律上特殊教育教諭免許状の所有は求められていないが,児童生徒の障害の種類・程度に即した教育の専門性を求められることは同様であり,担当する児童生徒の障害の種別に対応した特殊教育教諭免許状の保有率の向上を図っていくことが望ましい。
(2)特殊教育の現職研修の現状と課題
ア 特殊教育を担当する現職教員の専門性を向上させるため,国立特殊教育総合研究所は,特殊教育指導者に対する長期・短期の研修や新たな諸課題に対応する講習会を開催している。
また,大学は,現職教員の専門性を高める内地留学生の受け入れや,より上級の免許状の取得を可能にする認定講習の開催等を行っている。
都道府県は,近年の特殊教育を取り巻く諸課題に対応した各種の研修会を実施するとともに,免許状取得のための認定講習を開催している。この場合,きめ細かく認定講習を開催し,3年程度で免許状を取得できる県もあれば,特殊教育に関する認定講習の講座の開催数が少ない県も多く,中には免許状取得に10年近くを要するような場合も見受けられる。
イ このような現状を改善するため,国立特殊教育総合研究所や教員養成大学等は,引き続き専門性の高い研修の充実を図るとともに,特に都道府県単位では対応することが困難な研修について,積極的に企画,実施していく必要がある。
また,認定講習等が教員の需要に十分応えられていない都道府県にあっては,その拡充を図る必要がある。
さらに,今後は放送メディア等を活用した通信教育や情報ネットワークを活用した研修等を奨励,助長するなど,新たな研修機会の拡充についても検討する必要がある。
(3)特殊教育をめぐる状況の変化に対応した教員の資質向上の課題
特殊教育担当教員の資質については,上記のようにそれぞれの学校種に応じた教員免許状を取得することにより,基礎的な専門性を確保する必要があるが,これとともに,特殊教育をめぐる今日的な諸状況を踏まえ,次のような課題に対応した教員の養成・研修制度の改善を図る必要がある。
(1) 障害の重度・重複化への対応
重度・重複障害の幼児児童生徒が増加していることに対応し,複数の障害に対応した専門性を習得することができるよう養成課程の改善を図るとともに,重複障害の幼児児童生徒の指導に当たるための研修の充実を図る必要がある。また,重度・重複障害の幼児児童生徒に対する実践的指導力を向上するため,担当者の学校内外の相互研修や医療・福祉施設における実地研修等の機会を積極的に設けていく必要がある。
(2) 早期からの適切な教育の充実
第一次報告で述べたように,障害のある乳幼児及びその保護者に対し,育児の悩みなどの相談に応じたり,養育上の指針を助言するための教育相談の機能を充実していく必要がある。就学前の早期からの教育相談を適切に行うためには,学校の教育相談体制の整備,医療・福祉機関との緊密な連携を図るとともに,幼稚部担当教員や教育相談担当教員の資質向上を図るための多様な研修の機会を設ける必要がある。
(3) 雇用環境に対応する職業教育の充実
「障害者対策に関する新長期計画」や「障害者プラン」等においてノーマライゼーションの理念が示され,社会全体の障害者雇用に対する理解は広く浸透しつつある。「障害者の雇用の促進等に関する法律」において,障害者雇用率の算定基礎として知的障害者も含まれることになるなど,近年,障害のある者の雇用環境は大きく前進してきているといえる。
他方,科学技術の高度化や,従来障害者が担っていた職種への健常者の進出等の状況の変化の中で,障害者が社会的に自立していくためには,新たな職域の開拓等も求められている。このような状況の変化に対応するため,社会人講師の確保等多様な教員の養成・確保や,教員の職業教育や進路指導にかかわる指導力の向上を図る必要がある。
(4) 特殊学級及び通級による指導の担当教員の専門性の向上
現在,特殊学級及び通級による指導の担当教員のかなりの割合の者が特殊教育教諭免許状を有しない状況に鑑み,新任の担当者に対する事前研修の実施や,特殊教育教諭免許状の取得に向けた養成・研修の充実を図る必要がある。
また,言語障害教育や情緒障害教育の専門性を確保するための養成・免許制度の在り方についても検討する必要がある。
(5) 盲・聾・養護学校の養護教諭の資質の向上
小・中学校等においても,ヘルスカウンセリング能力等,養護教諭の資質向上の問題が教育職員養成審議会等で取り上げられているが,盲・聾・養護学校では,心身の健康管理等に特別の配慮を必要とする幼児児童生徒が多く,特に最近は,障害の重度・重複化が一層進んでいることから,このような状況に応じた養護教諭の資質向上策を講じる必要がある。
(6) 管理職の専門性の向上
盲・聾・養護学校や特殊学級を設置する小・中学校の校長・教頭には,管理職としての資質とともに,特殊教育についての知識や経験を有し,その教育の充実のために適切な指針や助言を与える指導力が求められる。
このため,特殊教育教諭免許状の保有者等の経験者の配置に配慮するとともに,特殊教育の経験のない新任管理職を対象とした研修の充実を図る必要がある。
2 特殊教育担当教員の養成・免許制度の改善
(1)養成・免許制度の改善内容
特殊教育担当教員の養成制度の改善項目については,前述のとおり本協力者会議から今年6月に教育職員養成審議会に提言を行い,教養審第一次答申において,その多くが反映されたところである。今回の教養審第一次答申の提言内容と,それを受けて今後取り組むべき課題等について整理すると,次のとおりである。
(1) 盲・聾・養護学校の教諭免許状の複数取得を容易にするための改善
近年,盲・聾・養護学校においては,複数の障害を併せ有する幼児児童生徒が増加してきており,複数の障害に対応した専門性と実践的指導力を備えた教員の養成・確保が緊急の課題となっている。
このため,異なる学校種の教諭免許状の複数取得を容易にする観点から,教養審第一次答申では, 「(教育職員免許法)施行規則第7条表のうち第一欄については盲・聾・養護学校教諭の免許状取得に当たり共通に認められる科目とする」と提言された。
今後,この提言に沿った制度改正を図るとともに,大学等が採用側等の要請を踏まえて,科目内容の改善や学部の教育と連動した修士課程での養成カリキュラムの改善を図ることを望みたい。また,盲・聾・養護学校の教諭免許状の複数取得や,上級免許状の取得が促進されるように,大学における特殊教育内地留学生の積極的な受け入れや,大学や都道府県等による認定講習の一層の拡充が望まれる。
(2) 盲・聾・養護学校において知的障害者及び知的障害を併せ有する者を教育する場合の基礎免許状における制限の緩和
知的障害者及び知的障害を併せ有する者の教育については,学習指導要領上,児童生徒の実態に即した教育課程が編成できるよう各種の特例が定められているとともに,実際の授業でも,各教科・領域を合わせた指導などの総合的な学習の形態がとられていることが多い。しかし,現行の教育職員免許法では,盲・聾・養護学校の教員は,中学部・高等部に対応する中学校・高等学校の「基礎免許状」を有する者でなければならないとされているため,例えば,高等学校の基礎免許状を取得するために大学で履修した高等学校の各教科の目標・内容と,生徒の実態に応じた指導内容の差異が極めて大きいものとなっている。
こうした状況を踏まえて,教養審第一次答申では,「知的障害や知的障害を併せ有する重複障害に係る国語,社会,数学等いわゆる一般教科の扱いについては,基礎免許状による担当部・担当教科の制限を撤廃する」こととされた。
また,「養護訓練を含む特殊教科については,いわゆる基礎免許状の制約がない」ことの位置づけを明確にすることが提言された。
この制度改正は,知的障害や重複障害のある児童生徒の教育に専門性を もった教員を弾力的に配置することを可能にする画期的なものであるので,各学校の実態を踏まえて,より適切な教育が行われるようこの制度の活用が望まれる。
(3) 特別非常勤講師制度・特別免許状制度の活用
近年の社会情勢や雇用環境の変化,生徒の実態の多様化等に鑑み,盲・聾・養護学校での職業教育の重要性が増してきている。このような状況を踏まえ,高度な知識・技術あるいは豊かな経験等のある社会人を活用することにより,生徒の職業能力の向上を図ることの必要性が高まっている。
また,盲・聾・養護学校においては,児童生徒の障害の状態に応じ,様々な教育の場面において,専門の医師や専門家などによる適切な指導を行ったり,成人障害者及び卒業生から,その社会的自立の体験を学ぶ機会を増やすなど,特別非常勤講師制度や特別免許状制度を広く活用することが望まれる。
このため,教養審第一次答申では,社会人を活用する観点から,現在,盲・聾・養護学校において,理療,養護・訓練等の特殊の教科について認められていない特別非常勤講師制度を「全教科に拡大する」とともに,一部の教科について適用がなかった特別免許状制度についても,同様に「全教科に拡大する」ことが提言された。
今後,この提言の趣旨に沿った制度改正がなされた際には,職業教育や養護・訓練等様々な教科等で,社会人や医療・福祉等の専門家を積極的に活用して,学校全体の指導力を強化していくことが望まれる。
(4) 職業に関する教科の位置づけ
障害のある生徒の社会的・職業的自立を図ることは極めて重要な課題であるが,この中にあって,現在国家資格を取得することができる職業学科は大きな役割を果たしている。
このため,国家資格を取得できる新たな職域の開拓や盲・聾・養護学校高等部における職業教育のための資格を有する教員の適正な配置が必要である。
しかし,例えば,盲学校の高等部専攻科における「理学療法科」は,理学療法士養成施設(理学療法士及び作業療法士法第ll条第1号)として指定を受ける必要があるが,理学療法士の資格と高等学校の教諭免許状の両方を有する者は極めて少数であり,その教員の確保が大きな課題となっている。
こうした状況に対応するため,教育職員免許法施行規則第63条第4項に,「理学療法」等の特殊教科を新たに設けることで,理学療法士の資格を持った者が,その専門性に対応した教諭免許状を比較的容易に取得できるようにする必要がある。
(2)今後さらに検討すべき課題
(1) 総合免許状の検討
現行の特殊教育に係る免許制度は,視覚障害に対応した盲学校教諭免許状,聴覚障害に対応した聾学校教諭免許状,知的障害,肢体不自由,病弱という3種類の障害に対応した養護学校教諭免許状の学校種ごとの免許状になっている。しかし,特に近年,幼児児童生徒の障害の重度・重複化,多様化が急速に進んでいることから,各障害種別に対応した専門性を確保しつつ,多様な障害へ対応することが可能となる総合的な専門性が求められている。
この点については,既に昭和62年の教育職員養成審議会答申でこの学校種ごとに定められている免許を「総合免許状」として一本化することが今後の検討課題とされたところである。
この総合免許状の在り方を検討するに当たっては,免許基準(科目,単位数等)をどう定めるか,大学の学部及び修士課程での養成をどうするか,特殊学級担当教員にまで保有を求めるか等の検討すべき様々な課題があり,これらを含め,今後,関係団体・機関等において,検討を進める必要がある。
(2) 特殊学級,通級による指導の専門性確保のための養成・免許制度の対応
特殊学級及び通級による指導の担当教員の専門性の確保は重要な課題であるが,特に,現行の学校種ごとの教諭免許状の区分と完全には対応していない言語障害,情緒障害の指導の専門性の確保については,これまで主として研修制度によって対応してきており,養成・免許制度の側面からの検討は必ずしも十分なされてこなかった。
このため,前述の総合免許状の制度化の検討との関連を図りつつ,軽度の障害のある児童生徒に対する指導の専門性の在り方について,さらに検討する必要があると考える。
3 特殊教育担当教員等の専門性確保のための採用・研修・配置の改善
(1)特殊教育担当教員の採用・研修・配置の改善方策
特殊教育担当教員は,基礎免許状に加えて特殊教育教諭免許状を有することが原則とされているが,人事交流の要請や教科教育の必要性から基礎免許状のみをもつ者もかなり見られる状況にあること,他方,盲・聾・養護学校における専門的力量を高めていくためには,基礎的な専門性の裏付けとなる特殊教育教諭免許状の保有率を向上させる必要があることは,1の(1)で述べたとおりである。
このような認識の下に,養成課程で特殊教育を修めた者の専門性を評価した教員採用,現職研修による特殊教育教諭免許状取得の促進,人事配置等の配慮や管理職の専門性の向上等,採用,研修,配置等を通じ,以下のような対策を講じていく必要があると考える。
(1) 採用における対策
採用に関しては,養成課程で特殊教育について専門的に修め,特殊教育担当教員としての基本的な資質を有している者を採用していくことに意を用いていく必要がある。
現在,特殊教育担当教員の採用に関し,全国の6割を越える都道府県においては,小・中学校等の教員とは別枠で試験等を行っている。
しかしながら,このような場合であっても,受験資格上特殊教育教諭免許状の保有を要件にしなかったり,試験内容も小・中学校等の教員採用試験と同内容としていたりするなど,必ずしも養成課程で修めた専門性が適切に評価される仕組みとはなっていないところもある。
特殊教育について,養成課程で専門的に修めた者の資質が的確に評価される仕組みを整えた別枠試験等を行うことが,専門性を有する特殊教育担当教員を確保する有効な方策となると考える。
(2) 研修における対策
研修に関しては,学校種に対応した特殊教育教諭免許状をもたない教員であっても,採用後一定期間(例えば5年間)内に,できるだけ当該免許状を取得できるようにしていくことが望ましい。
特殊教育教諭免許状の保有率の高い県では,きめ細かく認定講習を開催し,早ければ3年程度で免許状が取得できるが,他方,都道府県主催の特殊教育に関する認定講習を年間3講座以下しか開催していない県が半数以上を占め,免許状取得に10年程度かかるところもあるなど,都道府県によりその対応には大きな差異がある。
このため,各都道府県では,一定期間内に必要単位数を取れるだけの認定講習の開催に努めるとともに,都道府県単位では,開催に必要な希望者数が集まりにくかったり,講師の確保が難しいような講座については,国立特殊教育総合研究所の短期研修を活用したり,ブロック単位で複数県が持ち回りで研修機会を確保する等の方策を立てることも有効である。
さらに,将来的には,放送大学等の通信教育やマルチメディアを活用すること等により講習の機会を確保する方策も検討するべきと考える。
(3)人事異動上の配慮
人事異動については,特殊教育に意欲があり,優れた実践的な指導力をもつ教員を,他の障害種別の学校や通常の学校から人事交流することは,多様な知識や経験の交換と組織の活性化にとって望ましいことであるが,特殊教育の指導分野のリーダーの確保や,教員が実践的な指導力をつけるためには,それぞれの教員の意欲,適性を勘案しながら,人事異動のサイクルの弾力的な取扱いについても考慮していく必要がある。
盲・聾・養護学校と特殊学級及び通級による指導の担当教員の人事交流については,設置者が異なることから,各都道府県の人事方針によってはそうした交流が行われていないところもある。しかしながら,特殊学級及び通級による指導の担当教員の資質の向上及び盲・聾・養護学校の活性化を図るためにも,各都道府県において,相互の適切な人事交流を推進していくことが望まれる。
(4) 管理職の配置
盲・聾・養護学校の管理職の人事については,円滑な学校運営と教育活動を図るため,管理職としての力量はもとより,特殊教育についての専門性をもった者を配置することが望まれる。このため,教頭の資格に原則としてそれぞれの学校の教諭免許状の保有を求めている学校教育法施行規則第10条の趣旨に則り,教頭には特殊教育教諭免許状を有する者を充てるようにしていく必要がある。また,このような人材を求められない場合でも校長を含む管理職の人事配置に当たり,できる限り特殊教育に関する知識と経験を有する者を配置するような配慮が望まれる。
(2)障害の重度・重複化に対応した養護教諭の配置
盲・聾・養護学校の幼児児童生徒については,きめ細かな健康管理や保健指導が特に必要とされるが,近年の障害の重度・重複化の傾向の中でその必要性はますます高まっている。特に,病弱養護学校や肢体不自由養護学校等,医療と密接に関連していたり,障害の重い幼児児童生徒の健康管理に関して特段の医学的知識や救急措置等の専門技術的対応が求められることが多い場合にあっては,看護婦免許を有する養護教諭を配置することや,その研修の在り方について検討する必要がある。
4 現職研修の改善
特殊教育担当教員の現職研修については,3で述べたように認定講習の量的整備を図るとともに,幼児児童生徒の障害種別に配慮した教科指導や養護・訓練等の指導力の向上を図る研修の質的整備が望まれるが,さらに1の(3)で述べた特殊教育担当教員の資質向上の課題に対応した現職研修の今後の改善方策について述べると,次のとおりである。
(1)障害の重度・重複化への対応
ア 重度・重複障害の幼児児童生徒の増加に対応するため,ほとんどの都道府県で訪問教育担当教員の研修を実施するとともに,全国の約3分の1の都道府県が複数の障害に関する研修の受講を奨励し,約3分の2の都道府県では「重複障害児の指導」を内容とする研修を開設している。
イ 今後とも重度・重複障害に関する研修の充実が望まれるが,その内容としては,(1)個別の指導計画,(2)実態把握の方法,(3)指導技術,(4)障害に対応した配慮事項を重視する必要がある。
ウ ー部の都道府県で医療・福祉施設における救急対処法や介助法等についての実地研修を,教職員に対して行っているが,今後とも,障害の重度・重複化に対応するためには,このような研修の充実が望まれるところである。
(2)幼稚部教育及び早期からの教育相談機能の充実への対応
ア 適正な就学指導を行うための就学指導担当者の研修は,全国の約3分の2の都道府県が実施するとともに,幼稚部教諭の研修は11県が,医療・福祉関係者との合同研修・研究会は8県が実施している。他方,早期からの教育相談担当者の研修については4県の実施に止まっている。
イ 特に,早期からの教育相談機能の充実を図るため,その担当職員の専門性を向上させる研修の充実が求められるが,その他,幼稚部から就学指導につながる担当者の専門性を確保するとともに,障害のある乳幼児の医療福祉を担当する医療・福祉機関との間で,障害のある者の立場に留意した早期相談や就学指導が行われるよう,これらの担当者の研修の充実が必要である。
(3)雇用環境に対応する職業教育の充実の必要性
ア 雇用環境に対応した職業教育や進路指導担当者の研修については,全国の都道府県のうち15県で職業教育の研修を実施し,13県で生徒の就職先の企業,医療・福祉施設での実地研修を実施し,18県で高等学校の進路指導担当者向けの研修や労働機関の研修への参加を奨励している。
イ 今後とも,職場に円滑に適応するための職業人としての基礎や新たな職域に対応した能力を生徒に身に付けさせる実践的な指導力を高める研修の充実や,教員の長期社会体験研修制度の活用を図るとともに,専門高校の教員を対象とする研修や労働関係機関の研修等,関連する外部の研修への参加を積極的に奨励する必要がある。また,生徒の現場実習実施事業所や医療・福祉施設における実地研修等を通じて,生徒の実態に合った職務内容の分析や,職場がどのような能力を求めているかを知る機会を充実することが望まれる。
なお,公共職業安定所との連携を図りつつ新たな職域の開拓を進めるとともに,地域の障害者職業センター等と協力して生徒の障害の実態等に沿った職務内容の分析等の研究を進めることも重要である。
ウ また,2で述べたように,特別非常勤講師制度や特別免許状制度による社会人の活用が望まれるが,これらの人々の中で,必ずしも十分に特殊教育の知識,経験を有していない者には,特殊教育の基礎知識を身に付けさせる研修の受講を奨励することが望ましい。
(4)特殊学級及び通級による指導の担当教員の専門性の確保
ア 特殊学級及び通級による指導の担当教員に対しては,ほとんどの都道府県で特殊教育センター等における都道府県主催の研修が実施されているか,全国の都道府県のうち20県では,市町村等の地域単位の授業を中心とした指導法・教材開発等の研究会を実施し,10数県では特殊学級と盲・聾・養護学校の間で連携して児童生徒の指導法等に関する共同研究会を開催するとともに研修・人事交流等の面で様々な連携を図っている。
イ 今後とも,特殊学級及び通級による指導の担当教員の専門性向上のための研修の充実に努めるとともに,盲・聾・養護学校が周囲の特殊学級等に対して,教員の専門知識や教材の提供,合同研修の場の提供等,地域の特殊教育のセンター的な機能を果たしていくことが望まれる。
(5)校内研修・通常の学級との合同研修の推進
ア 盲・聾・養護学校及び特殊学級担当教員等の専門性を高めていくためには,各学校における校内研修の恒常化が重要である。既に,児童生徒の実態把握,児童生徒理解,各教科等の指導法,交流教育の効果的な実施等についての研修が進められているが,児童生徒の障害の重度・重複化,多様化等の変化,個に応じた指導の一層の充実,国際化・情報化等の新たな課題への対応など,教員として求められる資質の内容の変化に対応した研修の充実を図る必要がある。
イ 特殊学級及び通級による指導の担当教員の資質の向上を図るためには,通常の学級を担当する教員と共同の校内研修に積極的に参加し,児童生徒理解,授業研究,各教科の指導法,障害のある児童生徒に対する理解啓発などを進めるとともに,特に,個に応じた指導の充実について研修を深めることが重要である。
また,このことにより,通常の学級を担当する教員の交流教育に対する理解や,特殊学級及び通級による指導に対する学校全体の支援体制が確立されることが望ましい。
(6)管理職の専門性の確保
ア 特殊教育について未経験で管理職に就く者を対象とした研修は,国立特殊教育総合研究所における「新任特殊教育諸学校等校長・教頭講習会」の実施や,文部省と国立教育会館の共催の「全国特殊学級設置学校長等研修」の実施により,大きな成果を上げてきている。また,全国の約半数の都道府県で新任管理職向けの研修を実施している。
イ 今後とも,これらの新任管理職向けの研修の充実を図る必要があるが,各都道府県においては,特に,全小・中学校数の約半数にも上る特殊学級設置校については,新任の管理職に対する研修や研究会の機会を提供することが必要である。
ウ また,盲・聾・養護学校の校長・教頭が市町村の校長会へ参加することや,地域の小・中学校の管理職との合同研修を開催することを奨励するなど,相互の連携・協力による研修の機会の充実を図ることも望まれる。
(7)情報化の進展に対する対応
ア 近年の急速な情報化の中で,情報機器や通信ネットワークの教育への活用が求められている。教養審第一次答申においても,「情報機器の操作」がすべての教員の養成課程において必修化されることとなった。特に,特殊教育については,障害に基づく種々の困難の克服,各教科等の学習の補完,情報活用能力の育成において,情報機器の活用は大きな可能性を有している。
イ したがって,現職研修においても,特殊教育担当教員の情報機器活用能力を向上させることは重要なことと考える。現在,国立特殊教育総合研究所において教育工学関連の研修が行われているほか,全国の8割強の都道府県において情報関連の研修が行われているが,今後ともこのような研修の一層の充実を図る必要がある。
なお,教員の指導力の向上を支援するため,国立特殊教育総合研究所において実施されている教育ソフトウェアの開発や研究成果の普及,特殊教育に関する実践的研究,現職研修,教育相談等に関する情報の収集と提供等の条件整備を,今後とも推進していく必要がある。
また,都道府県の特殊教育センターにおいても,情報通信機器の充実を図るとともに,特殊学級等の個々の担任の指導法の悩みに対してインターネット.ファクシミリ等を利用した相談や情報提供を行う等,情報機器を活用した教員に対する支援機能の充実が図られることが望まれる。
さらに,将来的には認定講習や各種講習会の研修の手段として,衛星通信,情報ネットワーク,マルチメディア等の活用を図ることを検討する必要がある。
5 小・中学校等の教員の特殊教育に関する学習・研修の充実
(1)小・中学校等の教員が特殊教育について学習・研修することの意義
盲・聾・養護学校等では,在学している幼児児童生徒の障害の状態,発達段階,特性等が一人一人異なつていることから,きめ細かな実態把握に基づき,綿密な指導計画を作成し,個別指導を積極的に取り入れた教育を行っている。このような個に応じた指導は,教育の基本ともいうべきものであり,小・中学校等の教育においても,今後,特に重視されなければならない。
また,小・中学校等の通常の学級と盲・聾・養護学校や特殊学級との交流は,すべての幼児児童生徒にとって大切であり,今後積極的に進めていかなければならない。このため,小・中学校等に配置されている養護教諭を含むすべての教員が,特殊教育について幅広く学習・研修することが求められている。
(2)小・中学校等の教員の養成課程における特殊教育に関する学習
(1)で述べたとおり,教員を目指す者すべてが特殊教育に関して学習し盲・聾・養護学校の教育現場を体験する必要がある。
このような考え方に立って,教養審第一次答申においては,特殊教育に係る内容をすべての小・中学校等の教員の養成課程において必修とするとともに,盲・聾・養護学校において教育実習の一部を実施することの意義が示されているところである。
また,去る6月には「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が成立し,教員を志す者は,盲・聾・養護学校や社会福祉施設で一週間程度の介護・交流等の体験が義務づけられることになった。この制度は平成10年度から施行されるが,介護・交流等の体験のうち一定期間は,盲・聾・養護学校において特殊教育に関した体験をすることが望ましく,盲・聾・養護学校においては,積極的にこのような実習や介護・交流等の体験を行おうとする者を受け入れていく必要がある。
教育職員養成審議会では,今後養護教諭の養成課程の在り方について検討する予定であるが,養護教諭についても同様に,特殊教育に係る内容が養成課程に盛り込まれることが望ましい。
(3)小・中学校等の教員の特殊教育に関する研修の受講奨励
障害がある幼児児童生徒や特殊教育に関する正しい理解が得られるように,既に全国の約7割の都道府県において,小・中学校等の教員が,特殊教育担当教員向けの研修に参加できるようにしており,9県においては通常の学級を担当する教員向けに特殊教育の関連講座を開設している。
今後とも,より多くの都道府県で,このような研修を充実することが望まれる。
III 今後の課題
以上特殊教育に関する教育課程の改善と特殊教育担当教員の資質の向上について提言したが,その他,特殊教育制度全般を通じて,今後の課題となると考えられることについて,3点述べることとしたい。
1 学習障害児への対応
ア 学習障害(LD)のある児童生徒の指導については,平成7年3月に「学習障害及びこれに類似する学習上の困難を有する児童生徒の指導方法に関する調査研究協力者会議」が中間報告をまとめ,学習障害の定義や基本的な指導の在り方等を発表した。その後も,理解啓発リーフレットや通常の学級における指導用冊子を配布したり,国立特殊教育総合研究所で学習障害児等指導者講習会を開催している。
イ 現在のところ,その明確な障害像や診断方法,望ましい指導方法等について,必ずしも十分明らかになってはおらず,なお研究すべき課題が多い。今後とも,これらの研究を推進しつつ,より多くの小・中学校等の教員に対し,理解・啓発を図る努力を続けるとともに,適切な授業の形態や教育の場の在り方について,引き続き検討する必要がある。
2 完全学校週5日制施行に向けた家庭や地域社会との連携
ア 障害のある幼児児童生徒の生きる力をはぐくみ,社会の一員として主体的に活動できるように育てていくためには,学校,家庭及び地域社会が一体となった取組が重要であり,このことは,将来,完全学校週5日制を実施する上でも極めて重要なことと考える。
イ 完全学校5日制については,その円滑な施行に向けて,学校と家庭や地域社会との連携・協力の在り方を引き続き検討する必要がある。特に,盲・聾・養護学校の幼児児童生徒は,ともすれば地域の同年齢の幼児児童生徒とのつながりが希薄になりがちであることから,特に十分な配慮と対応が必要と考える。
このことから,現在でも土曜日や休日におけるスポーツ,文化活動のためのスクールバスや指導員の確保等が地方交付税により行われるとともに,ウィークエンド・サークル活動推進事業や学校開放事業等による社会教育,学校教育等の対応が行われているが,今後,その一層の充実が求められる。
また,重度・重複障害の幼児児童生徒の休日における対応については,医療・福祉等の関係機関との連携が特に必要である。
3 労働,医療,福祉関係機関との連携の強化
ア 障害のある子供たちの社会的自立を図っていくためには,労働・医療・福祉・教育関係機関の相互の連携が必要である。
例えば,就学前においては,教育,医療及び福祉の各分野で行われている早期相談の担当者相互の連携を図ることが考えられる。
学校教育の各段階においては,障害が極めて重度な重複障害児に対する医療的ケアを含む適切な療育の在り方についての検討や,在学する幼児児童生徒の二一ズに応じた福祉サービスに関する情報の提供のために,医療,福祉関係機関との連携を図ることが考えられる。
卒業期においては,生徒の社会的自立を図るために,企業等が求めている基礎的な職業的能力や,新たな職業能力を育成するための職業教育の改善と進路指導の充実,卒業後円滑に社会生活を営むことができるようにするための追指導の充実等に関して,労働・福祉関係機関との連携を図ることが考えられる。
さらに,卒業後の生活をより豊かなものにする生涯にわたる学習機会の提供等のために,各種機関との連携を図ることも考えられる。
このようにいろいろな段階で,他の様々な分野との連携を図り,障害のある者の立場に立った総合的なサービスを提供できるようにしていくことが重要である。
今後,このような観点から,国,地方の各段階において,教育と労働,医療,福祉等の関係機関が,それぞれ有している施策と資源を提供し合い,十分な連絡・連携を図っていく必要がある。
イ このため,今後,国においても,関係省庁の連携の下に特殊教育と福祉・医療の望ましい連携・協力に関する実践的研究を行ったり,時代の変化に対応して新たな職域開拓に向けた職業教育の在り方の調査・研究などに積極的に取り組んでいくことが必要であると考える。
児童生徒数等の推移
(1)特殊教育の対象となる児童生徒数(義務教育段階)の推移
| 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | |
| 盲・聾・養護学校 | 54,684 | 53,063 | 51,761 | 50,491 | 50,093 | 49,544 | 49,138 |
| 特殊学級 | 77,162 | 74,267 | 71,895 | 69,250 | 66,951 | 66,039 | 66,162 |
| 通級による指導 | - | - | - | 12,259 | 14,069 | 16,700 | 20,006 |
| 計 | 131,846 | 127,330 | 123,656 | 132,000 | 131,113 | 132,283 | 135,306 |
(2)義務教育段階の就学率の推移

(3)小・中学部における重複障害学級在籍率の推移

(4)盲・聾養護学校の幼稚部及び高等部の設置状況(平成8年5月1日現在)
| 全学校数 | 幼 稚 部 | 高 等 部 | ||||
| 設置校数 | 設置率(%) | 設置校数 | 設置率(%) | |||
| 盲 学 校 | 71 | 47 | 66.2 | 61 | 85.9 | |
| 聾 学 校 | 107 | 100 | 93.5 | 70 | 65.4 | |
| 養護学校 | 知的障害 | 511 | 11 | 2.2 | 389 | 76.1 |
| 肢体不自由 | 191 | 13 | 6.8 | 141 | 73.8 | |
| 病 弱 | 95 | 1 | 1.1 | 40 | 42.1 | |
| 計 | 797 | 25 | 3.1 | 570 | 71.5 | |
| 計 | 975 | 172 | 17.6 | 701 | 71.9 | |
(5)養護学校高等部設置率の推移

(6)盲・聾・養護学校中学部及び中学校特殊学級卒業者の高等部への進学率の推移

(7)盲・聾・養護学校高等部(本科)卒業者の就職率の推移

(8)盲・聾・養護学校及び特殊学級担当教員数の推移 (国・公・私立計 本務教員のみ)

(9)盲・聾・養護学校及び特殊学級の免許保有率全国平均推移 (国・公・私立計 本務教員のみ)

「特殊教育に関する免許及び研修制度に関する調査」集計結果
1 調 査 日 : 平成9年7月
2 調査対象 : 47都道府県
3 調査内容 : 各都道府県における特殊教育諸学校の免許取得や現職研修の実態を把握するためのもの。
4 集計結果 : (1つの設問に複数回答,数字は都道府県数,%は全都道府県に対する割合)
○特殊教育諸学校の教員免許取得率について
設問 特殊教育諸学校の免許保有率向上のため取っている措置 A1 別枠試験,別枠採用を行っている 29(62%) A2 認定講習会の受講を奨励 37(79%) A3 人事異動サイクルを通常より延長 10(21%) A4 特殊教育諸学校の校長,教頭は原則免許保有者 3( 6%) としている
(参考) 都道府県の認定講習会開催数
| 0講座 | 1~3講座 | 4~6講座 | 7~9講座 | 10講座以上 | |
| 都道府県数 | 4( 9%) | 21(45%) | 15(32%) | 4( 9%) | 3( 6%) |
○特殊教育諸学校,特殊学級,通級指導担当教諭等の研修の現状
設問1 障害の重度・重複化に関する研修の実施状況 既に実施 実施検討 A1 複数の障害の研修受講を奨励 16(34%) - A2 「重複障害の指導」研修 31(66%) 2( 4%) A3 訪問教育担当教員の研修 46(98%) - A4 他の障害種別の学校で実地研修 7(15%) 1( 2%) A5 医療・福祉施設で救急対処,介護方法実地研修 2( 4%) 5(11%) 設問2 幼稚部・早期教育に関する研修の実施状況 既に実施 実施検討 A1 幼稚部教諭の研修 11(23%) 1( 2%) A2 早期教育相談(0~3歳)担当者の研修 4( 9%) 4( 9%) A3 就学指導担当者の研修 32(68%) 1( 2%) A4 医療福祉関係者との合同研修・研究会 8(17%) 7( 15%) 設問3 職業教育・進路指導に関する研修の実施状況 既に実施 実施検討 A1 職業教育の研修 15(32%) 3( 6%) A2 専門高校教員向け研修の受講奨励 3( 6%) - A3 就職先の企業,福祉・医療施設で実地研修 13(28%) 3( 6%) A4 高校の進路指導担当者向け研修や労働機関の研修への参加奨励 18(38%) 2( 4%) 設問4 特殊学級・通級指導担当教員に関する研修の実施状況 既に実施 実施検討 A1 特殊学級・通級指導担当教員の研修 46(98%) - A2 地域ごとの研究会,合同授業の実施 20(43%) 1( 2%) A3 盲・聾・養護学校との共同研究会,教材提供,合同授業の実施等の連携強化 14(30%) 3( 6%) A4 盲・聾・養護学校との相互交換研修,人事交流 10(21%) 2( 4%) A5 通常の学級の教員との共同研究,研修会 7(15%) 2( 4%) 設問5 特殊教育諸学校,特殊学級設置校の管理職に関する研修の実施状況 既に実施 実施検討 A1 新任管理職向けの研修 22(47%) 4( 9%) A2 特殊学級設置校の管理職と盲・聾・養護学校の管理職の合同研究会の開催等連携強化 1( 2%) 3( 6%) 設問6 特殊教育諸学校,特殊学級設置校の管理職に関する研修の実施状況 既に実施 A1 情報機器・インターネットの活用方法の研修 39(83%) 設問7 小・中・高等学校等教員を対象とした特殊教育に関する研修の実施状況 既に実施 A1 特殊教育担当教員向け研修への参加を認める 33(70%) A2 通常の学級担当教員向けの特殊教育関連講座の開催 9(19%) 設問8 学習障害児等の指導に関する研修の実施状況 既に実施 A1 学習障害児等の指導に関する研修 32(68%)
○近年の障害者関係施策の動向
(1)国際的動向
| 昭和58年~平成4年 |
国連・障害者の十年
○国際障害者年(昭和56年)終了後も障害者問題に積極的に取リ組むため,障害者の「完全参加と平等」を目標テーマに設定 |
| 平成5年~平成14年 |
アジア太平洋障害者の十年
○国連・障害者の十年の後を受け,アジア太平洋地域における更なる障害者施策の進展を期して設定 |
(2)国内動向
| 平成5年12月 |
障害者基本法の成立
障害者の自立と社会参加の一層の推進を図ることを基本理念として「心身障害者対策基本法」を改正。教育については次のとおリ規定 ○障害の状態等に応じた教育内容・方法の改善充実 ○障害者の教育に関する調査研究,環境整備の促進等 |
| 平成5年3月 |
障害者対策に関する新長期計画の策定
「障害者基本法」に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(平成5~14年度)を策定。特殊教育については次のとおリ ○早期教育相談体制の整備,幼稚部の拡充整備,○通級による指導の整備充実, ○交流教育の推進,○学習障害児等についての研究の推進, ○高等部の整備充実,職業教育・進路指導の充実等 |
| 平成7年12月 |
障害者プランの策定
「障害者対策に関する新長期計画」の具体化を図るための重点施策実施計画。特殊教育については次のとおリ ○高等部の整備,職業教育・進路指導の充実,○教育相談体制・教員研修の充実, ○交流教育の充実等 |
| 平成8年5月 |
障害者の雇用・就業に関する行政監察
障害者に対する雇用・就業対策の実施状況及び特殊教育諸学校における職業教育の実施状況についての行政監察。特殊教育に関する勧告内容は次のとおリ ○盲学校及び知的障害養護学校の職業教育の改善,○進路指導体制の整備 |
| 平成9年4月 |
障害者雇用促進法の改
○法定雇用率の算定基礎に知的障害者を算入等 |
(3)特殊教育に関する施策等
| 平成5年4月 |
通級による指導の制度化
○軽度障害児の教育の充実 |
| 平成7年3月 |
学習障害児等の教育に関する中間まとめ
○学習障害児について基本的な考え方,配慮事項等 |
| 平成8年3月 |
高等部の職業教育の在り方等関する報告
○職業に関する学科・教科の改善,現場実習の充実等 |
| 平成8年7月 |
中央教育審議会第一次答申
○「生きる力」をはぐくみ,可能な限リ社会参加・自立を実現する観点から,指導内容・方法等の改善・充実 ○早期教育相談体制の充実,幼稚部の整備 ○高等部の職業教育の改善・充実,進路指導体制の強化 ○高等部における訪問教育の実施 ○盲・聾・養護学校と小・中学校等との交流教育の推進 ○学習障害児に対する指導内容・方法等の研究の促進等 |
| 平成9年1月 |
特殊教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議一次報告
○高等部の拡充整備と訪問教育の実施,○交流教育の充実, ○早期からの教育相談の充実,幼稚部の整備 |
参 考 資 料
1 検討結果
| 年 月 | 協力者会議 | ワーキンググループ |
| 平成8年9月 | 第1回(25日) | |
| 10月 | 第2回(22日) | 事前打合せ(22日) |
| 11月 |
第1回(19日)
第2回(26日) |
|
| 12月 | 第3回(19日) |
第3回( 6日)
第4回(25日) |
| 平成9年1月 |
第4回(17日)
第5回(24日) (第一次報告公表) |
第5回( 9日) |
| 2月 | 第6回(19日) |
第6回( 6日)
第7回(21日) |
| 3月 | 第7回(18日) |
第8回( 6日)
第9回(21日) |
| 4月 | 第8回(25日) |
第10回( 2日)
第11回(15日) 第12回(18日) |
| 5月 | 第9回(29日) |
第13回(12日)
第14回(20日) |
| 6月 | 第10回(30日) |
第15回( 6日)
第16回(16日) |
| 7月 | 第17回(18日) | |
| 8月 | 第11回(29日) |
第18回(11日)
第19回(18日) |
| 9月 |
第12回( 9日)
第13回(19日) (第二次報告公表) |
特殊教育の改善・充実に関する調査研究について
平成8年9月12日
初等中等教育局長裁定
1 趣旨
中央教育審議会の答申等を踏まえ,特殊教育の改善・充実のための諸課題について,基礎的な調査研究を行う。
2 調査研究事項
(1)特殊教育の教育内容等の改善に係る基礎的事項について
(2)特殊教育の当面する諸課題について
(3)その他
3 実施方法
別紙の学識経験者等の協力を得て,調査研究を行う。
なお,必要に応じ,別紙以外の者の協力を得ることができる。
4 実施期間
平成8年9月12日から平成9年9月30日までとする。
6 庶務
この研究に関する庶務は初等中等教育局特殊教育課において処理する。
3 調査研究協力者名簿 (委嘱期間:平成8年9月12日~平成9年9月30日)
職名は平成9年9月1日現在
| 氏 名 | 職 名 | 備 考 |
| 番 谷 利 夫 | 国立特殊教育総合研究所長 |
副座長
ワーキンググループ委員兼任 |
| 上 野 轟 | 大阪教育大学教授 | ワーキンググループ委員兼任 |
| 大 南 英 明 | 東京都立青鳥養護学校長 | ワーキンググループ委員兼任 |
| 大 山 泰 弘 |
日本理化学工業(株)代表取締受社長
(重度障害者雇用事業所協会会長) |
|
| 小 関 洋 治 | 和歌山県教育委員会教育次長 | |
| 亀 井 浩 明 | 帝京大学教授 |
座 長
ワーキンググループ委員兼任 |
| 国 本 翠 |
神奈川県福祉部
障害福祉課主幹 |
|
| 小 出 進 | 千葉大学教授 | ワーキンググループ委員兼任 |
| 瀬 尾 政 雄 | 筑波大学教授 | ワーキンググループ委員兼任 |
| 橘 厚 子 |
東京都渋谷区立
神宮前小学校長 |
|
| 西 間 三 馨 | 国立療養所南福岡病院長 | |
| 野 原 明 |
文化女子大学教授
NHK解説委員 |
|
| 服 部 祥 子 | 大阪府立看護大学教授 | |
| 細 村 迫 夫 | 群馬大学教授 | ワーキンググループ主査兼任 |
| 三 浦 和 | 全国特殊教育推進連盟理事長 | |
| 宮 崎 昭 |
筑波大学附属
桐が丘養護学校教諭 |
ワーキンググループ委員兼任 |
| 百 井 悦 子 |
北海道立特殊教育センター
情緒障害教育室長 |
ワーキンググループ委員兼任 |
| 山 内 美 代 |
社会福祉法人
全日本手をつなぐ育成会理事 |
|
| 渡 邊 研 | 筑波技術短期大学名誉教授 | ワーキンググループ委員兼任 |
特殊教育の改善・充実について(第一次報告)
特殊教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議(座長 亀井浩明帝京大学教授)では,平成8年9月以来,今後の特殊教育の改善・充実に資するため,幅広い観点から検討を行っているが,この度,早急な対応が求められている下記の事項について第一次報告を取りまとめた。報告の要旨は以下の通り。
盲学校,聾学校及び養護学校の高等部の拡充整備と訪問教育の実施について
◎ 高等部の拡充整備
近年,養護学校を中心に高等部への進学希望者が増加するとともに,障害の重度・重複化が進行。
高等部の整備は相当進んできているが,なお,地域差等が見られ,今後,その計画的な整備と重複障害学級の設置促進が必要。
◎ 高等部における訪問教育の実施
通学が困難な生徒に対し中学部に引き続き高等部において訪問教育を行うことは,義務教育で培われた社会参加・自立に必要な知識や習慣の定着を図る上で大きな意義。
近年,高等部への進学率が向上し,各県等の高等部の整備も一定程度充足してきていることから,今後,高等部等の整備と併行し,その実施体制を整えることが適当。
〔試行的実施〕通学が困難な生徒の進学希望に一日も早くこたえ,本格的実施に向けた実施体制の整備に資するため,現行制度の枠内で,各県等が試行的に実施できるようにすることが適当。→平成9年度より実施。
今回の試行の成果を踏まえ,学習指導要領や訪問教育の関係規定の整備等が必要。
交流教育の充実について
交流教育は,児童生徒の豊かな人間性や社会性を育成する上でも大きな意義。
すべての児童生徒や教員の理解と認識を深めるため,多様で継続的な交流の展開が必要。
完全学校週5日制に向け,地域における交流の充実について工夫することが必要。
交流教育の意義を踏まえ,教育課程上の位置づけなどについても検討が必要
早期からの教育相談の充実について
乳幼児の障害などの状態の改善,保護者の不安の軽減等のため,早期からの教育相談が有効。
特殊教育センター等を中心とし,盲・聾・養護学校とのネットワークを形成し,早期教育相談の機能を高めることが重要。
教育相談を盲・聾・養護学校の新たな教育サービス機能として位置づけることが適当。
また,幼稚部の設置促進や充実方策について検討が必要。
教育分野と医療・福祉分野の特徴や機能等を生かし,相談活動が一体化して行われる方策についての検討が必要。
特殊教育の改善・充実について(第二次報告の概要)
特殊教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議(座長 亀井浩明 帝京大学教授)は,平成8年9月以来,今後の特殊教育の改善・充実方策を幅広く検討してきたが,教育課程審議会や教育職員養成審議会の審議の状況を踏まえ,この度,第二次報告を取りまとめた。
I 盲・聾・養護学校等の教育課程の改善
社会の変化に対応するとともに,障害のある児童生徒等が社会的に自立・参加する基盤となる[生きる力]を培う観点から,以下のような改善を提言。
◎障害の重度・重複化,多様化への対応
・障害の状態を改善・克服するための特別な指導である「養護・訓練」について,自立を目指した主体的な活動である趣旨を明確にするため,名称,内容等について検討する。
・個に応じた指導の一層の充実を図るため,「個別指導計画」の策定について検討する。
・高等部の訪問教育について,試行的実施の成果を踏まえ,学習指導要領に明確に規定する。
◎早期からの適切な教育的対応の充実
・早期からの教育的対応の有効性に鑑み,幼稚部の教育内容の充実を図るとともに,教育相談に関し,学習指導要領に規定する。
◎軽度の障害のある児童生徒への指導の充実
・特殊学級や通級による指導について小・中学校学習指導要領に規定し,その指導の充実と全校的な取り組みの推進を図る。
◎交流教育の充実
・盲・聾・養護学校と小・中学校の児童生徒等との交流教育について,小・中学校等の学習指導要領に明確に位置付け,一層の充実,推進を図る。
II 教員の資質向上
特殊教育担当教員の専門性の向上と適材の確保を図るため,新たに,以下のような改善方策を提言。
◎特殊教育担当教員の免許取得の促進
・特殊教育担当教員の専門性の裏付けである特殊教育教諭免許の取得を促進するため,認定講習会を積極的に拡充する。
・障害の重複化に対し,複数の障害に専門性を持った「総合免許状」の在り方を検討する。
◎適材確保のための採用・人事配置等の改善
・養成課程で特殊教育を修めた者を評価する別枠試験の採用,専門性を培う観点からの人事サイクルの配慮,管理職への特殊教育の専門家の配置等を積極的に進める。
◎今日的な諸課題に対応した現職研修の改善
・重複障害児指導,早期教育相談等の諸課題に対応した研修を充実する。
・研修の手段として,衛星放送,マルチメディア等の活用を検討する。
◎小・中学校教員等の特殊教育に関する養成課程における体験の充実
・「介護体験法」に基づく教員志望者の介護体験の場として,盲・聾・養護学校における積極的な受け入れ体制を整備する。
・小・中学校等教員の特殊教育に関する研修の参加を積極的に奨励する。
(平成9年10月21日付け文初特第422号初等中等教育局長通知 添付資料)
新たな時代に向けた教員養成の改善方策について(第一次答申)(抄)
平成9年7月28日
教育職員養成審議会
II 教員養成カリキュラムの改善
2 教職課程の教育内容の改善
(3)具体的改善方策
イ.教育実習の充実
◎ロ 現行制度でも,取得しようとする免許に対応する学校以外の学校においても教育実習を行うことができることとされており,そのようなことは,幼児・児童・生徒の発達の状況をより適切に理解する上で望ましいことであるにもかかわらず,実際の運用例は少ない。
また,教育実習の一部を盲・聾・養護学校や特殊学級において実施することについては,障害のある子どもたちに対する個に応じた指導を観察・体験することで,教職に関する理解と自覚を深めるとともに,教育者としての使命感や実践的指導力の基礎を一層高める観点から,大きな意義があるものと考える。
これらのことにかんがみ,施行規則第6条表備考第7号に規定された制度がより積極的に運用されるよう,条文の表現を工夫する必要がある。
エ.特殊教育に係る内容の必修化
◎ 障害のある子どもたちの心身の発達及び学習の過程に係る内容を,現行の「幼児,児童又は生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目」の中に含めるべきことを制度上明記し,すべての学校段階に属する教員の特殊教育に関する理解を深めることとする。
III カリキュラム以外の免許制度の弾力化
1.社会人の活用促進
学校教育の水準の維持・確保に留意しつつ,以下の弾力化措置を講ずるものとする。
(1)特別非常勤講師制度の改善
■ 小学校及び盲・聾・養護学校の特別非常勤講師制度に関し,対象を全教科(盲・聾・養護学校にあっては施行規則第62条~第65粂の2に規定する特殊教科を含む。)に拡大する。
(2)特別免許状制度の改善
■ 小学校及び盲・聾・養護学校の特別免許状制度について,特別非常勤講師制度の場合と同様,対象を全教科に拡大する(注)。
(注) 小学校の場合も,特別免許状の授与は各教科ごとに行われる。
■ 特別免許状の有効期間については,現行制度では「3年以上10年以内において都道府県の教育委員会規則で定める期間」(免許法第9条第2項)とされているが,これを緩和して「5年以上10年以内…」と改める。
■ 学校教育に社会の優れた人材をより積極的に迎え入れる観点から,特別免許状から普通免許状への上進制度を創設する。
2 盲・聾・養護学校に係る免許制度の弾力化
◎ 特殊教育教員の免許状の複数取得を容易にする観点から,施行規則第7条表(盲・聾・養護学校における「特殊教育に関する科目」)のうち,第1欄については盲・聾・養護学校教諭の免許状取得に当たり共通に認められる科目とする。
■□ 知的障害者及び知的障害を併せ有する重複障害者に係る国語,社会,数学等いわゆる一般教科の扱いについては,学習指導要領に基づく教科を合わせた指導等がより円滑に行われるよう,基礎免許状による担当部・担当教科の制約(免許法第3条第3項に係るもの)を撒廃することとする。
また,養護訓練を含む特殊教科についてはいわゆる基礎免許状の制約がないが,このことについて必ずしも十分な理解が得られていないことから,その位置付けを更に明確にする必要がある。
■ このほか,1.に掲げたように特殊教育に係る特別非常勤講師及び特別免許状の対象範囲の拡大を図る。
3 その他の弾力化措置
◎ その他の法令の規定の不備等により運用に支障が生じている点等について,適宜制度の明確化等を図る必要がある。