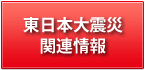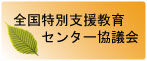ホーム > 図書室利用案内・データベース >
特別支援教育法令等データベース 総則 / 報告・答申等 - 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の医学的・法律学的整理に関する取りまとめ -
盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の医学的・法律学的整理に関する取りまとめ
(平成16年9月17日 在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会)
盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の 医学的・法律学的整理に関する取りまとめ 平成16年度厚生労働科学研究費補助事業 平成16年9月17日 在宅及び養護学校における日常的な医療 の医学的・法律学的整理に関する研究会
1 報告書の目的 ○ 「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する 研究」は、行政的課題となっている (1)ALS以外の在宅患者に対するたんの 吸引行為と、 (2)盲・聾・養護学校における医療のニーズの高い幼児、児童及 び生徒(以下「児童生徒等」という。)に対するたんの吸引、経管栄養及び導 尿(以下「たんの吸引等」という。)に焦点を当て、それらの医学的・法律学 的整理を行うことを目的としている。 ○ (2)の盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の問題については、すでに文部 科学省により平成10年度から平成14年度にかけて実施された「特殊教育に おける福祉・医療等との連携に関する実践研究」及び平成15年度から実施さ れている「養護学校における医療的ケアに関するモデル事業」(以下「モデル 事業等」という。)において実践的な研究がなされてきたところであるが、た んの吸引等の取扱いをどうするかの結論が求められている状況にあり、 (1)の 在宅患者に対するたんの吸引の問題に先んじて整理することとした。 ○ モデル事業等の現状及びそれに対する評価を踏まえ、盲・聾・養護学校にお ける医療のニーズの高い児童生徒等に対するたんの吸引等を教員が実施するこ とについて、医学的・法律学的な問題の整理を行い、結論をとりまとめた。 ○ この報告は、モデル事業等の成果を基に、盲・聾・養護学校におけるたんの 吸引等について、教員が行うことが許容される範囲・条件等について検討を行 ったものであり、たんの吸引等以外の行為や、盲・聾・養護学校以外での医行 為についての検討を行ったものではない。 ○ ALS以外の在宅患者に対するたんの吸引行為に関する医学的・法律学的整 理は、この報告の後、あらためて検討する。 2 盲・聾・養護学校における日常的な医療の提供を巡る現在の状況 (1)現行の法規制 ○ 医師法第17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と規定し ている。行政解釈上、「医業」とは、医師の医学的判断及び技術をもってする のでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行 為)を、反復継続する意思をもって行うことと解釈されている。 ○ また、保健師助産師看護師法上、看護師が行う医行為は診療の補助行為に位 置付けられるものと解釈されており 1 、その他の医療関係の資格を有する者が う医行為も、同様の位置付けを与えられている。 1 保健師助産師看護師法第31条第1項 看護師でない者は第5条に規定する業〔傷病者若しくはじよく婦に対する 療養上の世話又は診療の補助〕をしてはならない。 ○ したがって、医療関係の資格を保有しない者が医行為を業として行うことは 一般的に禁止されている。 (2)ALS分科会報告書を踏まえた行政的対応 ○ 在宅で療養しているALS患者のたんの吸引については、当該行為が患者の 身体に及ぼす危険性にかんがみ、原則として、医師又は看護職員が行うべきも のとされてきた。しかし、在宅のALS患者にとっては、頻繁にたんの吸引が 必要であることから、家族が24時間体制で介護を行っているなど、患者・家 族の負担が非常に大きくなっており、その負担の軽減を図ることが求められて いた。 ○ 平成15年6月、「看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科 会」は、報告書をとりまとめた。この報告書では、在宅で療養しているALS 患者に対するたんの吸引行為について、基本的には医師又は看護職員が行うこ とを原則としつつも、3年後に、見直しの要否について確認することを前提に、 医師の関与やたんの吸引を行う者に対する訓練、患者の同意など一定の要件を 満たしていれば、家族以外の者が実施することもやむを得ないものとされた。 なお、家族以外の者が実施するたんの吸引は、当面やむを得ない措置として実 施するものであって、ホームヘルパー業務として位置付けられるものではない とされている。その後、行政の実務においても、同旨の医政局長通知(平成15 年7月17日医政発第0717001号)が発出された。 ○ これは、ALS患者の在宅療養という限定された状況において、一定の厳格 な条件を満たしていれば、たんの吸引という医行為を家族以外の者が実施して も、医師法第17条との関係では違法性が阻却されるものとして取り扱ったも のである。 (3)モデル事業等の現状及び評価 ○ 近年の医学・医療技術の進歩やノーマライゼーションの理念の普及などを背 景に、盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の必要性が高い児童生徒等の割 合が増加しつつある。このため、盲・聾・養護学校において、障害のある子ど もの教育を受ける権利や、その前提として安全かつ適切な医療・看護を受ける 権利を保障する体制を整備する必要性が高まってきている。しかし、たんの吸 引等は現状では医師若しくは看護職員又は保護者が行うとされており、これら の児童生徒等が医療関係者の配置されていない盲・聾・養護学校に通学するた めには保護者の付き添いが必要となる。保護者の負担の軽減という観点からも、 盲・聾・養護学校における体制整備の必要性が指摘されている。 ○ このような事情から、文部科学省では、厚生労働省と各県教育委員会の協力 を得て、平成10年度からモデル事業等を実施し、盲・聾・養護学校における 医療のニーズの高い児童生徒等に対する教育・医療提供体制の在り方を探って きた。 ○ モデル事業等では、非医療関係者が医行為を実施する場合の危険性やこれら の行為が必要となる頻度を踏まえ、「咽頭より手前の吸引」、「咳や嘔吐、喘 鳴等の問題のない児童生徒で、留置されている管からの注入による経管栄養 (ただし、経管の先端位置の聴診器による判断は除く)」及び「自己導尿の補助」 の3つの行為に限定し、どのような医療体制の下で、どのような手続きを踏ん で、どこまでの行為を教員が行うことが適当か、また、看護師と教員の連携の 在り方、医療・福祉の関係機関と連携した望ましい医療体制の在り方等につい て研究を行った。 ○ 医療安全面については、医療事故の発生の報告はなく、看護師と教員の連携 の中で円滑にたんの吸引等が実施できた。また、医療安全面の体制の充実とい う観点では、 (1)県レベルでの実施体制の整備を図ったことにより地域の医療 機関からの協力が得られた、 (2)看護師が学校に常駐しているため、教員が児 童生徒等に対する医療上の配慮や健康状態について相談することや、たんの吸 引等に関する知識、手技についての研修を受けることが容易になり、教員が安 心してたんの吸引等に従事できた、 (3)健康管理、健康指導が充実するととも に、これに携わる教員の資質の向上、予見・注意義務の徹底による教員の危機 管理意識の高揚を図ることができた、 (4)緊急時の医療機関との連絡体制が整 備された、等の効果が観察された。 ○ 教育面では、医療が安全に提供されたことにより、授業の継続性の確保、訪 問教育から通学への移行、登校日数の増加、親から離れて教育を受けることに よる本人の自立性の向上、教育の基盤である児童生徒等と教員との信頼関係の 向上、健康管理の充実、生活リズムの確立等の効果が観察された。 ○ 保護者が安心して児童生徒を学校に通わせることができるようになり、また、 たんの吸引等が必要になったときに備えて学校待機をする必要がなくなるなど、 保護者の心理的・物理的負担の軽減効果も観察された。 ○ したがって、医療関係者の間の指示系統が不明確であるなどいくつかの課題 も指摘されているものの、モデル事業等の下では、関係者の協力により3つの 行為は概ね安全に行い得ることが実証され、教育上の成果が上がったと評価す ることができる。 3 盲・聾・養護学校における医療の実施の要件及び法律的整理 医療に必要な知識・技能を有していない者が医行為を行うことは本質的に危険 な行為であるため、医療に関する資格を有していない者が医行為を業として行う ことは法律により禁止されている。一方、医療のニーズが高い児童生徒等を受け 入れている盲・聾・養護学校においては、教育と医療が合わせて提供される必要 がある 2 。このため、盲・聾・養護学校に通う医療のニーズが高い児童生徒等の 数が増加する中で、これらの児童生徒等の教育を受ける権利を保障するためには、 看護師の適正な配置を進める必要がある。 3 しかし、必要な医行為のすべてを担 当できるだけの看護師の配置を短期間のうちに行うことには困難があることも予 想される。 したがって、看護師を中心としながら看護師と教員とが連携・協力して実施す るモデル事業等の成果を踏まえ、こうした方式を盲・聾・養護学校全体に許容す ることは、医療安全の確保が確実になるような一定の条件の下では、やむを得な い。 なお、盲・聾・養護学校における看護師及び教員による医行為は、適切な医学 的管理を前提に、学校長の統括の下、組織的に実施される必要がある。万一事故 が発生したときの第一義的な責任は学校にあると考えられるが、具体的な責任の 所在は事故の形態や過失の程度によって変わり得る。 2 肢体不自由養護学校において、日常的に経管栄養、吸引(口腔内、鼻腔内、気管内)、酸素吸入、ネブライザーに よる吸入、薬液の吸入、人工呼吸器の使用、気管切開部の管理、経鼻エアウェイの装着、自己導尿又は介助導尿を必要 とする児童生徒(通学生)の割合は、平成8年度の10.6%から平成15年度の18.7%に増加した。(肢体不自 由養護学校長会調査) 3 盲・聾・養護学校における業務にかんがみ、3(1)(イ)において述べる看護師のように、重度障害児の看護に 十分な知識・経験のある保健師、助産師及び准看護師を含む。 (1)モデル事業等において教員に認められていた行為を盲・聾・養護学校全体に 許容する場合の要件 モデル事業等の対象となったたんの吸引等には医療関係者が行うのでなけれ ば危険を伴う部分があるため、モデル事業等において教員に認められていた行 為を盲・聾・養護学校全体に許容する上では、看護師の適正な配置等による医 療関係者の関与など必要な条件を明らかにしておく必要がある。 以下において、モデル事業等における評価を踏まえ、教員が行うことが許容 される医行為の範囲と、それらを適正に実施するための条件を示す。 (ア) 教員が行うことが許容される行為の範囲 △ 医行為は医療関係者が行うのが原則であり、教員は医療の専門家として の訓練を受けていない。このため、モデル事業等では、教員が行える行為 は、他の行為に比べ、医療関係者との協力の下では相対的に危険性の程度 が低く、また、日常的に行われる頻度が高いと考えられた範囲( (1)咽頭 より手前のたんの吸引、 (2)咳や嘔吐、喘鳴等の問題のない児童生徒で留 置されている管からの注入による経管栄養、(3)自己導尿の補助 )に限定 されている。 △ たんの吸引、経管栄養、自己導尿の補助という3つの行為は、モデル事 業等における要件の下では、概ね安全に実施されているものと認められる。 ただし、その前提として、3つの行為の内容について一定の共通理解が存 在することが不可欠であると考えられるため、これら3つの行為の標準的 手順と、医療関係者との連携を含む一定の条件の下で教員が行うことが許 容される行為の標準的な範囲を別紙1に示す。 △ なお、胃ろう・腸ろうによる経管栄養については、モデル事業等の対象 として明示されていないが、鼻腔を経由しての経管栄養に比べ、医学的に 見ても相対的に安全であるとの評価が定着している。肉芽などの問題があ る場合の衛生管理は看護師が行う等の条件が整っていれば、胃ろう・腸ろ うからの食物・栄養物の注入を教員が行ったとしても、安全が確保できる と考えられる。このため、盲・聾・養護学校において教員が行い得る経管 栄養に含めて考えて差し支えない。 △ 導尿については、モデル事業等では、児童生徒等が自ら導尿を行う場合 の教員の補助を念頭に、「自己導尿の補助」を教員が行うことが許される こととされていたが、その部分の記述だけでは必ずしも導尿の手順全体が 明らかにならないので、この報告では、モデル事業等の成果を踏まえつつ、 導尿の手順全体を記述した上で看護師が行うべき部分と、教員が行うこと も認められる部分とを明らかにしている。 (イ)非医療関係者である教員がたんの吸引等を実施する上で必要であると考え られる条件 △ 非医療関係者である教員がたんの吸引等を実施する上で、本来、教員は 医行為を行う職種としての専門的訓練を受けていないことから慎重な対応 が求められ、その実施においても、危険をできるだけ減少させるため具体 的方策を立てるとともに、責任の所在を明確にする必要がある。 △ したがって、盲・聾・養護学校においてたんの吸引等を安全かつ適切に 実施するためには、非医療関係者である教員がたんの吸引等を行うことに 鑑み、教員の希望等を踏まえるなど十分な理解を得た上で、必要な研修を 行い、上記の標準的な手順を参考に、医師の承認の下、保護者及び学校長 の了解した範囲の行為のみを実施することが必要である。また、医療関係 者間の指示系統の明確化を含め適正な医学的管理の確保のための条件を整 える必要がある。 △ 特に看護師の配置は重要な要素であり、児童生徒等が学校に滞在してい る間、重度障害児の看護に経験を有する看護師が適正に配置されるととも に、医療機器の整備を含め学校内の医療安全体制に関与する仕組みとする 必要がある。 △ また、養護学校においては、校内感染の予防に注意する必要があり、看 護師等医療関係者による適切な感染管理が行われることが不可欠である。 △ 上記の課題を踏まえ、非医療関係者である教員が医行為を実施する上で 必要であると考えられる条件は、別紙2の通りである。 (2)法律的整理 (ア)実質的違法性阻却 △ すでに述べたとおり、医師法第17条は、医師以外の者が医行為を反復 継続する意思をもって行うことを禁止している。教員によるたんの吸引等 の行為も、その本来の業務であるか否かを問わず、反復継続している以上 医業に該当し、形式的には医師法第17条違反の構成要件に該当する部分 がある。 △ しかし、構成要件に該当していたとしても、当該行為の目的が正当であ り手段が相当であることなどの条件を満たしていれば、違法性が阻却され ることがあり得ることは、学説・判例が認めるところである。 △ 前出のALS分科会報告書は、医療の資格を持たないホームヘルパー等 がたんの吸引を行えば形式的には医師法第17条違反の構成要件に該当す るが、当該行為が在宅のALS患者とその家族の負担を軽減するという目 的のため、医師の関与や患者の同意、たんの吸引を行う者に対する訓練な どALS分科会報告書によって明示された条件を満たして行われているの であれば、実質的に違法性が阻却されるという考え方に基づいているもの と考えられる。 △ 医師法第17条の究極の目的は国民の健康な生活の確保であり、この趣 旨を没却するような解釈は許されない。しかし、現在の盲・聾・養護学校 をとりまく状況を前提とすると、盲・聾・養護学校の児童生徒等に適切な 医療を提供しつつ教育を受けさせるためには、この報告が検討の対象とし ている盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の行為についてもALS分 科会報告書と同様の違法性阻却の考え方を当てはめることは法律的には許 容されるのではないかと考えられる。 (イ) 判例の示す違法性阻却の5条件 △ 刑罰法規一般について、判例が実質的違法性阻却事由としてほぼ共通に 挙げる条件は、 (1)目的の正当性(単に行為者の心情・動機を問題にする のではなく、実際に行われる行為が客観的な価値を担っていること)、 (2)手段の相当性(具体的な事情をもとに、「どの程度の行為まで許容され るか」を検討した結果として、手段が相当であること)、 (3)法益衡量 (特定の行為による法益侵害と、その行為を行うことにより達成されること となる法益とを比較した結果、相対的に後者の法益の方が重要であること)、 (4)法益侵害の相対的軽微性(当該行為による法益侵害が相対的に軽微であ ること)、 (5)必要性・緊急性(法益侵害の程度に応じた必要性・緊急性 が存在すること)である。 4 今回の問題についても、実質的違法性阻却を 説明する上では、これらの実務上の5つの要件該当性を確認することが適 当である。 4 前田雅英『刑法総論講義(第3版)』東京大学出版会(平成10年)206・207頁。 △ 以下で、上の5つの条件について、たんの吸引等を医療関係者でない教 員が行うことと医師法第17条との関係についてみる。 △ 目的の正当性についてみると、盲・聾・養護学校において教員がたんの 吸引等を限定された範囲で行うのは、児童生徒等が盲・聾・養護学校にお いて教育を受けることができるようにするためであり、憲法第26条の教 育を受ける権利の実質的な保障のための措置であること、また、保護者の 負担の軽減のためでもあることから、単に関係者の一方的な善意のみでは ない客観的な価値を担っているということができる。 △ 手段の相当性についてみると、教員が行うたんの吸引等は、別紙1に掲 げる範囲で、医療関係者の関与など別紙2の条件を守って行われる場合に は、医療の安全が十分に確保され、手段として相当であるということがで きる。 △ 法益衡量についてみると、医療のニーズの高い児童生徒等が盲・聾・養 護学校において医療の安全を確保した上で教育を受けることができるよう になるという利益と、医療関係者ではない一般の教員が一定の限定された 範囲の医行為を行った場合の法益侵害とを比較すると、上記の手段の相当 性、下記の法益侵害の相対的軽微性と合わせて考えれば、前者の利益の方 が後者の法益侵害よりも大きいのではないかと考えられる。 △ 法益侵害の相対的軽微性についてみると、今回の措置は、盲・聾・養護 学校という限定された場で、児童生徒等が必要とする医療のうち必要な条 件を整えれば医療に関する資格を有していない教員であっても安全に実施 できると考えられるものだけを、看護師の常駐の下で、児童生徒等及び保 護者の信頼を得た特定の教員が必要な研修を受けた上で行うものである。 したがって、無資格医業を助長するものではなく、公衆衛生上の危険は相 対的に小さいと考えることができる。 5 5 法益侵害の相対的軽微性とは、たんの吸引等の行為が本来危険を伴わないという意味ではない。 △ 必要性・緊急性についてみると、盲・聾・養護学校の現在の職員配置を 前提とすれば、児童生徒等に対し教育を提供していく上で、教員がたんの 吸引等を行う必要性があり、かつ、それらの行為を緊急に実施することが 不可欠である。 △ したがって、判例から抽出された上記の5つの条件に照らしてみても、 教員によるたんの吸引等は、医師法第17条との関係では違法性が阻却さ れるものと考えられる。 (3) 環境の変化に応じた見直し ○ 今回の考え方の整理は、現状及びこれまでの知見を念頭に置いたものであ り、医療を必要とする児童生徒等を取り巻く環境の変化に応じて適宜見直す 必要がある。また、盲・聾・養護学校全体に教員によるたんの吸引等を許容 する上では、モデル事業等の成果や本報告の趣旨が関係者に周知徹底される ようきめ細かな研修を行うとともに、実施状況の点検・評価等を通じ医療安 全の確保に十分配意することも重要である。このため、厚生労働省及び文部 科学省は、盲・聾・養護学校における医療を必要とする児童生徒等の状況、 看護師の配置状況、医療技術の進歩等の状況について、今後とも継続的に把 握を行い適切に対応することが必要である。 4 おわりに ○ 盲・聾・養護学校において医療のニーズの高い児童生徒等に対して適切な医 療を保障していくため、盲・聾・養護学校において医療を適切に提供していく 体制の整備の必要性が認識されたことが、平成10年度の文部科学省の実践研 究が開始された当時の出発点であった。以来、6年余の年月を経て、モデル事 業等で行われた体制の整備を、盲・聾・養護学校全体に許容することが可能な 段階に達している。 ○ この報告では、盲・聾・養護学校において、たんの吸引等を適切に行うため の条件を示したが、この報告による提言が多くの盲・聾・養護学校で実施に移 されれば、医療のニーズの高い児童生徒等のうち通学する者の教育環境が向上 し、盲・聾・養護学校における教育は新たな展開の時を迎えることとなる。 ○ したがって、国においては、本報告を踏まえ、早期に適切な取扱い方針を打 ち出すべきである。また、厚生労働省と文部科学省が密接に連携し、盲・聾・ 養護学校における看護師の適正配置など体制整備の状況を継続的に点検し、そ れらの水準の維持・向上のための方策を探っていくべきである。 ○ また、増大する医療需要に対応し、盲・聾・養護学校の児童生徒等に必要な 医療を適切に提供するため、看護師の適正配置への努力など、地域医療関係者、 教育関係者をはじめ、都道府県保健福祉担当部局、都道府県教育委員会等の一 層の努力を要請したい。
(別紙1) たんの吸引、経管栄養及び導尿の標準的手順と、教員が行うことが許容される 行為の標準的な範囲 たんの吸引、経管栄養及び導尿について、文部科学省のモデル事業等における 実績と現在の医学的知見を踏まえると、看護師が当該盲・聾・養護学校に配置さ れていることを前提に、所要の研修を受けた教員が行うことが許容される行為の 標 準的な範囲は、それぞれ以下の通りである。しかし、いずれの行為にあって も、その処置を行うことが適切かどうかを医療関係者が判断し、なおかつ、具体 的手順については最新の医学的知見と、当該児童生徒等の個別的状況を踏まえた 医療関係者の指導・指示に従うことが必要であり、緊急時を除いては、教員が行 う行為の範囲は医師の指示の範囲を超えてはならない。 1 たんの吸引 (1)標準的な手順 (1) 深く入りすぎないようにあらかじめチューブを挿入する長さを決めておく。 (2) 適切な吸引圧で、吸引チューブを不潔にしないように、吸引する。 (3) 咽頭にある痰を取り除くには、鼻腔から吸引チューブを挿入して吸引した 方が痰を取り除きやすい場合もある。 (4) その場合、鼻腔粘膜などを刺激して出血しないようにチューブを入れる方 向等に注意しながら挿入する。 (2)教員が行うことが許容される標準的な範囲と看護師の役割 (1) 咽頭より手前の範囲で吸引チューブを口から入れて、口腔の中まで上がっ てきた痰や、たまっている唾液を吸引することについては、研修を受けた教 員が手順を守って行えば危険性は低く、教員が行っても差し支えないものと 考えられる。 (2) 鼻からの吸引には、鼻腔粘膜やアデノイドを刺激しての出血が、まれでは あるが生じうる。また、鼻や口からの、咽頭の奥までの吸引を行えば、敏感 なケースでは嘔吐・咳込み等の危険性もある。したがって、鼻からの吸引や、 口から咽頭の奥までの吸引は、「一般論として安全である」とは言い難い。 しかし、鼻からの吸引は、児童生徒等の態様に応じ、吸引チューブを入れる 方向を適切にする、左右どちらかのチューブが入りやすい鼻からチューブを 入れる、吸引チューブを入れる長さをその児童生徒等についての規定の長さ にしておく、などの手順を守ることにより、個別的には安全に実施可能であ る場合が多い。以上の点を勘案すると、教員は、咽頭の手前までの吸引を行 うに留めることが適当であり、咽頭より奥の気道のたんの吸引は、看護師が 担当することが適当である。 2 経管栄養(胃ろう・腸ろうを含む) (1)標準的な手順 (1) 鼻からの経管栄養の場合には、既に留置されている栄養チューブが胃に挿 入されているか注射器で空気を入れ、胃に空気が入る音を確認する。 (2) 胃ろう・腸ろうによる経管栄養の場合には、び爛や肉芽など胃ろう・腸ろ うの状態に問題がないことの確認を行う。 (3) 胃・腸の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量を確認、胃や腸 の状態を確認し、注入内容と量を予定通りとするかどうかを判断する。 (4) あらかじめ決められた注入速度を設定する。 (5) 楽な体位を保持できるように姿勢の介助や見守りを行う。 (6) 注入終了後、微温湯を注入し、チューブ内の栄養を流し込む。 (2) 教員が行うことが許容される標準的な範囲と看護師の役割 (1) 鼻からの経管栄養の場合、栄養チューブが正確に胃の中に挿入されている ことの確認は、判断を誤れば重大な事故につながる危険性があり、看護師が 行うことが適当である。 (2) 胃ろう・腸ろうによる経管栄養は、鼻からの経管栄養に比べて相対的に安 全性が高いと考えられるが、胃ろう・腸ろうの状態に問題のないことの確認 は看護師が行うことが必要である。 (3) 経管栄養開始時における胃腸の調子の確認は、看護師が行うことが望まし いが、開始後の対応は多くの場合は教員によっても可能であり、看護師の指 示の下で教員が行うことは許容されるものと考えられる。 3 導尿 (1)標準的な手順 (1) 全手順を通じ、身体の露出を最小限とし、プライバシーの保護に努める。 (2) 尿道口を消毒薬で清拭消毒する。 (3) カテーテルが不潔にならないように、尿道口にカテーテルを挿入する。 (4) カテーテルの挿入を行うため、そのカテーテルや尿器、姿勢の保持等の補 助を行う。 (5) 下腹部を圧迫し、尿の排出を促す。 (6) 尿の流出が無くなってから、カテーテルを抜く。 (2)教員が行うことが許容される標準的な範囲と看護師の役割 ○ 尿道口の清拭消毒やカテーテルの挿入を本人が自ら行うことができない場 合には、看護師が行う。 ○ 本人又は看護師がカテーテルの挿入を行う場合には、尿器や姿勢の保持等 の補助を行うことには危険性はなく、教員が行っても差し支えないものと考 えられる。
(別紙2) 非医療関係者の教員が医行為を実施する上で必要であると考えられる条件 1 保護者及び主治医の同意 (1) 保護者が、当該児童生徒等に対するたんの吸引等の実施について学校に依頼 し、学校の組織的対応を理解の上、教員が当該行為を行うことについて書面に より同意していること (2) 主治医が、学校の組織的対応を理解の上、教員が当該行為を行うことについ て書面により同意していること 2 医療関係者による的確な医学管理 (3) 主治医から看護師に対し、書面による必要な指示があること (4) 看護師の具体的指示の下、看護師と教員が連携・協働して実施を進めること (5) 児童生徒等が学校にいる間は看護師が学校に常駐すること (6) 保護者・主治医 ※・看護師及び教員の参加の下、医学的管理が必要な児童生 徒ごとに、個別具体的な計画が整備されていること 3 医行為の水準の確保 (7) 看護師及び実施に当たる教員が必要な知識・技術に関する研修を受けている こと (8) 特定の児童生徒等の特定の医行為についての研修を受け、主治医 ※が承認し た特定の教員が実施担当者となり、個別具体的に承認された範囲で行うこと (9) 当該児童生徒等に関する個々の医行為について、保護者、主治医 ※、看護師 及び教員の参加の下、技術の手順書が整備されていること 4 学校における体制整備 (10) 学校長が最終的な責任を持って安全の確保のための体制の整備を行うため、 学校長の統括の下で、関係者からなる校内委員会が設置されていること (11) 看護師が適正に配置され、児童生徒等に対する個別の医療環境に関与するだ けでなく、上記校内委員会への参加など学校内の体制整備に看護師が関与する ことが確保されていること (12) 実施に当たっては、非医療関係者である教員がたんの吸引等を行うことにか んがみ、学校長は教員の希望等を踏まえるなど十分な理解を得るようにするこ と (13) 児童生徒等の健康状態について、保護者、主治医 ※、学校医、養護教諭、看護 師、教員等が情報交換を行い連携を図れる体制の整備がなされていること。同 時にそれぞれの責任分担が明確化されていること (14) 盲・聾・養護学校において行われる医行為に関し、一般的な技術の手順書が 整備され、適宜更新されていること (15) 指示書や指導助言の記録、実施の記録が作成され、適切に管理・保管されて いること (16) ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、医師・看護師の参加の下で、定期的な 実施体制の評価、検証を行うこと (17) 緊急時の対応の手順があらかじめ定められ、その訓練が定期的になされてい ること (18) 校内感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分留意すること 5 地域における体制整備 (19) 医療機関、保健所、消防署等地域の関係機関との日頃からの連絡支援体制が 整備されていること (20) 都道府県教育委員会等において、総括的検討・管理が行われる体制の整備が 継続的になされていること ※ 学校が依頼し、主治医の了承の下に指導を行う「指導医」がいる場合は「指導医」も含む。
(別紙3) 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の実施体制(例)大きなサイズで表示
(参考1) 在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に 関する研究会委員名簿(五十音順) 青木重孝 (社)日本医師会常任理事 阿部俊子 (社)日本看護協会副会長 飯野順子 筑波大学附属学校教育局教授 伊藤道哉 東北大学大学院医学系研究科講師 井上愛子 東京都多摩立川保健所企画調整課 川村佐和子 東京都立保健科学大学保健科学部看護学科教授 北住映二 心身障害児総合医療療育センター外来療育部長 ○ 木村光江 東京都立大学法学部教授 島崎謙治 国立社会保障・人口問題研究所副所長 中桐佐智子 吉備国際大学保健科学部看護学科学科長 ◎ 樋口範雄 東京大学大学院法学政治学研究科教授(英米法) 福原信義 上越総合病院神経内科(脳神経センター長) 山路憲夫 白梅学園短期大学福祉援助学科教授 ※ ◎:座長 ※ ○:副座長 ※ 敬称略
(参考2) 「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究」 これまでの検討経緯 ------------------------------------------------------------------------- 回 数 開催日時 議事内容 ------------------------------------------------------------------------- 第1回 5月31日(月) (1) これまでの経緯 16:00~18:00 (2) 盲・聾・養護学校に通う児童生徒に対する 日常的な医療の現状 ------------------------------------------------------------------------- 第2回 6月2日(水) 関係者からのヒアリング 14:00~16:00 ------------------------------------------------------------------------- 6月21日(月) 千葉県立桜が丘養護学校(モデル事業実施校) 11:00~14:00 視察 ------------------------------------------------------------------------- 第3回 6月30日(水) (1) モデル事業の成果について 10:00~12:00 (2) 論点整理メモ(案)について ------------------------------------------------------------------------- 第4回 7月7日(水) (1) 看護師の配置状況について 10:00~12:00 (2) 盲・聾・養護学校において教員が行う医行 為の範囲について (3) 教員が医行為を実施する上で最低限満たし ている必要のある条件(案)について (4) 盲・聾・養護学校の教員による医行為の位 置づけの考え方について ------------------------------------------------------------------------- 第5回 7月22日(木) 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の医学 16:00~18:00 的・法律学的整理について(たたき台) -------------------------------------------------------------------------