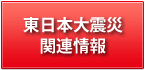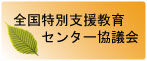ホーム > 図書室利用案内・データベース >
特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 就学奨励 - 学校給食における食事内容について(通達) -
15文科ス第121号
平成15年5月30日
附属学校を置く各国立大学長
国立久里浜養護学校長
各都道府県知事 殿
各都道府県教育委員会教育長
文部科学省スポーツ・青少年局長
田 中 壮 一 郎
学校給食における食事内容について
このたび、平成15年5月30日付けをもって、別紙1及び別紙2のとおり「学校給食実施基準」
(昭和29年文部省告示第90号)及び「夜間学校給食実施基準」(昭和32年文部省告示第28号)の
一部がそれぞれ改正され、義務教育諸学校及び夜間課程を置く高等学校における学校給食の児童又
は生徒1人1回当たりの平均栄養所要量の基準の改訂が行われました。併せて、別表のとおり『盲
学校、聾学校及び養護学校の幼児1人1回当たりの平均栄養所要量の基準」を改訂しました。
ついては、別記のとおり、このたびの改訂の趣旨を御理解いただくとともに、改訂の趣旨を踏ま
えた学校給食の食事内容の充実等が図られるよう願います。
また、都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会並びに学校給食実施校等に対し
て、都道府県知事におかれては所轄の私立学校に対して、この趣旨を周知徹底されるとともに、適
切に指導するよう併せて願います。
なお、平成7年3月29日付け文体学第131号「学校給食の食事内容について」は廃止します。
記
1 学校給食の栄養所要量の基準について
(1) 学校給食における平均栄養所要量については、義務教育諸学校の児童生徒については学校
給食実施基準別表(別紙1)に、夜間課程を置く高等学校の生徒については夜間学校給食実施
基準別表(別紙2)に、盲学校、聾学校及び養護学校(以下「特殊教育諸学校」という。)の幼稚
部の幼児については別表にそれぞれ掲げる基準によること。
(2) これらの栄養所要量の基準は、厚生労働省が定める日本人の栄養所要量の基準を参考とし、
食事摂取基準の考え方を斟酌しつつ、児童生徒等の健康の保持増進を図るのに望ましい栄養
量として算出されたものであるが、 これは、児童生徒等の1人1回当たりの全国的な平均値
を示したものである。したがって、適用に当たっては、個々の児童生徒等の健康及び生活活
動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。
(3) 今回の栄養所要量の基準の改訂についての基本的な考え方は次のとおりである。
エネルギー
学校給食のエネルギー所要量は、1日の所要量の33%とした。生活活動強度は、望まし
い生活習慣として適度な活動強度である基礎代謝の1.7倍を用いた。
たんぱく質
児童生徒等のたんぱく質所要量は、体重当たりのたんぱく質所要量から1日の所要量を求め
ており、前回と同様に1日の所要量の40%程度としたこと。
脂質
脂質はエネルギー源として、あるいは必須脂肪酸の供給など、健康増進に大切な栄養素であ
るが、過剰な摂取は肥満等の生活習慣病につながる可能性がある。したがって、脂質の所要量
としてのエネルギー比は前回と同様に摂取エネルギーの25~30%としたこと。
カルシウム
カルシウムは、日常の食生活において摂取しにくい実態を考慮しつつ、学校給食の役割を考
え、前回とほぼ同様に1日の所要量の50%としたこと。
鉄
日常の食生活で鉄の所要量を満たすのは一般的に容易ではないことから、学校給食では1日
の所要量の三分の一程度の摂取は必要であり、1日の所要量の33%としたこと。
ビタミン類
ビタミン類は、日常の食生活の中で摂取できるようになってきており、基本的には1日の所
要量の33%とした。ただし、ビタミンB1は欠乏症になりやすいため40%とし、ビタミン
B2は牛乳を飲用することにより確保できるため40%としたこと。
なお、ビタミンAの単位は、世界的に国際単位(IU)から重量単位(レチノール当量)に移
行していることから重量単位とした。
食物繊維
食物繊維の所要量は、1日の所要量において摂取エネルギー1000kcal当たり10gとされてい
るので、各年齢のエネルギー当たりに換算して策定した。
食物繊維は、人の消化管内では消化されないため、糞便量を増やし大腸内の環境を整える効
果が認められている。また、保水性、粘性あるいは、粘着力などの物理的な性質によって、血
清脂質や血糖値の改善も期待される。したがって、近年の生活習慣病の若年化など児童生徒の
健康問題を考慮し、食物繊維を新たに基準値として位置付けた。
ナトリウム(食塩相当量)
食塩摂取量については、 高血圧予防の観点から1日10g未満にすることが望ましいとされて
おり、学校給食においては、食塩相当量を3g以下としたこと。
なお、健康教育の観点から幼児期より薄味の習慣化を図るよう配慮するため、ナトリウムを
新たに基準値として位置付けた。
マグネシウム及び亜鉛(目標値)
マグネシウム及び亜鉛などの微量栄養素については、その欠乏により様々な疾患を誘引すると
して重要視されており、マグネシウムと亜鉛の摂取に配慮するよう、マグネシウム及び亜鉛を新
たに目標値として位置付けた。
2 学校給食における食品構成について
(1) 学校給食における食品構成は、食品の種類を幅広く求め、これを適切に組み合わせて食事内
容の充実及び栄養所要量の均衡を図るように配慮すること。実施に当たっては、次のことに留
意しつつ、児童生徒等の個々の健康及び生活活動等の実態並びに家庭における食生活や地域の
実情等に十分配慮して創意工夫すること。
我が国の伝統的な食文化を継承し、日本型の食生活が実践できるよう配慮すること。
豆類は、脂質とたんぱく質を多く含み、古くから動物性食品に代わるものとして日本人に摂
取されてきたが、これまでは、豆類の中では豆製品が中心に摂取されているため、植物性たん
ぱくの豊富な豆の摂取等についても配慮すること。
カルシウムなどの微量栄養素の供給源として小魚類を摂取することは重要であること。
家庭における日常の食生活の指標になるものとして、その摂取状況に近いものを採用するよう
配慮すること。
食に関する指導の生きた教材として、広く児童生徒等や保護者等にわかりやすいものとし、
日常の食生活への導入や活用に役立つよう工夫すること。
(2) 牛乳については、児童生徒等のカルシウム摂取に効果的であるため、その飲用に努めること。
なお、家庭の食事においてカルシウムの摂取が不足している地域にあっては、積極的に調理
用牛乳の使用や乳製品の使用に努めること。
3 学校給食の食事内容の充実等について
(1) 学校給食の食事内容は、成長期にある児童生徒等の健康の保持増進と体位の向上のため、多
様な食品を組合せ、栄養的にバランスのとれた食事となるよう絶えず改善に努めること。また、
学校給食の実施に当たっては、児童生徒等の発達段階に応じて指導するとともに、特に次の点
に配慮すること。
郷土食や地場産物の導入に関しては、様々な教育的意義があり、食に関する指導の生きた教
材としてより効果的に活用できることから、地域の実情に応じた活用について十分に工夫し、
魅力あるものとなるよう努めること。
食物アレルギー等を持つ児童生徒等に対しては、学校医、校長、学級担任、学校栄養職員等
が密接に連携して学校内の体制等を整備し、できるだけ一人一人の児童生徒等の健康状態や個
人差を把握しながら、個に応じた対応を行うことが大切であること。
(2) 献立作成及び調理に当たっては、児童生徒等の嗜好の偏りをなくし、食に関する指導の生き
た教材として活用できるよう食品の組合せ、調理方法等を工夫すること。
また、食事は調理後できるだけ短時間に適温で供食でき、衛生的かつ安全であるよう十分配
慮すること。
さらに、調理の多様化等を図るため、必要な調理用機械器具の導入について考慮すること。
(3) 食器具については、安全性が確保されたものであること。また、児童生徒等の望ましい食習
慣の形成に資するため、料理形態に即した食器具の使用に配慮するとともに、教育的効果が高
いため、地場産物の使用に配慮すること。
(4) 喫食の場所については食事にふさわしいものとなるよう改善工夫を行うこと
(5) 望ましい生活習慣を形成するため、適度な運動、調和のとれた食事、十分な休養・睡眠とい
う生活習慣全体を視野に入れた指導の取組にも配慮すること。
4 特殊教育諸学校における食事内容の改善について
(1) 特殊教育諸学校の幼児、児童及び生徒については、障害の種類と程度が多様であり、日常の
生活活動量が様々であることから、栄養所要量の基準の適用については、個々の児童生徒等の
健康状態及び生活活動の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。
(2) 児童生徒等が楽しく、満足して食べることができるように、食事内容を多様化するよう努め
るとともに、障害を持った児童生徒等が無理なく食べられるような献立や調理についても配慮
すること。
(3) 特殊教育諸学校の児童生徒等に対する食事管理については、家庭での食生活や寄宿舎、病院
での食事と密接に関連するものであり、学級担任、学校栄養職員、養護教諭、学校医、主治医
及び保護者等関係者が適切に連携し、共通理解を図りながら、適度な運動など生活習慣全体を
視野に入れた取組を進めつつ、食事管理に当たるよう努めること。
5 その他
学校給食における栄養所要量の基準の改訂等に際して、文部科学省に調査研究協力者会議を設
置し検討を行ってきたので、「学校給食における栄養所要量の基準等について(報告)(平成15年3
月)」を参考とされたいこと。
別紙1
児童又は生徒1人1回当たりの平均栄養所要量の基準
区 分 |
栄養量 |
|||
| 児童(6歳~7歳)の場合 | 児童(8歳~9歳)の場合 | 児童(10歳~11歳)の場合 | 児童(12歳~14歳)の場合 | |
| エネルギー (Kcal) | 580 |
650 |
730 |
830 |
| たんぱく質 (g) | 21 |
24 |
28 |
32 |
| 脂 質 (%) | 学校給食による摂取エネルギー全体の25%~30% |
|||
| ナトリウム(食塩相当量)(g) | 3以下 |
3以下 |
3以下 |
3以下 |
| カルシウム (mg) | 300 |
330 |
350 |
400 |
| 鉄 (mg) | 3 |
3 |
3 |
4 |
| ビタミンA (μgRE) | 120 |
130 |
150 |
190 |
| ビタミンB1(mg) | 0.3 |
0.3 |
0.4 |
0.4 |
| ビタミンB2(mg) | 0.3 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
| ビタミンC (mg) | 20 |
20 |
25 |
25 |
| 食物繊維 (g) | 5.5 |
6.5 |
7 |
8 |
(注) 1 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取量について配慮 すること。 マグネシウム ・・・・・・ 児童(6歳~7歳)60mg、 児童(8歳~9歳)70mg、 ・・・・・・ 児童(10歳~11歳)80mg、生徒(12歳~14歳)110mg 亜 鉛 ・・・・・・ 児童(6歳~7歳) 2mg、児童(8歳~9歳) 2mg、 ・・・・・・ 児童(10歳~11歳) 2mg、生徒(12歳~14歳) 3mg 2 この栄養所要量の基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、 個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する こと。
別紙2
夜間課程を置く高等学校の生徒1人1回当たりの平均栄養所要量の基準
区 分 |
栄 養 量
|
| エネルギー (Kcal) | 830 |
| たんぱく質 (g) | 29 |
| 脂 質 (%) | 学校給食による摂取エネルギー全体の25%~30% |
| ナトリウム(食塩相当量)(g) | 3以下 |
| カルシウム (mg) | 350 |
| 鉄 (mg) | 4 |
| ビタミンA (μgRE) | 190 |
| ビタミンB1(mg) | 0.4 |
| ビタミンB2(mg) | 0.5 |
| ビタミンC (mg) | 30 |
| 食物繊維 (g) | 8 |
(注) 1 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取量について配慮 すること。 マグネシウム ・・・・・・130mg、 亜 鉛 ・・・・・・3mg、 2 この栄養所要量の基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、 個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する こと。
別 表
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児1人1回当たりの平均栄養所要量の基準
区 分 |
栄 養 量
|
| エネルギー (Kcal) | 540 |
| たんぱく質 (g) | 18 |
| 脂 質 (%) | 学校給食による摂取エネルギー全体の25%~30% |
| ナトリウム(食塩相当量)(g) | 3以下 |
| カルシウム (mg) | 250 |
| 鉄 (mg) | 2.5 |
| ビタミンA (μgRE) | 100 |
| ビタミンB1(mg) | 0.2 |
| ビタミンB2(mg) | 0.3 |
| ビタミンC (mg) | 17 |
| 食物繊維 (g) | 5 |
(注) 1 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取量について配慮 すること マグネシウム ・・・・・・40mg、 亜 鉛 ・・・・・・2mg、 2 この栄養所要量の基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、 個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する こと。 3 幼稚園の幼児に供する食事内容については、この基準を参考とすること