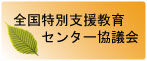ホーム > メールマガジンバックナンバー >
国立特別支援教育総合研究所メールマガジン 第6号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国立特別支援教育総合研究所メールマガジン 第6号 2007.9.3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ NISE ━ 【目次】 ■研究所からのお知らせ ■今月の特集 ■研究所の研究活動 ■特別支援教育トピックス ■研修員だより ■編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■研究所からのお知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●平成18年度に実施した研究について、下記のとおり研究報告書、ガイドブ ック・マニュアル等を刊行し、今月中に各関係機関に送付する他、研究所Web に掲載します。 ◇平成18年度終了研究成果報告書・ガイドブック・マニュアル ○プロジェクト研究 1「拡大教科書作成システムの開発とその教育効果の実証的研究」報告書 2「特別支援教育に於ける教育課程の編成・実施の推進に向けた実際的研究」 -特別支援教育の充実に向けた教育課程編- ○課題別研究 1「言語に障害のある子どもへの教育的支援に関する研究 -吃音のある子 どもの自己肯定感形成を中心に-」報告書 吃音のある子どもの自己肯定感を支えるために 2「慢性疾患児(心身症や不登校を含む)の自己管理支援のための教育的対応 に関する研究」報告書 3「脳科学と障害のある子どもの教育に関する研究」報告書 4「ICF及びICF-CYの活用 試みから実践へ-特別支援教育を中心に-」 5「地域の支援をすすめる教育相談の在り方に関する実際的研究」報告書 -学校コンサルテーションケースブック- 6「地域の支援をすすめる教育相談の在り方に関する実際的研究」報告書 -学校コンサルテーションを進めるためのガイドブック- ○調査研究 1「乳幼児期からの一貫した軽度発達障害者支援体制の構築に関する研究」 報告書 2「障害のある児童生徒等の教育の総合的情報提供体制におけるコンテンツ の充実・普及方策に関する実際的研究」報告書 3「全国難聴・言語障害学級及び通級指導教室実態調査」結果報告書 ○共同研究 1「発達障害のある学生支援ケースブック-支援の実際とポイント-」 2「パーソナルロボットの特性を利用した障害者向けインターフェースの開 発」報告書 3「電子透かし技術を応用した障害児者のための情報補償システムの開発 -音響の情報バリアフリー化に向けて-」報告書 ◇平成19年度継続研究のうち報告書をとりまとめた課題 ○プロジェクト研究 1「小・中学校における特別支援教育への理解と対応の充実に向けた総合的 研究研究活動報告」 2「小・中学校における特別支援教育への理解と充実に向けた盲・聾・養護 学校のセンター的機能に関する調査報告書(速報版)」 3「小・中学校における特別支援教育への理解と充実に向けた教育委員会に 関する調査報告書(速報版)」 研究所の刊行物は下記からご覧になれます。 ○こちら→http://www.nise.go.jp/blog/kankoubutu.html ●第27回アジア・太平洋特別支援教育国際セミナー /NISE 障害者週間パネル展開催のお知らせ 本研究所では、1981年来アジア・太平洋地域における障害のある子どもの 教育の発展・充実に資するため、ユネスコ国内委員会の共催によるアジア・ 太平洋特別支援教育国際セミナーを毎年開催しています。本年度も我が国の 障害者週間行事として、12月4日~6日に「第27回アジア・太平洋特別支援教 育国際セミナ-」を開催します。 2006年度から新たに、5年間にわたるセミナーの基本テーマを「共生社会 を目指し、子ども一人一人のニーズに応じた教育の発展を考える」と設定し、 その下に今回は、「地域の社会資源と連携した、特別なニーズのある子ども のための学校運営~その工夫と課題~」をテーマに基調講演を行い、またア ジア・太平洋諸国から13カ国の代表者を招聘して各国報告・討議を行います。 また、併せてNISE障害者週間行事として、パネル展2007を開催し、障害に ついてご理解頂くために、障害のある子どもの教育に関わる方々ばかりでな く、広く一般の方々にも公開しております。 ■開催日程 平成19年12月4日(火)~12月6日(木) ■会場 横浜シンポジア(横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタ-ビル9F) ■参加予定国 オーストラリア、バングラディシュ、中国、インド、インドネシア、 日本、マレーシア、ニュージーランド、ネパール、パキスタン、 フィリピン、韓国、スリランカ、タイ 【日英同時通訳が付きます】 ○国際セミナーの詳細や参加の方法は、次号でご案内いたします。 ○これまでのセミナーの概要は →http://www.nise.go.jp/blog/kokusai2.html#asia ○本セミナーに関する問い合わせはこちら→ 同研究所総務部企画調整課広報国際係 TEL: 046-839-6811 FAX: 046-839-6919 E-mail:●平成19年度第32回特別支援教育教材教具展示会作品募集中! (財団法人障害児教育財団) 特別支援教育に携わる教職員が手作りし、教育・指導に活用している教材 教具(コンピュータによる学習ソフトウェアを含む。)の優秀な作品を紹介 ・表彰します。 以下のとおり募集しますので、多数の応募をお待ちしております。 なお、この展示会は今年で32回目となり、昨年の応募件数は72件で、文部 科学大臣賞は内藤壽先生(大阪府立寝屋川養護学校)が、受賞されました。 賞及び賞金: ・文部科学大臣賞 30万円 ・国立特別支援教育総合研究所理事長賞 20万円 ・障害児教育財団理事長賞 金賞 15万円 銀賞(2作品) 10万円 銅賞(3作品) 5万円 佳作(20作品程度) 1万円 ◇応募締め切り 平成19年10月16日(火)必着 ◇応募先 (財)障害児教育財団事務局 〒239-8585 神奈川県横須賀市野比5丁目1番1号 電話 046-839-6888 ○募集要項及び応募用紙はこちら→ http://www.nise.go.jp/blog/kyozaitenjikai.html ●ちょっと一息 季節のたより -夕焼け小焼け- 1923年9月1日に発生した関東大震災にちなんだ毎年9月1日の「防災の日」。 その日をまたがるこの「防災週間( 8月30日~9月5日)」に、地震を想定し た防災訓練に参加される機会も多いことと思います。関東大震災による横須 賀市の震度は6で、中心市街地は全滅し大きな被害を受けました。 さて、研究所のある三浦半島には、北から衣笠断層、北武断層、武山断層、 南下浦断層、引橋断層の5本の活断層が知られています。研究所の北側には、 そのうちの北武断層が走り、その東端が研究所の前の野比海岸で海中に入り こんでいます。また、それとほぼ平行して南に武山断層が走っています。 そして、なんと!様々な調査の結果、比較的近い将来において特にこの二 つの断層を起震断層とする、直下型地震が発生する危険性があることが報告 されています。(※ただし、ここでいう「近い将来」とは、現在を含む数100 年先ということである。)残暑も忘れるような背中の寒くなる話です。 横須賀市には防災行政無線が整備され、雷雨、台風や地震、津波などの気 象情報を知らせる非常放送は研究所の建物の中にまで、良く届きます。(普 段は夕方5時に「夕焼け小焼け」が流れる。) また、10月1日からは、全国 的に緊急地震速報の提供が始まります。 私たちは、災害にあったときにどうするのか、この防災週間を機に、改め て考え、再確認をしておく必要があります。夕刻「夕焼け小焼け」の平穏な 調べをいつも聞くことができる平和さを改めて考えずにはおれません。 参考: 地震調査委員会三浦半島断層群の長期評価について(平成14年10月9日) 地震関係基礎調査交付金による活断層調査事業(神奈川県) 三浦半島断層群に関する調査成果報告書(平成12年度) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■今月の特集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特別支援教育における生涯学習について 笹本 健(教育支援研究部・上席総括研究員) 1994年のサラマンカ宣言以来、インクルージョン、ノーマライゼーション の理念を背景として、国連では障害者権利条約や、ICFが採択されるなど、 障害がある人に対する環境の整備が国際的に急速に進められています。我が 国においても、このような流を反映し、障害者基本計画や中央教育審議会答 申において、障害のある子ども一人ひとりの教育的ニーズを正確に把握して 自立や社会参加を支援するという考え方に基づき、様々な体制整備が進めら れています。 一方、ポール・ラングラン(Paul Lengrand:仏)は、1965年ユネスコの成人 教育推進国際会議において、生涯教育(生涯学習)を提唱し、これが世界的 に認知されるようになりました。生涯学習とは、一人ひとりが自己の充実と 自らの生活の向上をめざし、自己にもっとも適した手段・方法で、生涯にわ たって行う学習活動のことです。 障害のある子どもの教育は、まず「一人ひとり」という個を重視し、障害 を発達的視点でとらえることが重要です。発達の各段階において、個に対す る支援の内容や方法が異なっていくことが想定されるためです。そして、こ うした支援には、医療、福祉、労働等の理解や協働が不可欠であり、これら の連携のもとに、生涯にわたって「一貫した支援」が実現されていくことが 大切です。障害のある子どもへの教育は、まさに生涯学習の理念に通じるも のがあるといえるのではないでしょうか。 これまで、特殊教育の時代においては、「個別の指導計画」に基づいて実 践があり、成果をあげてきました。今後、特別支援教育においては、「乳幼 児期から就労に至るまでの個に応じた一貫した支援」が重要であり、その実 現のためには、これまでの個別の指導計画を再検証し、上記の関係機関等と の有機的な関係の下に「個別の教育支援計画」を策定し、機能させていくこ とが重要です。この際、先に述べたような生涯学習の考え方に基づき、学校 教育期間に限らず、常に子どもの自己の充実と生活の向上を目指した学習活 動を行うことができるよう支援に取り組まなければなりません。 特別支援教育の推進が今後の我が国の生涯学習社会の構築にも寄与するこ とを願っています。 ○笹本 健(ささもと けん) →http://www.nise.go.jp/blog/2005/03/post_100.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■研究所の研究活動 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このコーナーでは、研究所の研究活動について紹介します。 今回は、課題別研究を2件紹介します。 ●課題別研究 「ICF児童青年期バージョンの教育施策への活用に関する開発 的研究」(平成18~19年度)について 徳永 亜希雄(企画部・主任研究員) 「障害者基本計画(2002)」において、 WHO(世界保健機関)の国際分類の 一つである「ICF(International Classification of Functioning, Dis- ability and Health、国際生活機能分類) 」(※1)の活用施策を検討する 必要性が指摘されて以降、個別の教育支援計画における活用等、特別支援教 育の分野においても様々な活用の取り組みが行われ、成果や課題が明らかに なってきました。それらの取り組みをまとめたものとして、本研究所と WHO との編著で「ICF活用の試み:障害のある子どもの支援を中心に」を2005年に 発行しました。 ○こちら→http://www.kyoikushinsha.co.jp/books/37.html また、今後の特別支援学校での教育課程の基準の在り方を検討している、 中央教育審議会の中の特別支援教育専門部会でも、特別支援教育におけるICF の活用の必要性が議論されており、本研究所からも資料提供を行いました。 ○こちら→ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/032/06091306.htm 一方、WHO は、20歳以下を対象とする ICFの派生分類、(ICF version for Children and Youth、ICF-CY、 ICF児童青年期バージョン、仮訳)の検討の ためのワーキンググループを2002年に設け、検討作業を進めてきました。 2006年10月、チュニジアで行われた WHO国際分類ファミリーネットワーク会 議において承認され、この秋にも WHOから出版される方向で動いています。 これらの動向を踏まえ、本研究では、教育施策においてICF-CYがどのよう な活用ができるのか、学校現場での活用も含めてその方向性について検討を 進めています。正式版の出版に先駆け、本研究においては、日本においてICF を所管している厚生労働省内担当部局の了解を得て全文翻訳を済ませ、研究 用資料として用いながら研究活動を進めています。また、ICF-CYの本格的な 導入を前にして、これまでのICFの活用動向を総括すると共に ICF-CYの概要 をまとめたものとして「ICF及びICF-CYの概要:試みから実践へ -特別支援 教育を中心に-」を発行します。 本研究では、国内外の関係機関・関係者と連携のもとで研究活動を行って おり、得られた研究成果について、これまでも国内外の学会や雑誌、Web( ※2)等で積極的に公表してきました。今後もそれらの活動を継続し、研究 期間の終了する年度末には、さらに具体的な形で成果を公表する予定です。 ※1 ICF の概要については、こちらの厚生労働省の Webページをご覧くだ さい。 →http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html ※2 本研究の概要はこちら →http://www.nise.go.jp/blog/2007/05/icf_2.html#torikumi ●課題別研究「盲学校等における視覚障害教育の専門性の向上と地域におけ るセンター的機能を果たすための小・中学校等のニーズに対応した支援の在 り方に関する実際的研究」(18~19年度)について 大内 進(企画部・上席総括研究員) 視覚障害教育においては、児童生徒の少人数化多様化が進み、教科に関す る専門的な指導法や適切な教材教具の活用などの継承発展が大きな課題とな っています。一方で、通常の学級で学ぶ視覚障害児童生徒は相対的に増加し ている傾向にあり、こうした児童生徒への盲学校と連携した支援が課題とな っています。 こうした状況を踏まえ、今期の研究ではとくに視覚障害児童生徒への算数 ・数学に関する指導及び実践報告に関するデータベースを整備するとともに、 その指導法やそれらにかかわる教材の活用に関するガイドブックの作成をめ ざした取組を行っています。 18年度において、地域で学ぶ視覚障害児童生徒への指導の実態と支援のニ ーズを把握するための調査を実施するとともに関連データの収集、整理に取 り組んできました。19年度は、集積したこれまでの関連データを活用して、 ニーズ調査から明らかになったとくに配慮を要する点に考慮した算数・数学 の指導法や教材教具の作成方法に関するガイドブックをまとめるべく取組を 進めているところです。 これらの研究成果は、研究報告書として刊行すると共に、データベースに ついては「視覚障害教育情報ネットワーク」を通じて公開する予定です。 ○概要はこちら→http://www.nise.go.jp/blog/2006/06/post_585.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■特別支援教育トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このコーナーでは特別支援教育に関連する最近のトピックスを紹介してい ます。また今回は、文部科学省から平成20年度特別支援教育関連概算要求の 概要が出されましたので、掲載します。 ●文部科学省から平成19年度学校基本調査速報が公表されました。 (文部科学省Webサイト) http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/07073002/index.htm 特別支援学校の学校数・在学者数などはこちらです。 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/07073002/005.htm ●厚生労働省において障害者雇用促進のための3つの研究会の報告書が公表 されました。 (厚生労働省Webサイト) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0807-3.html ●平成20年度特別支援教育関連概算要求の概要 (文部科学省初等中等教育局 特別支援教育課) はじめに 本年4月から改正学校教育法が施行され、特別支援教育が幼稚園、小学校、 中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において本格的に実施さ れています。 各学校では、以前から特別支援教育を推進するため、校内委員会の設置や 特別支援コーディネーターの指名などの体制を整えており、平成18年 9月に は、90%以上の小・中学校で、設置や指名が行われておあります。しかし、 幼稚園や高等学校の体制整備については、まだ課題がある等、今後、各学校 で校内体制の整備をさらに進め、障害のある幼児児童生徒への教育を今以上 に充実させる必要があります。こうしたなか、特別支援教育に直接関わる教 育関係者とともに、福祉、医療、労働等の関係機関との連携によるライフス テージに応じた支援体制や、障害のある子どものための個別支援ファイルの 作成・活用を検討している自治体等もあると聞いています。 このように、特別支援教育を推進・実践する機運が高まるなか、文部科学 省では平成20年度概算要求案を財務省に提出しました。今回は特別支援教育 に関連する要求内容について、その主な概要を紹介します。 ○要求要旨 発達障害を含む障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた支援 を行うため、幼稚園から高等学校における適切な支援のための外部専門家 の活用を含めた体制整備を推進するとともに、特別支援教育に関わる教員 配置の充実及びその専門性の向上を図ります。 ○発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業(新規) 1,386百万円 発達障害を含む全ての障害のある幼児児童生徒の支援のため、医師や大 学教員等の外部専門家による巡回指導、各種教員研修、厚生労働省との連 携による一貫した支援を行うモデル地域の指定などを実施することにより、 特別支援教育を総合的に推進します。 また、都道府県や推進地域に厚生労働関係者とも連携する連携協議会を 設置し、法律に明記された特別支援学校のセンター的機能の強化、学生支 援員の活用、地域住民へのきめ細やかな理解推進、学校における支援体制 の整備等を実施します。(特別支援教育体制推進事業の後継事業) ◇委嘱先 47都道府県 ○発達障害教育情報センター事業の委託(新規) 105百万円 発達障害児の教育的支援のために、外部専門家や専門機関、教材等の情 報提供を行うとともに、教員研修用講義コンテンツの配信、総合的調査、 先端技術や ICTを活用した支援機器の使用に関する研究等を実施します。 ○特別支援学校教員専門性向上事業(拡充) 48百万円 発達障害を含む多様な障害や重度・重複化に対応する適切な指導及び支 援の在り方、関係機関や地域の小・中学校等との連携の在り方などについ ての専門的な研修を実施します。 ◇委嘱先 6ブロック各3大学 ○PT、OT、ST等の外部専門家を活用した指導方法等の改善に関する実践研 究事業(新規) 75百万円 特別支援学校に在籍する障害のある児童生徒等に対してPT(理学療法士)、 OT(作業療法士)、ST(言語聴覚士)等の外部専門家を活用した指導方法 等の改善について実践研究を実施します。 ◇委嘱先 10都道府県 ○特別支援教育就学奨励費負担等 6,882百万円 特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級等への就学の特殊事情を鑑 み、障害のある児童生徒等の保護者の経済的負担を軽減するために必要な 援助を行い、就学を奨励します。 ○特別支援教育充実のための定数措置 2,128百万円 小・中学校におけるLD・ADHDの児童生徒に対する指導の充実を図るとと もに、特別支援学校におけるセンター的機能の充実を図るための定数措置 を行います。 ○その他 このほか、平成19年度から新たに開始された「発達障害早期総合支援モ デル事業」及び「高等学校における発達障害支援モデル事業」についても、 拡充して要求が行われています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■研修員だより ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このコーナーでは、研究所に研修に来られた方々からの寄稿やさまざまな 情報提供を行っていきます。今号は、平成18年度短期研修員(情緒障害教育 コース)の米田憲昭先生からお寄せ頂きました。 ● 「あれから1年」 短期研修が終了してもう1年余りが経ちました。毎日講義を受けた研修室。 実地研修で訪問し、感激して帰ってきた社会福祉法人けやきの郷。部屋から 見える海。毎朝あいさつをしてくれた筑波大学附属久里浜養護学校(現在は 特別支援学校ですね)の警備員さん。夜中にみんなで声をからして応援した サッカー日本代表W杯の試合。思い出すときりがありません。あれから1年。 この原稿依頼を受け、改めて自分はあれから何をしてきただろうか、何がで きただろうかと考えるよい機会になりました。しかし、どう考えても反省材 料ばかりが思い浮かんでしまいます。 私は現在、校内では、特別支援学級担任、特別支援教育コーディネーター という立場にあります。また、青森県独自の施策である「特別支援学級担任 等指導員」に今年度任命され、要請のあった学校に出向いて助言をする立場 になりました。一言で自分を評せば、「どれも中途半端」に尽きます。短期 研修終盤に「ここで研修したことのまず1割程度から現場に還元できるよう に」とおっしゃった笹森洋樹先生の言葉が身にしみる今日この頃です。 しかし、悲観しているわけではありません。特別支援教育の理想を久里浜 で学び、現場の厳しさも学びました。日本全国津々浦々に仲間ができました。 その仲間は一人一人が素晴らしい理想と実行力を持った愛すべき仲間達です。 特別支援教育は始まったばかりです。特別支援教育の理想が日本中に根ざす よう、今後もこの仲間達とともに地道に取り組んでいきたいと思っています。 青森県の夏は「ねぶた祭り」一色です。北国の短い夏を燃えるように駆け 抜けると、青森は一気に秋へと向かいます。まるで、短期研修を駆け抜けた 私たち研修員のようです。 最後になりますが、このような場を与えてくださった方々に心から感謝し ます。 青森県むつ市立奥内小学校 教諭 米田 憲昭 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■編集後記 読者には、特別支援教育に仕事として携わっておられる方も多いことと思 います。仕事もまた、日々の学びの連続体のなかで自己実現をはかったり生 き甲斐を感じたりする面もあり、今号で取り上げた生涯学習に通じるものだ と私は思います。なかでも、教育では、「子どもから学ぶ」とよくいいます。 この「子どもから学ぶ」は、私たちにとって仕事が「学び」だったり、「生 き甲斐」であることを上手く表現している言葉ではないでしょうか。もちろ ん子どもにとっては毎日の全てが学びです。私たちは、子どもが夢中になっ て遊びや学習に取り組んでいるような、「子どもが学んでいる姿」から学ぶ のだと思います。 子どもが大人になっても当たり前に自己の充実が図ることができるよう、 生涯学習を視野に入れた特別支援教育を今後も充実させていきたいと思いま す。このメールマガジンがその一助になれれば幸いです。 (第6号編集主幹 内田 俊行) ○「メールマガジン」へのご意見・ご感想をお寄せください。 こちら→
○研究所メールマガジンのバックナンバーは、こちら→ http://www.nise.go.jp/magazine/back.html ○研究所メールマガジンの利用については、こちら→ http://www.nise.go.jp/magazine/policy.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国立特別支援教育総合研究所メールマガジン 第6号 発行元 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所内 国立特別支援教育総合研究所メールマガジン編集部 メールアドレス:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━