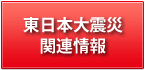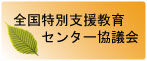ホーム > メールマガジンバックナンバー >
国立特別支援教育総合研究所メールマガジン 第10号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国立特別支援教育総合研究所メールマガジン 第10号 2008.1.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ NISE ━ 【目次】 ■新年のご挨拶 ■研究所からのお知らせ ■今月の特集 ■研究所の研究活動 ■特別支援教育トピックス ■研修員だより ■編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■新年のご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国立特別支援教育総合研究所メールマガジン愛読者の皆様、新年明けまし ておめでとうございます。 昨年は、特別支援教育元年といわれ、我が国の障害のある子どもの教育に とって歴史的な年でした。さらに、今年は、学習指導要領の改訂について審 議を行っている中教審が、今月にも答申を取りまとめることとしており、障 害のある子どもの教育内容の方向性が示される年になると思われます。 このような状況の中、当研究所といたしましては、国や地方公共団体と連 携・協力しつつ、研究活動を核として、研修事業及び教育相談事業などを一 体的に推進し、これまでにも増して、障害のある子ども一人一人の教育的ニ ーズに対応した教育の実現に貢献したいと考えております。 また、昨年4月に創刊しましたこのメールマガジンも、毎号順調に登録者 数を増やし、昨年11月には 1,000人の大台を超えることができました。今年 も特別支援教育に関する最新の情報を提供できるよう、更なる内容の充実を 図っていきたいと考えております。 どうぞ、本年もよろしくお願い申し上げます。 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 小田 豊 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■研究所からのお知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●平成19年度 国立特別支援教育総合研究所セミナーII参加のご案内 教育現場、教育行政、国際情勢の各立場からのリレー講演を通して、日本 における「特別支援教育の今」に迫りたいと考えています。 後半には本研究所の最新の研究成果について、ポスター発表やミニセッシ ョン、分科会を通して報告するとともに広く情報交換を行い、教員の特別支 援教育に関する専門性の充実・発展の一助にしたいと考えております。 多くの方々のご参加をお待ち申し上げております。 ◇2007年度テーマ 「特別支援教育の今」 ◇開催日程 平成20年 2月19日(火) ◇内容 講演 特別支援教育の今 -三者によるリレー講演- 『国の教育施策について』 講師 新谷 喜之 氏 (文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 特別支援教育企画官) 『地方の教育行政について』 講師 佐藤 紘昭 氏 (弘前大学教育学部 教授) 『国際情勢について』 講師 落合 俊郎 氏 (広島大学大学院教育学研究科 教授) ポスター発表及び研究成果発表 分科会 第1分科会「特別支援教育が本当につなぐもの -教科教育に焦点を当てて-」 第2分科会「発達障害のある子どもの早期からの支援 -現在とこれから-」 第3分科会「知的障害教育におけるこれからの職業教育、進路指導の 在り方 -キャリア教育の視点から-」 ◇申し込み期間 平成20年 1月11日(金)~ 1月17日(木) ○セミナーIIの詳細・申し込みはこちら→ http://www.nise.go.jp/blog/2007/09/19-14.html ◇会場 国立オリンピック記念青少年総合センター (東京都渋谷区代々木神園町3-1) ◇定員 700名 ◇問い合わせ 総務部企画調整課企画係 TEL 046-839-6806(又は6808) FAX 046-839-6919 E-mailセミナーIは、募集受け付け期間を終了しました。多数のご応募を頂き ありがとうございました。 ●NISE新刊情報 研究所刊行物の新刊を下記のとおりお知らせします。なお、各報告書等は 各関係機関に送付する他、研究所Webに掲載いたします。 教育・研究資料 『Journal of Special Education in the Asia Pacific (JSEAP) Vol.3 December,2007』 ○こちら→ http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub_d/d-262.html 『NISE Newsletter for Special Needs Education in Asia-Pacific No. 27』 ○こちら→ http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub_d/d-261/d-261.pdf ●NISE市販書籍情報 本研究所では、障害のある子どもを支援する立場にある方々の様々なニー ズにお応えするため、下記ガイドブック・マニュアル等を書店・出版社にて 市販しております。皆様の支援の充実にぜひお役立てください。 『発達障害のある学生支援ケースブック-支援の実際とポイント-』 定価1,575円(税込) ジアース教育新社 ISBN978-4-921124-76-2 発売年月 平成19年 9月 ○こちら→http://www.kyoikushinsha.co.jp/books/76.html お問い合わせ先 ジアース教育新社 TEL 03-5282-7183(販売部) また、上記の刊行物は、本研究所内障害児教育財団でも取り扱っています。 ○こちら→ TEL 046-839-6888、FAX 046-839-6919 ●日本・マレーシア経済連携研修第2期研修実施報告 本研究所では、「日本・マレーシア経済連携協定(平成17年12月)」に基 づき、マレーシアにおける国立特別支援教育研究所設立への支援を行うため に、JICA(独立行政法人国際協力機構)と協力して、マレーシアから、各障 害種別担当の研修員の受け入れを行っています。 平成19年度は、第2期研修として、平成19年11月 5日(月)~30日(金) の日程で3名の研修員を受け入れました。研修では、日本の特別支援教育制 度などに関する講義受講、特別支援学校や小学校の特別支援学級、通所施設 などへの見学、などの活動に取り組んでいただきました。 ○概要については、こちらをご参照ください。 →http://www.nise.go.jp/blog/nichima.html ●NISE 障害者週間関連行事報告 先月号までご案内しました、NISE障害者週間2007の三つの行事は、おかげ をもちまして 、無事すべて終了いたしました。 学校関係者のみならず地域の方々など一般の方々にも多数ご来場頂きまし た。お忙しい中、お越しいただきました皆様にはこの場をお借りしてお礼申 し上げます。 第27回アジア・太平洋特別支援教育国際セミナー/パネル展 2007年度開催テーマに基いた各国の貴重な報告と活発な意見交換が行わ れました。この内容については、「Final Report」として刊行し、各関係 機関に送付する他、参加14カ国代表者が更新した最新の各国基礎情報及び セミナーの概要を研究所Webに掲載しています。 ○各国基礎情報(英語版)については、こちらをご参照ください。 →http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub_d/d-262/d-262_3.pdf ○セミナー概要については、こちらをご参照ください。 →http://www.nise.go.jp/blog/2007/12/post-718.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■今月の特集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●平成20年度の研修事業について ◇平成20年度研修事業の改善の視点 松村 勘由(教育研修情報部 総括研究員) 当研究所では、平成20年度、学校教育法の一部改正の趣旨に対応した各 研修事業の見直しを行い特別支援教育専門研修及び各種研修等について、 次のような観点で改善を行います。 (1)特別支援教育は、特別支援学校のみならず、特別な支援を必要とす る幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものであること から、特に小・中学校における特別支援教育の充実を観点に、また、発達 障害のある幼児児童生徒に対する教育の充実を観点に改善を行います。 (2)特別支援学校制度創設の趣旨を踏まえ、特別支援学校教員の資質と して必要とされる障害に関わる総合性と専門性の両側面に対応して、各コ ース編成及びプログラム構成を改善します。 (3)喫緊課題である発達障害教育への対応を図るため、新たに、発達障 害教育指導者研究協議会を創設することとしました。 ◇平成20年度研修事業の概要 (総務部研修情報課) 平成20年度に実施を計画している主な研修事業は、以下に示す通りです。 各研修の受講者は、国立大学の附属学校の教員については当該国立大学長、 公立学校の教員及び教育委員会、特別支援教育センター等の教育職員につ いては当該都道府県又は当該政令指定都市の教育委員会教育長、私立学校 の教員については当該都道府県知事の推薦を受け、それに基づき理事長が 決定した者としています。 <<特別支援教育研究研修員制度>> 本年度より開始された特別支援教育研究研修員制度は、平成20年度も引 き続き実施します。 <<特別支援教育専門研修>>(推薦期限:平成20年 1月31日(木)) 障害のある幼児指導生徒の教育を担当する教育職員に対し、専門的知識 及び技術を深めさせるなど必要な研修を行い、その指導力の向上を図り、 今後の都道府県等における指導者としての資質を高めることを目的として います。 [第一期:情緒障害・言語障害・発達障害教育コース] 平成20年 5月12日~ 7月11日、80名 [第二期:知的障害・肢体不自由・病弱教育コース] 平成20年 9月 3日~11月11日、80名 [第三期:視覚障害・聴覚障害教育コース] 平成21年 1月 7日~ 3月12日、40名 なお、選択履修領域として、「情緒障害・言語障害・発達障害教育コー ス」では、情緒障害・自閉症教育専修プログラム、言語障害教育専修プロ グラム、発達障害教育専修プログラムを、「知的障害・肢体不自由・病弱 教育コース」では、知的障害教育専修プログラム、肢体不自由専修プログ ラム、病弱教育専修プログラムを、視覚障害・聴覚障害教育コースでは、 「視覚障害専修プログラム、聴覚障害専修プログラム」を構成し、それぞ れの障害に対応したより深い内容について研修を進めるようになっていま す。また、知的障害・肢体不自由・病弱教育コースでは、知的障害を伴う 自閉症教育、重複障害教育、情報手段活用のそれぞれの内容を重点的に研 修する重点選択プログラムも併せて編成しています。 <<各種研修>> その他、教育現場の喫緊の課題の解決を図るための指導者研修として、 「発達障害教育指導者研究協議会」政策課題の推進を図るための指導者研 修として、「特別支援教育コーディネーター指導者研究協議会」「交流及 び共同学習推進指導者研究協議会」また、教職員の指導力向上を図るため の指導者研修として「特別支援学校寄宿舎指導実践指導者研究協議会」の 実施を計画しています。 ○平成20度国立特別支援教育総合研究所研修計画一覧は こちら→http://www.nise.go.jp/blog/kenshuichiran.html ○平成20度特別支援教育専門研修実施要項は こちら→http://www.nise.go.jp/blog/2007/11/20-3.html ○研修事業のお問い合わせは こちら→総務部研修情報課研修係(佐藤、阿部、伊與田) TEL 046-839-6827・6828・6895 E-mail
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■研究所の研究活動 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このコーナーでは、研究所の研究活動について紹介します。 今回は、現在も継続中の課題別研究2件を紹介します。 ●課題別研究「聾学校におけるコミュニケーション手段に関する研究-手話 を用いた指導法と教材の検討を中心に-」(平成18年度~19年度)について 研究代表者 小田 侯朗 (教育支援研究部・総括研究員) 本研究は平成16年度から平成17年度の2年間で行われた課題別研究「聾学 校におけるコミュニケーション手段に関する研究-教職員の手話活用能力の 向上とこれを用いた指導法の検討-」を引き継ぐ研究です。近年の聴覚障害 教育では児童生徒それぞれの特徴やニーズに合わせて多様なコミュニケーシ ョン手段の活用が大切な課題となっています。その中でも手話の活用につい ては様々な面での検討や研究が求められているところです。本研究では手話 を活用した効果的な授業やその他の活動の検討に加え、手話を活用した授業 に必要な教材について調査や検討にも焦点を当てました。これまでの2年間 で、聾学校での多様なコミュニケーション手段活用の実態調査、聾学校での 言語力やコミュニケーション力の評価法に関する調査、手話を中心とした教 材の活用状況の調査などを行ってきました。また各地の聴覚障害者情報提供 施設やライブラリーへの調査も進め、教材の活用のための聾学校と聴覚障害 者情報提供施設の連携についても調査を進めました。授業に関しては、日本 語の読み書きと手話活用を関連させた取組や聴者教員と聴覚障害者教員のチ ームティーチングの実践等について検討を進めてきました。 これらの研究の成果は平成20年春に課題別研究報告書として刊行を予定し ております。 ○研究の概要はこちら→ http://www.nise.go.jp/blog/2005/03/post-582.html ●課題別研究「通常の学級で学習する障害のある子どもの日本語の音韻・音 節の認識に関する研究-書き言葉において間違えやすい日本語の特殊音節の 特性の分析と指導方法の開発-」(平成18年度~19年度)について 研究代表者 藤本 裕人(企画部・総括研究員) 現在、発達障害児等の教育において、日本語の特殊音節と言われる促音や 拗音などの「話し言葉」を「書き言葉」にする際に、誤りが起きる場合があ ることが指摘されています。しかしながら、発達障害児等の学習場面を踏ま え、「聴覚」を通して得られる「母音と子音」で構成される日本語の音韻の 特性と「書き言葉」の関係について、その関係を明らかにした研究はあまり 取り組まれていません。本研究は、児童が、書字において誤りやすい日本語 の音韻・音節の特性に着目し、授業を行う教員の音声を分析する方法で、 「聴覚的」な認知に着目した「正しい書き言葉」の指導方法の糸口を探って います。 ○研究の概要はこちら→ http://www.nise.go.jp/blog/2006/06/post-590.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■特別支援教育トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このコーナーでは特別支援教育に関連する最近のトピックスを紹介してい ます。 ●平成19年度辻村賞について 財団法人障害児教育財団 当財団では、我が国の特別支援教育の第一人者として、その振興発展のた めに尽力された故辻村泰男先生のご遺徳を永く記念するため、特別支援教育 の領域において特に顕著な功績のあった方や特に優秀な研究を行った方に対 して、「辻村賞」を授与しております。 第21回(平成19年度)の辻村賞は、特定非営利活動法人日本肢体不自由教 育研究会理事長の村田茂様が受賞され、平成19年12月14日に、当財団の鈴木 理事長から、賞状と記念品が授与されました。 ●平成20年度特別支援教育関係予算案について 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 平成19年12月24日に平成20年度政府予算案が閣議決定されました。特別支 援教育関係予算については、発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業や 発達障害教育情報センター事業、特別支援教育の充実のための教職員定数の 改善など、昨今の厳しい財政状況の中、大幅な予算増が認められました。 特別支援教育関係予算案の概要については下記のとおりです。 1.発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業(新規) 503,052千円(新規) 発達障害を含む全ての障害のある幼児児童生徒への支援のため、外部専 門家による巡回指導、各種教員研修、厚生労働省との連携による一貫した支 援を行うモデル地域の指定などを実施し、特別支援教育を総合的に推進する。 (特別支援教育体制推進事業の後継事業 19年度予算 193,857千円) (委嘱先:47都道府県) 2.発達障害教育情報センター(新規) 32,552千円(新規) 発達障害のある幼児児童生徒への教育的支援のため、外部専門家や専門機 関、教材等の情報提供、教員研修用講義コンテンツの配信、総合的調査、先 端技術やICTを活用した支援機器の使用に関する研究等を実施する。(独 立行政法人国立特別支援教育総合研究所に設置) 3.発達障害早期総合支援モデル事業(拡充) 122,964千円(50,807千円) 発達障害のある幼児及びその保護者を支援するため、幼稚園や保育所にお ける発達障害の早期発見の方法の開発や、早期支援を行うモデル地域を指定 し、早期からの総合的な支援の在り方について実践的な研究を実施する。 (指定地域数:20地域程度) 4.高等学校における発達障害支援モデル事業 51,071千円(21,121千円) 発達障害のある高校生の支援のため、モデル校において、ソーシャルスキ ルの指導や授業方法・教育課程上の工夫、就労支援等について実践的な研究 を実施する。(指定校数:20校程度) 5.特別支援学校等の指導充実事業(拡充) 100,086千円(72,085千円) 特別支援学校等の教育課程の編成、障害のある生徒の就労支援及びPT( 理学療法士)、OT(作業療法士)、ST(言語聴覚士)等の外部専門家を 活用した指導方法等の改善等について実践研究を実施する。 (指定校数:18校、指定地域数:17都道府県) 6.特別支援教育就学奨励費負担等 6,850,371千円(6,664,652千円) 特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級等への就学の特殊事情をかん がみ、障害のある児童生徒等の保護者等の経済的負担を軽減するために必要 な援助を行い、就学を奨励する。 【初等中等教育局財務課に計上】 7.特別支援教育の充実のための定数改善(小中学校の通級による指導) 171人 LD、ADHD等発達障害のある児童生徒に対する通級による指導の充実 のための定数改善を行う。 【平成20年度地方財政措置予定】 8.特別支援教育支援員(小・中学校) 約360億円 発達障害を含む様々な障害のある児童生徒に対する学校生活上の介助や学 習活動上の支援を行う「特別支援教育支援員」の配置に必要となる経費につ いて、地方財政措置を拡充予定。 20年度措置予定額 支援員 30,000人相当 約360億円 (19年度措 置 額 支援員 21,000人相当 約250億円) ●季刊特別支援教育28号の発行について他 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 文部科学省発行の「季刊特別支援教育28号」が平成19年12月25日に発行さ れました。特集は「特別支援教育支援員の活用」となっています。 また、文部科学省が全国特別支援教育推進連盟に委嘱して作成した「交流 及び共同学習事例集」が平成19年10月より市販されています。 ○「交流及び共同学習事例集」についての詳細はこちら→ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/003.htm ●文部科学省庁舎移転について 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 平成16年 1月より庁舎立替に伴い、丸の内の仮庁舎で業務を行っておりまし たが、本年1月より、霞が関の中央合同庁舎第7号館に移転しました。特別 支援教育課は東館の8階です。所在地・電話番号等は下記のとおり(所在地 は仮庁舎への移転前と同じ)です。 〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号 代表番号 03-5253-4111(代表) IP電話番号 050-3772-4111(代表) ※特別支援教育課各係の内線番号は発達障害支援係を除き変更はありません。 発達障害支援係 仮庁舎 3190 → 新庁舎 3254 ○地図等につきましては、文部科学省のHPをご参照ください→ http://www.mext.go.jp/submenu/07120607.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■研修員だより ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このコーナーでは、研究所に研修に来られた方々からの寄稿やさまざまな 情報提供を行っていきます。今号は、平成16年度情報手段活用による教育的 支援指導者研修修了の木村先生からお寄せ頂きました。 ●校内研究グループのリーダーとして 木村 政秀(滋賀大学教育学部附属特別支援学校) 平成16年に2週間の研修を受講させていただきました滋賀の木村と申しま す。本校では、平成15年度より本校教員の教育研究のニーズに基づき五つの 研究グループを立ち上げ、日頃の教育活動と連動させながら研究活動を展開 してきました。現在、私は「情報活用能力育成グループ」のリーダーをつと めており、3年前に特総研で学んだことが活かされています。 本研究グループでは、障害のある児童生徒の情報活用能力の育成に加え、 それを支援する教員の情報活用能力の育成に焦点を当てた研究を行ってきま した。今年度の研究の柱は、 (1)アシスティブ・テクノロジーを適用した教 材作りや学校支援 (2)情報モラル教材の開発 (3)地域の教員支援システム 開発のための実践と研究です。 研究成果の一部は、日本特殊教育学会の大会や日本教育情報学会の年会で 発表を行いました。今後も、研究を発展させていきたいと考えています。ど うぞよろしくお願い致します。 ○滋賀大学教育学部附属特別支援学校 Webサイトはこちら→http://fyw.sue.shiga-u.ac.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■編集後記 平成20年を迎え、最初のメールマガジン第10号をお届けします。現在、編 集委員会では今後のメールマガジンのあり方を検討しております。これまで で役に立った情報や、今後掲載してほしい情報などございましたら、記名で も無記名でも結構ですので、下記のメールアドレスまでお寄せ下さいますと ありがたく存じます。それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 (第10号編集主幹 渡邉 正裕) ○「メールマガジン」へのご意見・ご感想をお寄せください。 こちら→
○研究所メールマガジンのバックナンバーは、こちら→ http://www.nise.go.jp/magazine/back.html ○研究所メールマガジンの利用については、こちら→ http://www.nise.go.jp/magazine/policy.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国立特別支援教育総合研究所メールマガジン 第10号 発行元 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所内 国立特別支援教育総合研究所メールマガジン編集部 メールアドレス:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━