| II 「特殊教育」および「特別な教育的ニーズのある子ども」の定義と特殊教育の現状について |
 |
| 1.ウォーノック報告 |
「特別な教育的ニーズ」という概念が使用されるようになったのは、1978年にマリー・ウォーノック(Mary Warnock)を議長とする障害児・者の教育調査委員会の報告書が提出された時からである。
この報告を受けて、政府は1981年教育法で、特殊教育の対象となる子どもを、「障害」のある子どもとして捉えずに、「特別な教育的ニーズ」のある子どもとした。
1981年教育法以前の特殊教育の制度は、1944年教育法によるものであり、盲、弱視、聾、難聴、虚弱、糖尿、教育的遅滞、てんかん、不適応、肢体不自由、言語障害の11の障害カテゴリーが使われてきた(1953年に糖尿が虚弱に合併された)。
ウォーノック報告では、(1)医学的視点からの障害のカテゴリーは、子どもが必要としている教育と対応していない、(2)障害を子どもの要因としてのみ捉えている、(3)障害のあるなしは、明確に区分されるのもでなく、連続的なものである等の点が批判され、従来の障害カテゴリーの代わりに、「特別な教育的ニーズ」を用いることが提案された。
|
| 2.「特別な教育的ニーズ」の概念 |
この「特別な教育的ニーズ」は、1981年教育法によって、診断された障害についてではなく、教育的援助について言及する教育学的な概念とされた。そしてこの概念は、学習における困難さ(a learning difficulty)と特別な教育的手だて(special educational provision)で説明された。その概念規定は、現在でも大きな変化はなく、1996年教育法では以下のように記述されている。
(1)「特別な教育約手だて」を必要とするほどに、「学習における困難さ」があるならば、その子どもは、「特別な教育的ニーズ」を有するとする。
(2)「学習における困難さ」とは、
a.子どもが、同年齢の子どもと比べて、学習において有意に困難さを有する場合、
b.子どもが、学区又は学校にある施設設備を充分に利用できない困難さを有する場合、
c.5歳以下で、上記の状態に当てはまる場合、あるいは特別な教育的手だてがなければ、上記の状態になる可能性のある場合である。
(3)「特別な教育的手だて」とは、
a.2歳以上は、同年齢の子どもに提供される教育に、さらに追加された教育、あるいはその教育とは異なる教育的手だて
b.2歳未満は、全ての教育的手だてである。
この「特別な教育的ニーズ」の概念規定において、第一言語が英語でない家庭の子どもという理由で、学習において困難さを示す場合は、「学習における困難さ」には含めないとされている。
|
| 3.曖昧な概念規定 |
学習に遅れを生じさせる原因は、数多くあげられ、どの原因による学習の困難さを、「特別な教育的ニーズ」とするかは、その境界が明確でなく、曖昧さがある。子どもを取り巻く家庭、文化及び地域社会の環境を考慮する必要があり、そのため、基準次第で、対象となる子ども数やその実態は大きく異なってくる。
「特別な教育的ニーズ」のある子どもには、障害のある子どもだけでなく、病気で入院している子どもや不登校の子ども、いじめを受けている子どもが含まれる場合がある。しかしながら、それらの子どもがすべて含まれるわけでなく、それらの行動特性の原因に、何らかの学習における遅れが推測される場合である。不登枚が続けば、当然学習における困難さが生じ、その困難さが不登校の要因の一つになることも推測される。
このように、特別な教育的ニーズの判定は、きわめて多様であり、困難さを伴う。教員養成や研修においては、明らかな障害があれば、その対応に関しては比較的容易である。しかし、それ以外の要因等による特別な教育的ニーズを見極めるのは困難さが伴うということである。そのため、すべての教員への特別な教育的ニーズについて研修が必要であり、全員が研修を受けるようにと考えられているが、予算上の制約も大きい。
|
| 4.障害と特別な教育的ニーズ |
法律上は、ノンカテゴリーを前提とし、「特別な教育的ニーズ」を基本概念として、その教育的手だてが実施されている。しかしながら、特別学校(特に障害種別の団体の私立学校)においては、障害種別の概念を利用している場合がある。政府は、「特別な教育的ニーズで新たな枠組みをつくったが、これまでの障害種別の対応も維持しながら教育を提供している」としている。
|
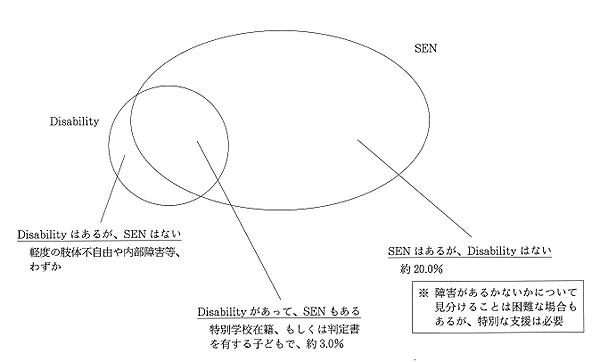
図1. 障害とSENの概念の関係図 |
| |
障害と特別な教育的ニーズの概念・範囲については、図1に示すように整理できる。2つの概念が重なる部分とそうでない部分がある。特別な教育的ニーズという概念の普及により、特別な教育の対象児童生徒は拡大した。
特別な教育的ニーズという概念の普及で、それらの子どもに対する通常学校の教師の理解は、どのように変化したのかについては、特別な子どもの教育を担当することに、神経質になっていたり、恐れを抱いている教員もいる。一方、非常に理解が進み、うまくインクルージョン教育を実現している学校もある。しかし、社会全体の障害者理解については多くの課題がある。
また、医療や福祉においては、特別な教育的ニーズという概念ではなく、ニーズのある子ども(Children in Needs)などが使われていて、共通する概念でない。それぞれの概念が領域で異なっている。
|
| 5.特殊教育の現状 |
英国のイングランドにおける特別な教育的ニーズのある子どもの教育の現状(2000年1月)を、表2に示した。特殊教育諸学校にあたる特別学校(special school)に在籍する子どもは96,600人であり、全子ども数の1.2%であった。この数値は1994年の1.26%と大きな変化がない。「判定書」を有する子どもの割合は、3.0%であり、1994年の2.5%より増加している。
|
表2.英国の特別な教育的ニーズの現状(2000)
( )は1994のデータ;−はデー夕なし
| 特別学校在籍者と判定書保有者の割合 |
| 特別学校在籍者割合 |
1.2 (1.3) % |
| 判定書保有者割合 |
3.0 (2.5) % |
| 特別な教育的ニーズのある子どもの割合 |
| (1)初等教育学校 |
22 ( - ) % |
| (2)中等教育学校 |
20 ( - ) % |
|
| |
「判定書」とは、子どもの特別な教育的ニーズとそれに対応する手だてを具体的に成文化した書類である。この「判定書」は、保護者とそれぞれの専門家の意見と評価(assessment)を基本として作成される。
「判定書」には、専門家による評価で得られた特別な教育的ニーズとそのニーズに対応するために学校で行われる教育的手だてや言語療法等のセラピーなどが示されている。この「判定書」を有する子どもで、その60%は通常の学校で、40%は特別学校で教育を受けている。
さらに特別な教育的ニーズのある子どもの割合については、初等教育学校で平均22%、中等教育学校で平均20%であった。この数値は、ウォーノック報告書の推定値20%に近い数値である。いくつかの学校では、この割合が50%を越える場合もある。
大まかな概要は以上であり、日本と比較すると、英国の特徴は、(1)インクルージョンを方針としつつ、特別学校に就学する子ども(1.2%)が日本(0.4%;'99)より多い、(2)通常学校の約20%の子どもに特別な教育的ニーズがあり、それに応じて支援が実施されている、の2点と考えられる。
|
| (石塚 謙二・徳永 豊) |
| |
| 資料 |
・Department for Education and Science:Special Educational Needs: Report of the Committee of Inquiry into the Education of Handicapped Children and Young People.London: HMSO,1978.
・Department for Education and Employment: Statistical Bulletin January 2000 Special Educational Needs in England.
http://www.dfee.gov.uk/sen/p-r-stat.htm
・DfEE: Statistical Bulletin January 2000 Special Educational Needs in England (統計表) |





