| 4.学校事例2 Cleves Primary School |
| 1)概要 |
ロンドン・ニューハム地区にあるクリーブス初等教育学校は、住宅地にある学校で、複数の言語で書かれている看板に、地域の特色が読みとれる。1992年9月開校で、420人定員の学校である。1984年に、ニューハム地区の議会が、インクルージョンを決議し、それから取り組みを正式に開始した。
この地域の特性として、多民族、多文化の人々が住み、避難民も多い。65%の子どもがアジア・アフリカ出身で、家庭での言語が英語でなく、ウルド語、ベンガル語等である。
家庭の社会経済的な状況は、悪い方で、無料給食率55%(イングランド平均19%)であり、低所得の家庭が多い。社会サービス受給者が多く、持ち家率も低い。借家、アパート、社会保障住宅で暮らしている。住む家が見つかると移動するため、子どもの転校が多い。卒業生の43%が、中途で転校してきた子どもである。
|
| 2)在籍幼児児童 |
表3に示すように、学校全体は、420人の定員と104人のパートタイム(午前と午後)で、在籍524名からなる。各学年が60人定員のため、7クラスで420人となる。内訳は、レセプションクラスが1クラス60人で、小学部が6クラス360人である(小学部は、第1・2学年、第3・4学年、第5・6学年の3グループに分けられ、各グループが120人である)。
|
表3.在籍する子どもの数
| ナーサリー |
104* |
| レセプション |
60 |
| 1・2学年 |
120 |
| 3・4学年 |
120 |
| 5・6学年 |
120 |
| 合計 |
524 |
*午前と午後が各52名で、計104名となる。
|
障害のある子どもについては、36人の特別な教育的ニーズ(重度・重複の学習困難)の枠を設置している。学習困難の子どもの粋が24名で、情緒・行動困難の子どもの枠が12名であり、現在33名が在籍している。1999年学校全体で、45名(8.6%)の子どもが「判定書」を有し、129名(24.7%)の子どもが特別な教育的ニーズが必要であると登録され、1から4段階のいずれかの段階となっている。
|
| 3)子どもの指導にあたるスタッフ |
校長が全体の管理・運営の責任者であり、教頭は校長の補佐とSENコーディネーターの役割を併任していた。SENコーディネーターは、特別なニーズのある子どもの教育の調整・実行の責任者である。他のスタッフについては、4つのグループに分かれ、表4にその人数を示した。
|
表4.各グループとスタッフ数
| |
EarlyYears |
Key Stage 1 |
Key Stage 2 |
Key Stage 3 |
| 子 ど も 数 |
164名* |
120名 |
120名 |
120名 |
| 教 師 |
5名 |
5名 |
6名 |
6名 |
| 保 育 士 |
5名 |
2名 |
2名 |
3名 |
| ア シ ス タ ン ト |
5名 |
1名 |
7名 |
2名 |
| 計 |
15名 |
8名 |
15名 |
11名 |
|
*レセプションの幼児60名と半日対応の幼児104名を加算した数
|
(1)幼稚部(ナーサリー&レセプション)
表4に示すように、164名に対して、スタッフ15名である。教師は5名で、チームリーダ、算数担当、カリキュラムサポート、美術担当等の教師である。保母は5人、アシスタントが5人であった。
(2)ステージ1(第1・第2学年)
子どもが120名に対して、スタッフが8名であり、最小スタッフ数であった。特別な教育的ニーズのある子どもが少ないグループである。教師が5人(うち非常勤1人で、そのひとりのポストを週に3日の教師、週に2日の教師で対応していた)で、保育士が2人、アシスタントが1名であった。
(3)ステージ2A(第3・第4学年)
子どもが120名に対して、スタッフは15名(教師6名、保育士2名、アシスタント7名)であった。
(4)ステージ2B(第5・第6学年)
子どもが120名に対して、スタッフ11名(教師6名、保育士3名、アシスタント2名)であった。
|
| 4)各スタッフの責任と役割について |
校長は、学校運営全体の責任者であり、教頭は、校長を補助する役割に加え、SENコーディネーターの役割も兼ねていた。教師は、実際の指導計画を作成し、その実行の責任者である。また、保育土やアシスタントの調整の重要な役割である。保育士は、子どもの日常生活の指導であり、アシスタントは、教師の補助的役割であった。それぞれのスタッフがチームを組んで、複数の子どもに対応していた。
|
| 5)支援サービスと予算について |
教室がオープンスペースで、多様な学習グループが構成できる。教室は比較的新しく、4つの部屋と特別室がある(図2)。教師は教科担当でなく、それぞれに教科を持ち回りで教えている。2学年の子どもを、複数の教師チームで対応している。
|
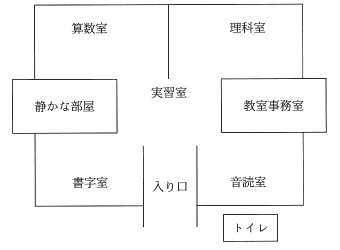
図2.オープンスペースの教室 Key Stage 2Bの部屋で、
120人の子どもが学習をするスペース
|
学校がその方針として大切にしていることは、(1)人材、教材が、豊富で適切な状況をつくること、(2)カリキュラムを工夫して、個々の子どもの状況に合わせること、(3)適切なアセスメントを実施し、記録を残し、整理することであった。
基本的には、学校区の子どもを受け入れている。学区外からも、その子どもの特別な教育的ニーズに従って、区の委員会で協議が行われ、親の希望を含めて検討された結果、この学校が適切とされると入学となる。現在4名の子どもが学区外から在籍している(地方教育局の情報)。
表5に示すように、地方教育局からの学習支援教師による巡回指導があり、多様なサービスが、豊富に提供されていた。4つのグループに、必要性に応じて、スタッフとして参加、助言している。
|
表5.地方教育局からの支援サービス
| サ ー ビ ス |
頻度 |
| 自閉症等助言チーム |
週に 1日 |
| 学習支援サービス |
週に 4.5日 |
| 聾・難聴支援サービス |
週に 0.5日 |
| 視覚障害支援サービス |
週に 3日 |
| 就学前支援サービス* |
週に 1日 |
| 言語・コミュニケーション支援サービス |
週に 2日 |
| 理学療法士* |
週に 3日 |
|
|
|
学校の年間予算は、日本円に換算して、2億4000万円(1.2ミリオンポンド)であり、子どもひとりあたり、46万円(他の地域の通常の教育費を平均30万円とすると1.5倍)であった。
|
| 6)その他 |
以下に、校長への質問とその回答を紹介する。
第1に、この学校には、強度行動障害の子どもが見受けられないが、多動や落ち着きがない子どもがいないのかという質問に対しては、学校がうまく対応し、行動が落ち着いているので、そのような印象をもったのではないか。8人の子どもが、チャレンジング・チルドレン(多動で、衝動的な子ども)である。今日(学校見学時)は、目立つ子どものうち、ひとりがプール、ひとりは外出していたため、印象が薄かったのではないだろうかということであった。
第2に、学校が受け入れきれない子どもはいるのか、あるいは過去にいたかという質問に対しては、神経症的な子どもが2名いた。彼らを学校に受け入れることは難しかった。病的性格者で治療的な対応が必要であった。物を投げたり、他の子どもに危険な行動をとった。地方教育局の行動支援サービスを部分的に活用して、在宅で対応している。また、施設からの支援サービスを家庭が受けているケースがあるということであった。
なお、このような措置に対して、保護者が満足できない場合は、裁定委員会(Tribunal)と呼ばれる機関があり、学校に対する保護者の不服申し立ての手続きがある。
第3に、障害のある子どもに集団指導で対応するのか、個別指導で対応するのかという質問に対しては、校長は、子どもの自己尊厳観を大切にしたいので、グループの中で、個別に対応し、同じ活動でも、課題を違えて活動を組む。取り出しの指導は、少なくするように努力している。理学療法や言語療法など必要な場合は、個別で指導していると述べていた。
第4に、アシスタントと教師の違いは何かという質問については、教師が計画を立てて、実行の責任者となり、アシスタントに指示を出す。個別の指導計画に応じて、課題に取り組んでいる。6週間ごとにまとめを行い、課題が何かを明確にし、スタッフで共通理解していくようにしているということである。
第5に、OFSTEDによる学校評価の報告書におけるSEN教育の評価の課題は何かという質問に対し、校長は、評価のチームが、この学校が抱えている課題や文化を理解できるかどうか難しい問題であり、的確な評価かどうかは疑わしい。報告書は、ステージ2の到達度評価が低いという厳しい指摘であったが、ここでの教育については、自信を持っている。
この学校は、日本の幼稚園、小学校の段階の学校であり、学校としての教育水準は低い。第5・6年生で、ジュウタンの上で座り込みながらの授業で、参加しやすい形態であることには違いない。社会的状況からみても、水準の高い教育を求めても、実現が難しい地域である。
文化・社会的状況を考慮しつつ、教室構造、教育の形態、教育の内容を、緩やかに、かつ、柔軟にすることで、他民族の子ども、特別な教育的ニーズのある子どもでも受け入れていた。
|
| (徳永 豊・川住 隆一) |
| |
| 資料 |
|
・Learning and Inclusion; The Cleves School Experience, Danid Fulton Publishers 1999.
・School Information; Cleves Primary School.2000
・Inspection Report
|





