| III.調査結果 |
 |
| 1.公教育省 |
公教育省では、文化交流部長Giuseppe MARTINEZ氏を表敬訪問し、文化交流部Aldo BOVE氏、および視学官Dea PELEEGRINI氏とLuciano SERRA女史と懇談し、イタリアにおける障害児教育の状況について説明を受けた。
イタリアの障害児教育の現状として、1992年に制定された法律104号「障害者の援助、社会的統合および諸権利に関する基本法」の精神が基本となっており、どのような障害のある児童であっても通常の学級において適切な教育を受ける権利が保障されていて、現在もその整備が進められているという説明があった。義務教育段階では障害のある児童生徒はほとんどが通常の学級に在籍するようになっており、近年では、高等教育での対応にも力を入れ、法律104号の完全実施に努力していることが強調された。ハード(施設)面の整備は進みつつあり、ソフト(運営)面での充実が今後の課題であること、指導の充実を図るために支援教師(Insegnanti di sostegno)の養成に努力しているという説明を受けた。
以下に懇談および資料から得た情報を基にイタリアの教育の現状について整理する。
|
| 1)イタリアの教育制度 |
イタリア公教育省の資料によるとイタリアの教育制度は、2000年9月から新制度が導入され、義務教育を8年から9年に拡張した。詳細は図1に示したとおりである。
|
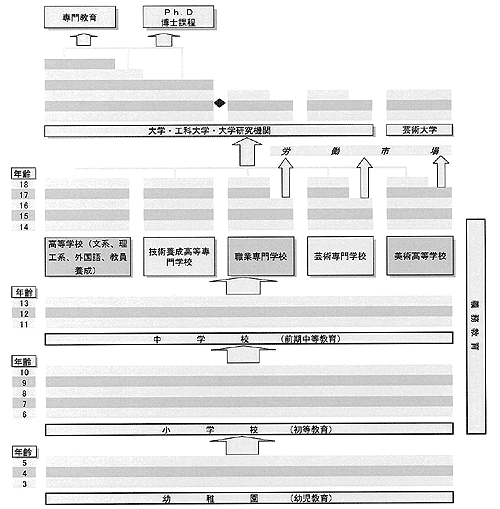
図1.2000年度から実施の新教育制度
|
<就学前教育>
0歳から3歳までは保育園が用意されている。公教育の管轄は幼稚園からであり、幼稚園は3歳から5歳までの3年課程である。かならずしも多くの幼児が3歳から幼稚園に通っているわけではないが、新制度では、年長児にあたる5歳児の段階から義務教育となる。
<小学校・中学校>
旧制度では小学校5年間(6〜10歳)、中学校3年間の8年が義務教育であった。新制度では小学校6年間、中学校3年間となり、中学校までが義務教育となる。イタリアでは、義務教育段階ではほとんどの児童生徒が公立学校に通学している。義務教育段階では、公教育省によって定められた指導要領に従って教育することになっており、均質な教育が行われるシステムになっている。しかし、施設・設備に差があったり、学校内の組織も異なっていたりして、実際には学校や地域での違いがあるのが実態である。義務教育段階での教師は、ほとんどが女性である(小学校で98%)。
初等教育段階は5年間で行われるが、前期課程(2年間)と後期課程(3年間)の二つの課程に分かれている。前期から後期への進級に際しては、進級試験があり、第5学年終了時にも国語と算数の2教科に関して修了試験が実施される。以前は筆記試験と口述試験が行われ厳しく評価されていたが、インクルーシブな教育が進展する中で口述試験を中心に緩やかになってきている。
中学校でも3年次に卒業資格試験が実施されており、留年する生徒も出ている。
<高等学校>
イタリアでは中学校卒業資格を取得すれば希望する高等学校に入学できる。高等学校は、文系高校・理系高校・職業学校などに細分化されている。中学卒業者のほぼ全員が高等学校に入学するが、留年および退学者が多いのが特徴である。旧制度では5年制および3年制に分かれていたが、新制度では一律3年課程となる。
<大学>
国立大学では、医学部、歯学部、獣医学部、建築学部を除いて入学試験はない。高等学校卒業資格があれば希望するところに入学できる。入学者数に比べて卒業者が少ないのが特徴的である。
|
| 2)イタリアの障害児教育の変遷 |
近代以降のイタリアにおける障害児教育の変遷をまとめると、次のようになる。
1920年代
特殊教育についての措置が始まる。
1928年
盲および聾の単一障害のある児童に限って、義務教育の対象になる。
1948年
イタリア共和国憲法が制定される。第3条に平等原則の規定、第34条に障害のある人々の教育と就労への権利が規定される。
1968年
障害児のための幼稚園の設置の議論が始まる。
1970年
障害者のための学校を作るために、リハビリテーション研究や障害の予防、建築物の改築などを検討する機関を設置する法律が制定される。
1971年
法律第118号。「義務教育は公立学校の通常の学級で行われるべきであるが、知的に遅れていたり、身体に障害があり、通常の学級での学習が困難な場合はその限りではない」とされ、障害児のための学校を作ったり、リハビリテーションに関する研究、障害の予防、建物の改善をしたりするなど障害児のために特別な弾力的運営を勧告する法律であった。
1974年
法律第416号。学校運営について、父母、教師、他の学校の教員ならびに生徒が共同参加することを規定した法律が制定される。学校運営が学校長、教員協議会、学校協議会、学年協議会によって行われることになった。
1975年
内閣委員会(上院議員ファルクッチ氏が委員長)の勧告。
「公立学校が障害児の教育の場として最も大切な場であり、分離した特殊教育的な施設を廃し、幼稚園から中学校まで通常の学校の中で教育が行われるような新しい運営が必要である。」
1975年
障害児教育のための師範学校が廃止される。
1977年
法律第517号「義務教育段階においては、障害が重篤な場合以外は、障害のある児童は通常の教育を受ける」ことが義務づけられた。
1987年
憲法裁判所判決215号高等学校への就学に関する法律118号28条3項の条文「高等学校への就学を容易にする」を違憲とし、「高等学校への就学は保障されなければならない」ものとした。
1988年
第262号通達「後期中等教育(高等学校)における、障害のある生徒の通常の学級での受け入れと学校のバリアフリー化」を勧告した。
1989年
支援教師資格を得るための2年間の専門研修課程制度が設けられる。2年間に1300時間の研修を受け、試験に合格すると支援教師としての資格が取得できる。
1992年
法律104号「障害者の援助、社会的統合および諸権利に関する基本法」が制定される。
この法令では、「学習の困難性やハンディキャップに関係する能力的欠如から生ずるその他の困難性によってその権利は妨げられない」と規定されており、大学を含む全ての学校段階で、障害のある児童生徒が通常の教育を受ける権利を補償されることになった。以後、この法律が障害児者の通常学級での教育の根拠となり、今日に至っている。
1993年
第81号法「障害の認定および学校日常生活の支援に関する法律」が定められた。
1997年
第59号法「義務教育に関する地方自治体への権限委譲、公的行政改革と簡素化」が定められる。
1998年
支援教師の養成に関する法律の整備
|
表1.学校教育に関連するデータ − 学校数
| |
国立 |
非国立 |
合計 |
| |
N |
% |
n |
% |
n |
| 幼稚園 |
13,624 |
52.2 |
12,498 |
47.8 |
26,122 |
| 小学校 |
17,544 |
90.3 |
1,874 |
9.7 |
19,418 |
| 中学校 |
8,049 |
91.2 |
780 |
8.8 |
8,829 |
| 高等学校 |
5,967 |
76.0 |
1,881 |
24.0 |
7,848 |
| 総計(全学校区分) |
45,184 |
72.6 |
17,033 |
27.4 |
62,217 |
| 幼稚園を除く総計 |
31,560 |
87.4 |
4,535 |
12.6 |
36,095 |
|
表2.学校教育に関連するデータ − 児童生徒数
| |
国立 |
非国立 |
合計 |
| |
N |
% |
n |
% |
n |
| 幼稚園 |
917,881 |
97.6 |
676,181 |
42.4 |
1,594,062 |
| 小学校 |
2,618,077 |
93.0 |
198,084 |
7.0 |
2,816,161 |
| 中学校 |
1,740,355 |
96.3 |
66,258 |
3.7 |
1,806,613 |
| 高等学校 |
2,449,347 |
93.2 |
179,030 |
6.8 |
2,628,377 |
| 総計(全学校区分) |
7,725,660 |
87.3 |
1,119,553 |
12.7 |
8,845,213 |
| 幼稚園を除く総計 |
6,807,779 |
93.9 |
443,372 |
6.1 |
7,251,151 |
|
表3.学校教育に関連するデータ − 障害児数と比率
| |
1997〜98 |
1998〜99 |
| |
障害児数 |
割合 |
障害児数 |
割合 |
| 幼稚園 |
9,896 |
1.08 |
10,012 |
1.09 |
| 小学校 |
49,279 |
1.88 |
50,746 |
1.95 |
| 中学校 |
42,244 |
2.46 |
42,169 |
2.50 |
| 高等学校 |
13,362 |
0.55 |
14,094 |
0.60 |
| 総計(全学校区分) |
114,781 |
|
117,021 |
|
| (出典:イタリア公教育省「The Italian Education system」(1999)および今回の調査による聞き取り) |
|
| 3)支援教師(Insegnanti di sostegno) |
イタリアでは、1971年から公的にインクルーシブな教育が開始されている。その当時から障害のある児童生徒を支援するための職員がいたが、教員資格のある人が担当していたわけではなかった。その後、支援者の役割の重要性が認識されるようになり、1989年になって、支援教師の資格が制度化された。
(1)支援教師の役割
支援教師は、障害児のいるクラスに入って、担任教師とティームを組んで指導にあたる。支援教師は障害児を直接支援するだけではなく、クラスメートが障害児を支援するように配慮したり、学級全体の活動に留意しながら、障害のある児童生徒だけでなく、クラス全体に対しても責任をもつこととされている。
(2)支援教師の配置
支援教師の配置については、当初障害のある児童生徒3〜4名に1名が配置されることになっていた。また対象児童生徒の障害の程度によって、その配当時間が異なるものとされ、週4時間〜22時間の間で時間数が決められていた。しかし、その後、障害児に対して支援教師を配当するのではなく、全児童生徒の数に応じて支援教師の必要性を割り出す方式に変更されている。現在では、児童生徒138人に対して支援教師を一人配当することが基準になっている。しかし、これはあくまでも目安で、障害が重度の場合は、1対1で支援教師がつき、軽度の場合は一人の支援教師が2〜4人を担当するようになっている。
(3)支援教師の資格
支援教師の資格は、大学卒業後さらに2年間のディプロマコース(2年間)を修了することにより習得することができる。一般の教員も研修により資格を得ることができる。支援教師の養成課程には、7つのレベルがあり、すべての障害をカバーするようプログラムされている。7つのレベルをすべて修得することにより支援教師として認定される。
(4)支援教師の待遇
支援教師の給与体系は、一般の教員と同一であり、特別な配慮はされていない。
|
|





