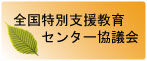ホーム > メールマガジンバックナンバー >
国立特別支援教育総合研究所メールマガジン 第8号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国立特別支援教育総合研究所メールマガジン 第8号 2007.11.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ NISE ━ 【目次】 ■研究所からのお知らせ ■今月の特集 ■研究所の研究活動 ■特別支援教育トピックス ■研修員だより ■編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■研究所からのお知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●NISE 障害者週間関連行事のご案内 「障害者週間」(12月3日~9日)にあたり、研究所では、より多くの方々 に障害について理解していただきたく、次の3つのNISE障害者週間行事を実 施します。行事はすべて参加費無料で、どなたでも参加できます。お申し込 みについては、下記ご案内及び Webサイトをご覧ください。 ▼第1弾 ---------------------------------------------------------- 第27回アジア・太平洋特別支援教育国際セミナー/NISE 障害者週間パネル展 「共生社会を目指し、子ども一人一人のニーズに応じた教育の発展を考える」 -------------------------------------------------------------------- ■2007年度テーマ 「地域の社会資源と連携した、特別なニーズのある子どものための学校 運営 ~その工夫と課題~」 ■開催日程 平成19年12月4日(火)~12月6日(木) ■会場 横浜シンポジア(横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタ-ビル9F) ■基調講演 講師 寺崎 千秋 氏 財団法人教育調査研究所研究部長(前・ 全国連合小学校長会会長) ■参加予定国 オーストラリア、バングラデシュ、中国、インド、インドネシア、 日本、マレーシア、ニュージーランド、ネパール、パキスタン、 フィリピン、韓国、スリランカ、タイ 【日英同時通訳が付きます】 ○参加者募集パンフレットはこちら(PDF 177KB)→ http://www.nise.go.jp/PDF/27thseminarbrochure.pdf ○国際セミナー参加のお申し込みはこちら→ http://www.nise.go.jp/blog/2007/09/nise_2007.html ○これまでのセミナーの概要はこちら→ http://www.nise.go.jp/blog/kokusai2.html#asia ▼第2弾 ---------------------------------------------------------- NISE障害者週間 2007 体験学習会 「発達障害児ってどんな子ども? ~疑似体験からさぐる理解と支援~」 -------------------------------------------------------------------- 内閣府の主催する「平成19年度障害者週間課題別セミナー」の一環として、 本研究所渥美義賢(あつみ・よしかた)教育支援研究部上席総括研究員によ り、体験学習会を実施いたします。「発達障害児ってどんな子ども?~疑似 体験からさぐる理解と支援~」というテーマで、発達障害児の理解と支援の ために、発達障害の特性などの概要について講演を行い、注意と認知の困難 さに関する体験学習会を行います。どなたでも参加できます。参加申込受付 中。 ■日時 平成19年12月4日(火) 18:30~20:30 ■会場 有楽町朝日スクエア 千代田区有楽町2-5-1有楽町マリオン11F 電話 03-3284-0131 ■参加費 無料 ○NISE障害者週間 2007 体験学習会への参加の方法は こちら→http://www.nise.go.jp/blog/2007/09/nise_2007_3.html ○有楽町朝日スクエア詳細はこちら→ http://www.asahi-hall.jp/yurakucho/access/index.html ▼第3弾 ---------------------------------------------------------- 平成19年度第32回特別支援教育教材教具展示会(財団法人障害児教育財団) -------------------------------------------------------------------- 前号でもご案内させて頂きました、標記について、優秀な作品を表彰し、 下記期間に優秀作品を展示します。 ■開催日程 平成19年11月28日(水)~12月11日(火)(土・日を除く) ■会場 国立特別支援教育総合研究所 大会議室(管理棟2階) ○お問い合わせ先は→ (財)障害児教育財団事務局 〒239-8585 神奈川県横須賀市野比5丁目1番1号 電話 046-839-6888 ●平成20年度特別支援教育研究研修員制度について 平成20度特別支援教育研究研修員制度実施要項を決定し、研究研修員の推 薦について関係都道府県等教育委員会等に照会しています。 この「特別支援教育研究研修員制度」は、各都道府県等において特別支援 教育の推進の中核となる教職員を対象に、本研究所が政策的な課題や喫緊の 課題について実施する「プロジェクト研究」等に直接参加し研究を行うこと により、各都道府県における特別支援教育のリーダーとしての資質の向上や 各都道府県等の教育政策や教育研究の推進に寄与する専門性の向上を図るこ とを目的としています。 ■推薦期限 平成19年12月17日(月)厳守 ■研修期間 平成20年4月16日~平成21年3月13日 ■募集人員 各受入研究課題ごとに、1名~2名、計12名程度 ○平成20度特別支援教育研究研修員制度実施要項及び受入研究課題の概要 はこちら→http://www.nise.go.jp/blog/2007/10/20_1.html ○お問い合わせはこちら→総務部研修情報課 専門員(兼)齊藤(046-839-6807) 研修係長 佐藤(046-839-6827) e-mail:━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■今月の特集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●高等教育機関における障害のある学生の支援 渡辺 哲也(教育支援研究部・主任研究員) 教育支援研究部生涯学習担当では、高等教育機関における障害のある学生 の支援について2本の研究テーマを推進しています。そのうち1本は、発達 障害のある学生の支援に関する研究です。これまでの調査研究では、発達障 害のある学生に対する組織的な支援体制のない大学等が多いこと、発達障害 に関する教職員の理解が進んでいないこと、個々の学生に対する支援の目標 設定と評価が明確でないことなどが明らかになりました。そこで平成19年度 から開始した研究では、発達障害のある学生支援に関するセミナーの開催に より教職員の理解啓発を進め、支援体制作りにつなげること、並びに、支援 の目標設定と支援達成度の評価チェックリスト(仮題)の試案を大きな柱と します。この研究は、独立行政法人日本学生支援機構との共同研究の形態で 進めています。 支援目標の設定には、海外の進んだ取組も参考にします。そこで、海外の 高等教育機関における障害のある学生の支援体制について、研究所発行の『 世界の特殊教育』、関連する一般紙・専門誌、高等教育機関の Webサイトな どの情報を収集し、整理を試みています。特に、 ADA(障害のあるアメリカ 人法)などの法律により障害者に対する施策を規定している米国の先進的な 取組は参考になると思われます。整理した情報を研究所 Webサイトへの掲載 や関連研究会における発表を通じて発信することで、今後の障害学生支援の 推進に寄与するものと考えます。 ○共同研究「高等教育機関における発達障害のある学生の支援に関する研 究―評価法の開発と教職員への啓発―」(平成19年度~平成20年度) →http://www.nise.go.jp/blog/2007/04/post_656.html ○調査研究「海外の大学における障害のある学生の支援に関する調査」 (平成19年度~平成20年度) →http://www.nise.go.jp/blog/2007/04/post_707.html ○共同研究「発達障害のある学生支援ケースブック-支援の実際とポイン ト-」(平成16年度~平成18年度) 報告書の内容(PDFファイル)をダウンロードできます。 報告書の冊子体を希望者にお配りします(受付は12月末まで)。 http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub_b/b-210.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■研究所の研究活動 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このコーナーでは、研究所の研究活動について紹介します。 今回は、平成18年度に終了した調査研究1件と、現在も継続中の課題別研 究1件を紹介します。 ●調査研究「障害のある児童生徒等の教育の総合的情報提供体制におけるコ ンテンツの充実・普及方策に関する実際的研究」(平成17年度~18年度)に ついて 渡邉 章(教育研修情報部・総括研究員) 本研究では、障害のある児童生徒等の教育に関する情報提供体制の充実に 資することを目的として、次のような取組を行いました。 1)情報提供体制の整備のあり方 都道府県と政令指定都市の教育委員会及び教育センターの Webサイトによ る情報提供の状況と保護者団体の Webサイトによる情報提供の取組について 検討し、情報提供体制を整備していくための方策について考察を行いました。 2)学校 Webサイトからの情報発信の活性化 研究協力校の協力を得て、地域のセンター的な機能を果たすための学校Web サイトからの情報発信のあり方と情報発信を活性化させるための校内体制作 りについて検討しました。 3)Webアクセシビリティの向上 都道府県と政令指定都市の教育委員会及び教育センターの Webサイトと研 究所 Webサイトのアクセシビリティを調査し、アクセシビリティ向上のため の対応策を検討しました。 4)eラーニング活用のあり方 情報教育担当教員を対象とした講習会と盲ろう児童生徒担当教員を対象と した講習会において、事前学習及び講習会後のフォローアップにおけるeラ ーニングの活用方法について検討しました。 本研究で得られた知見は、今後の研究所の情報普及活動に生かされていき ます。 ○研究の詳細はこちら→http://www.nise.go.jp/blog/2005/08/post_606.html ○研究報告書はこちら→ http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub-b.html ●課題別研究「重複障害児のアセスメント研究―自立活動のコミュニケーシ ョンと環境の把握に焦点を当てて―」(平成18年度~19年度)について 研究代表者 齊藤 由美子(教育支援研究部・研究員) 本研究では、自立活動を主とする重度・重複障害のある児童生徒に対して、 現場の教員が比較的容易に実施でき、実態把握が教育的支援や評価につなが り、教員同士や保護者とも共有できるアセスメントをめざして研究が行われ ています。平成18年度には、重度・重複障害児の教育に携わる教員へのアセ スメント活用についての聞き取り調査、及び、国内外の様々なアセスメント ツールの検討を行ったうえで、視覚を通した環境の把握のアセスメントを検 討・提案しました。研究協力校における試用では、アセスメント結果に基づ いて教員の教育支援が具体的に変化し、児童生徒の視覚活用による環境の把 握が促進されています。今年度は、コミュニケーションの方法や、やりとり の展開に関するアセスメントを研究協力校に提案し、試用と改良を重ねてい ます。 平成20年春に刊行予定の研究成果報告書において、最終的なアセスメント バッテリーを提案し、またそれらを活用して教育支援を行った事例を報告す る予定です。 ○概要はこちら →http://www.nise.go.jp/blog/2007/04/post_646.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■特別支援教育トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このコーナーでは特別支援教育に関連する最近のトピックスを紹介してい ます。 ●第2回特別支援教育全国フォーラムのご案内 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 平成19年度より、障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた適切 な指導や必要な支援を行う「特別支援教育」が始まりました。子どもたちの 自立と社会参加に向け、学校・家庭・地域社会などが一体となって、特別支 援教育を一層推進していくことが、今強く求められています。文部科学省で は、広く国民の皆様に特別支援教育についての理解と認識を深めていただく ため、平成19年12月8日(土)、第2回特別支援教育全国フォーラムを開催 いたします。 ■日時 平成19年12月8日(土)10:00~16:30(開場 9:30) ■場所 東京国際交流館(東京都江東区青海2-79) ■主催 文部科学省 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 全国特別支援教育推進連盟 全国特別支援学校長会 全国特別支援学級設置学校長協会 ■対象者 どなたでも参加いただけます ■参加費 無料 ■申込方法 FAXまたはEメールにて事前にお申し込みください。 今回のフォーラムでは、保護者、医療・福祉、教育のそれぞれの立場から 特別支援教育に求められることをテーマとしたてい談や、(1)特別支援教育 についての基本的な考え方や実践例、(2)関係機関の連携とそれぞれの役割、 (3)職業的な自立に向けた取組などについて、講義と実践事例紹介を踏まえ た意見交換など、多彩なプログラムをご用意しております。 多くの皆様のご来場をお待ちしております。 ○お申し込み、詳細はこちらをご覧ください。(文部科学省HPへリンク) http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/10/07101206.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■研修員だより ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このコーナーでは、研究所に研修に来られた方々からの寄稿やさまざまな 情報提供を行っていきます。今号は、平成19年度第1期特別支援教育専門研 修聴覚障害教育コースの新井先生からお寄せ頂きました。 ●「研修、未だ続行中」 今年度、特別支援教育専門研修員として研修をさせていただきました。初 日のオリエンテーションで、「このプログラムは、密度が高いので多大なエ ネルギーが必要です。」と説明を受けました。実際、驚きや発見や感動の毎 日で、とても刺激を受けました。後半、自分の許容量を超え、消化不良を起 こしましたが、私にとって、かけがえのない時間でした。一日が終わるとぐ ったりしてしまうような充実した講義はもちろんのこと、同じ研修員仲間と の語らいは、全国の情勢を知ることができ、視野を広げることができました。 また、聴覚障害児教育の奥の深さを知るにつれ、どのように、ろうと向き合 っていったらよいのかと考えるようになりました。そして、今自分が携わっ ている早期教育の大切さを改めて感じました。 現在、本校に戻り、幼稚部4歳の担任をしています。子どもを目の前にし て、また研修が始まりました。戻ってきて感じたことは、2ヶ月間だったに もかかわらず、目に見えて子どもの成長がわかったことです。少し離れるこ とで見えてくるものを実感しました。小田理事長の言葉にも、「人と人との 距離」というものがありました。大切なことを見落とさない子どもとの距離、 保護者との距離も考えながら、今後も久里浜で学んだことを実践していきた いと思います。 さいごに、本校が会場となって11月16日(金)に関東地区聾教育研究会( 定例研究会)があります。富士宮焼きそば、しぞーかおでん、浜松餃子など おいしいものもたくさんありますので、グルメの街静岡にぜひお越しくださ い。 ○静岡県立浜松聾学校Webサイトはこちら →http://www.shizuoka-c.ed.jp/hamamatsu-sd/ 静岡県立浜松聾学校 新井 崇史 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■編集後記 今月の特集では、高等教育機関における障害のある学生の支援を取り上げ ました。近年は日本学生支援機構による高等教育機関すべてを対象とした調 査と支援事業の実施、本課題に関するセミナー・シンポジウム等の開催、学 会における事例の報告など、様々な動きが見られます。研究所の今後の研究 成果にも是非期待して頂けたらと思います。 (第8号編集主幹 渡辺 哲也) ○「メールマガジン」へのご意見・ご感想をお寄せください。 こちら→
○研究所メールマガジンのバックナンバーは、こちら→ http://www.nise.go.jp/magazine/back.html ○研究所メールマガジンの利用については、こちら→ http://www.nise.go.jp/magazine/policy.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国立特別支援教育総合研究所メールマガジン 第8号 発行元 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所内 国立特別支援教育総合研究所メールマガジン編集部 メールアドレス:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━