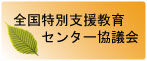ホーム > メールマガジンバックナンバー >
国立特別支援教育総合研究所メールマガジン 第7号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国立特別支援教育総合研究所メールマガジン 第7号 2007.10.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ NISE ━ 【目次】 ■研究所からのお知らせ ■今月の特集 ■研究所の研究活動 ■特別支援教育トピックス ■研修員だより ■編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■研究所からのお知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●NISE 障害者週間関連行事のご案内 我が国は、障害の有無にかかわらず誰もが人格と個性を尊重し支え合う「 共生社会」の実現を目指しています。そのためには、国民一人一人が、障害 について理解し、日常の生活の中で配慮や工夫をすることが必要であり、そ のことで障害のある方の社会参加の機会は広がることと思います。 「障害者週間」(12月3日~9日)は、このような「共生社会」の実現を目 指すため、平成16年 6月の障害者基本法の改正により、従来の「障害者の日」 (12月 9日)に代わるものとして設けられ、この期間中には、国や地方公共 団体、関係団体などにおいて、様々な意識啓発のための取組が展開されます。 本年の「障害者週間」にあたり、研究所では、より多くの方々に障害につ いて理解していただきたく、次の3つのNISE 障害者週間行事を実施します。 皆様に障害の理解を深めていただける一つの契機となり、我が国が目指す 「共生社会」の理想に近づくことができれば幸いです。行事はすべて参加費 無料で、どなたでも参加できます。お申し込みについては、下記ご案内及び Web サイトをご覧ください。 ▼第1弾 ---------------------------------------------------------- 第27回アジア・太平洋特別支援教育国際セミナー/NISE 障害者週間パネル展 「共生社会を目指し、子ども一人一人のニーズに応じた教育の発展を考える」 -------------------------------------------------------------------- ■2007年度テーマ 「地域の社会資源と連携した、特別なニーズのある子どものための学校 運営 ~その工夫と課題~」 ■開催日程 平成19年12月4日(火)~12月6日(木) ■会場 横浜シンポジア(横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタ-ビル9F) ■基調講演 講師 寺崎 千秋 氏 財団法人教育調査研究所研究部長(前・全 国連合小学校会長) ■参加予定国 オーストラリア、バングラデシュ、中国、インド、インドネシア、 日本、マレーシア、ニュージーランド、ネパール、パキスタン、 フィリピン、韓国、スリランカ、タイ 【日英同時通訳が付きます】 ○参加者募集パンフレットはこちら(PDF 177KB)→ http://www.nise.go.jp/PDF/27thseminarbrochure.pdf ○国際セミナー参加のお申し込みはこちら→ http://www.nise.go.jp/blog/2007/09/nise_2007.html ○これまでのセミナーの概要はこちら→ http://www.nise.go.jp/blog/kokusai2.html#asia ▼第2弾 ---------------------------------------------------------- NISE障害者週間 2007 体験学習会 「共生社会をつくるための発達障害児の理解と支援 ~発達障害児の抱える困難の体験と共感を基に~」 -------------------------------------------------------------------- 内閣府の主催する「平成19年度障害者週間課題別セミナー」の一環として、 本研究所渥美義賢(あつみ・よしかた)教育支援研究部上席総括研究員によ り、体験学習会を実施いたします。「共生社会をつくるための発達障害児の 理解と支援~発達障害児の抱える困難の体験と共感を基に~」というテーマ で、発達障害児の理解と支援のために、発達障害の特性などの概要について 講演を行い、注意と認知の困難さに関する体験学習会を行います。どなたで も参加できます。参加申込受付中。 ■日時 平成19年12月4日(火) 18:30~20:30 ■会場 有楽町朝日スクエア 千代田区有楽町2-5-1有楽町マリオン11F 電話 03-3284-0131 ■参加費 無料 ○NISE障害者週間 2007 体験学習会への参加の方法は こちら→http://www.nise.go.jp/blog/2007/09/nise_2007_3.html ○有楽町朝日スクエア詳細はこちら→ http://www.asahi-hall.jp/yurakucho/access/index.html ▼第3弾 ---------------------------------------------------------- 平成19年度第32回特別支援教育教材教具展示会(財団法人障害児教育財団) -------------------------------------------------------------------- 前号でもご案内させて頂きました、標記について、優秀な作品を表彰し、 下記期間に優秀作品を展示します。 ■開催日程 平成19年11月28日(水)~12月11日(火)(土・日を除く) ■会場 国立特別支援教育総合研究所 大会議室(管理棟2階) ■応募 作品募集中! 平成19年10月16日(火)必着 ■賞及び賞金: ・文部科学大臣賞 30万円 ・国立特別支援教育総合研究所理事長賞 20万円 ・障害児教育財団理事長賞 金賞 15万円 銀賞(2作品) 10万円 銅賞(3作品) 5万円 佳作(20作品程度) 1万円 ○募集要項及び応募用紙はこちら→ http://www.nise.go.jp/blog/kyozaitenjikai.html まだ締め切りには間に合いますので、ぜひこの機会に応募してください。 ○お問い合わせ先は→ (財)障害児教育財団事務局 〒239-8585 神奈川県横須賀市野比5丁目1番1号 電話 046-839-6888 ●ちょっと一息 季節のたより -台風9号- 今年の記録的な猛暑から少し解放され、ようやく秋の気配を楽しむ季節と なりました。しかし、10月はまだまだ台風シーズンとも言え、油断は出来ま せん。 さて、神奈川県では5年ぶりに台風が上陸し、多くの被害をもたらしまし た。研究所の目の前の野比海岸沿いの県道は、9月6日午後9時ごろから7日 午前にかけて高波により、歩道が幅約2メートル、長さ約 150メートルにわ たり崩落しました。研究所職員の通勤経路であり、また研修員の散歩コース でもあったこの美しい海岸が一夜にして、コンクリートの瓦礫(がれき)に 覆われ、見るも無惨な光景と変わりました。 海水浴シーズンを終え、今は人もまばらになった三浦海岸。この砂浜のよ うに、かつては野比海岸も遠浅の広い砂浜が広がっていたと言います。コン クリートの瓦礫に埋まった野比海岸を見ていると、昨今の異常気象による被 害も含めて、考えさせられるものがあります。 参考:神奈川新聞 カナロコ・ローカルニュース(平成19年9月7日) →http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiijul0707747/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■今月の特集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●解説:諸外国の特別支援教育の動向について 徳永 豊(企画部・国際比較担当・総括研究員) 我が国では特別支援教育として、新たな教育が展開されつつあります。 諸外国においてもそれぞれの歴史、文化を背景に、特別支援教育の充実を 目指して、関係者の努力が積み重ねられています。例えば、英国では特別な 教育的ニーズという概念で、学習の遅れ等も含む幅広い子どものニーズに対 応する教育が展開されています。 平成16年度より、企画部に国際比較担当が置かれ、ナショナルセンターと して、諸外国の特別支援教育に関する情報の収集、整理、分析に取り組んで います。例えば、英国、米国、フランス、イタリア、ドイツ等の「障害のあ る子どもの就学」「特別支援教育体制」などについて情報収集を行っていま す。 また、アジア・太平洋特別支援教育国際セミナーの一環として、セミナー 参加国の特別支援教育に関する基本情報についても整理しています。 我が国の特別支援教育の展開を見通す上では、諸外国の最先端の取組やそ の歴史的経緯を知ることは、貴重な手がかりとなります。さらに特別支援教 育がこれから本格化するアジア諸国の取組を知ることは、我が国の特別支援 教育の発展を振り返るとともに、その独自性に気づく契機を与えてくれます。 この国際比較研究等で得られた情報については、可能な限り研究所 Webサ イトや報告書等で情報提供していく予定です。 国際交流活動→ http://www.nise.go.jp/blog/kokusai.html 障害のある子どもの就学手続きに関する国際比較‐国連障害者の権利条約検 討の動向に関連して‐(PDF 1.2MB)→ http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub_d/d-241/d-241_04_04.pdf アジア・太平洋諸国の基本データ(英文・PDF 2.1MB)→ http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub_d/d-249/d-249_3.pdf 特別支援教育に関する国際比較→ http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/sekai/hikaku/index.html#pacific ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■研究所の研究活動 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このコーナーでは、研究所の研究活動について紹介します。 今回は、課題別研究を1件と調査研究を1件紹介します。 ●課題別研究 『肢体不自由のある子どもの教育活動における「評価」及び 「授業の改善・充実」に関する研究』(平成18~19年度)について 研究代表者 當島 茂登(教育支援研究部・総括研究員) 本研究では、肢体不自由のある子どもが在籍している各学校や学級での様 々な教育活動における「評価」及び「授業の改善・充実」に関する課題を取 り上げ、多角的に検討しています。現在、研究所がこれまでに実施した調査 研究における教育課程等の評価に関する課題の整理、研究協力機関等へのイ ンタビュー調査、「評価」や「授業の改善・充実」に向け取り組んでいる各 学校の事例の検討を行っています。 本年度第1回目の研究協議会を7月に研究所で開催しました。研究協議会 では、研究分担者より研究所の調査研究における「評価及び授業改善」に関 する課題の整理、授業の評価とその改善・充実について報告し、研究協力機 関については各学校における「評価」及び「授業の改善・充実」に関する取 組を報告して頂きました。これらの報告を踏まえて、学校における「評価」 及び「授業の改善・充実」の課題と必要とされる取組について協議を行いま した。現在、この協議で挙げられた課題と必要とされる取組の内容を分類し、 報告書に掲載するQ&Aの項目を検討しています。 本研究の成果として、取り上げられた課題等を整理・分析し、特別支援学 校や特別支援学級において活用できる報告書の作成を目指しています。報告 書は、第1章(概論編)、第2章(Q&A編)、第3章(学校事例編)で構 成する予定です。 ○本研究についてはこちら→ http://www.nise.go.jp/blog/2006/06/post_671.html ●調査研究「乳幼児期からの一貫した軽度発達障害者支援体制の構築に関す る研究-乳幼児期における発見・支援システムの実態調査を中心に-」(平 成17~18年度)について 研究代表者 後上 鐵夫(教育相談部長・上席総括研究員) 発達障害児に関する関心は大きく高まっているものの、発達障害児を取り 巻く環境の実態、発達障害やその可能性のある乳幼児の発見やその後の支援 が、システム的に確立し得ていない現状があります。特別支援教育を深化さ せていくためにも、軽度発達障害児の乳幼児期における実態を把握し、その 支援システムを構築していくことは重要な課題です。 そこで本研究では、就学前期における軽度発達障害児の発見システムや支 援システムがどのようになっているかの実態を調査することで、軽度発達障 害者に対する一貫した支援体制、特に乳幼児期を中心にした支援体制を構築 するための基礎資料を得ることを目的としました。その結果、以下のような ことが考えられました。 ○乳幼児健診は、軽度発達障害やその可能性のある幼児を早期に発見する 場として有効であるようです。しかし、軽度発達障害やその可能性のある 幼児の発見・支援を視野に入れた場合、スクリーニングの方法やその精度、 心理職の配置の少なさといった面では課題があります。また、健診業務に は多職種のスタッフがかかわっているという実態がありますので、健診業 務を担うスタッフの連携や力量を高めるための研修、紹介先の専門機関や、 子どもの在籍する機関とのきめ細やかな連携も、支援をすすめていく上で 重要であると考えます。 ○幼稚園・保育所調査からは、集団生活の利点から、幼稚園・保育所生活 の中で、幼稚園・保育所関係者によって、多くの軽度発達障害やその可能 性のある幼児が、3歳時をピークに4歳時までに気づかれていることが明ら かになりました。このことからは、幼稚園・保育所関係者が、軽度発達障 害やその可能性のある幼児についての理解を深めることで、配慮を必要と する幼児に早期に気づくことが可能になると思われます。この気づきを有 効にしていくためには、地域にある保健センターなどの母子保健業務を担 う保健師や心理職には、幼稚園・保育所での支援の場のアドバイザー役が 期待されます。また、病院に入院している幼児の院内保育に携わる保育士 の研修のように、障害のある子どもの保育にたずさわる職員の研修の機会 の確保は、必須と考えます。 (参考)調査研究報告書「乳幼児期からの一貫した軽度発達障害者支援体 制の構築に関する研究」-乳幼児期における発見・支援システムの実態調 査を中心に- 平成19年3月発行 ○上記報告書はこちら→ http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub-b.html ○概要はこちら→http://www.nise.go.jp/blog/2005/08/post_522.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■特別支援教育トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このコーナーでは特別支援教育に関連する最近のトピックスを紹介してい ます。 ●特別支援教育課に「発達障害支援係」を新設 (文部科学省初等中等教育局特別支援教育課) 文部科学省では、平成19年度から本格的に実施された特別支援教育の重要 な支援対象の一つである発達障害の支援体制を強化するため、10月 1日付け で特別支援教育課に「発達障害支援係」を新設しました。 これまで文部科学省には、「発達障害支援専門官」及び「発達障害教育担 当特別支援教育調査官」は設置されていましたが、発達障害を専門に支援す る係はありませんでした。 一方、厚生労働省には、すでに精神・障害保健課に「発達障害支援係」が ありましたが、今年5月に「発達障害対策専門官」が新設されて体制が強化 されています。 今後とも、両省連携を深めながら、発達障害のある子どもの支援を進めて まいりますので、よろしくお願いします。 ●中央教育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会について 平成19年 9月18日に行われた「中央教育審議会 初等中等教育分科会教育 課程部会(第4期10回)」の配付資料が、文部科学省の Webサイトにおいて 公開されています。 ○文部科学省 審議会情報のページはこちら→ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/004/07092002.htm ●感覚器障害戦略研究の実施について 厚生科学審議会科学技術部会において検討されていた感覚器障害戦略研究 の実施について、財団法人テクノエイド協会の Webサイトに掲載されていま す。 ○詳細はこちら→http://www.techno-aids.or.jp/senryaku.shtml ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■研修員だより ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このコーナーでは、研究所に研修に来られた方々からの寄稿やさまざまな 情報提供を行っていきます。今号は、平成18年度長期研修員の中元晶子先生 からお寄せ頂きました。 ●「新たな思いで教育実践を」 「はまゆう」は砂地に咲くヒガンバナ科の白い花です。私が勤務するはま ゆう養護学校は、和歌山県南部に位置する知的障害のある児童生徒を対象と する特別支援学校です。真っ白な砂浜の海と世界遺産である熊野古道の山や 川に囲まれ、すばらしい自然環境にある学校です。本校も「特別支援学校」 として、地域の幼稚園・保育所・小中学校・高校から、教育相談などセンタ ー的な役割を担い特別支援教育の推進に努めているところですが、近年その ニーズは急速に増加しています。 昨年度、私は長期研修員として一年間、主に自閉症の子どもの教育的支援 と授業評価・改善に関する課題研究に取り組みました。研修を終えて、今年 4月に学校に復帰してからは、小学部1年(5名全員自閉症の児童)を担当 し、元気によく動き回る子どもたちを相手に、体力勝負の毎日です。また、 コーディネーターとして地域支援に携わっています。そのような日々の中で、 以前とは違って、教育実践を経験としてだけでなく、仮説と検証、考察とい う視点をもって考えられるようになったのではないかと実感しています。 研究所での研修を通じて知識や情報もたくさん得られましたが、なにより そのような視点で自身の、また学校や地域の教育活動を見つめられるように なったことは、長期研修の大きな成果であり、今後の私の教員生活に新たな 境地が開拓された思いです。この糧を生かし、和歌山からも、積極的に教育 実践の取り組みについてメッセージを発信していきたいと思っています。 ○和歌山県立はまゆう養護学校 Webサイトはこちら →http://www.hamayuu-sh.wakayama-c.ed.jp/ 和歌山県立はまゆう養護学校 中元 晶子 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■編集後記 とりわけ暑かった今年の夏もいつしか過ぎて、秋らしさが感じられるよう になりました。研究所メールマガジンの刊行は、今号で第7号となりました。 創刊準備号以来、編集メンバーで検討しながら、メールマガジンを編集し、 お届けしてきました。平成19年 9月25日時点で、研究所メールマガジンの登 録者数は、 886名となりました。登録者数は順調に増えています。お知り合 いの方々にも、ぜひこの研究所メールマガジンのことをお伝え下さい。より 多くの方々に研究所メールマガジンを読んでいただければと思います。 (第7号編集主幹 渡邉 章) ○「メールマガジン」へのご意見・ご感想をお寄せください。 こちら→○研究所メールマガジンのバックナンバーは、こちら→ http://www.nise.go.jp/magazine/back.html ○研究所メールマガジンの利用については、こちら→ http://www.nise.go.jp/magazine/policy.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国立特別支援教育総合研究所メールマガジン 第7号 発行元 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所内 国立特別支援教育総合研究所メールマガジン編集部 メールアドレス:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━